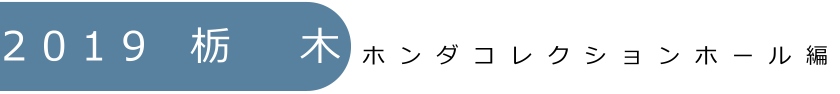
すでに述べたように本田宗一郎総司令官の暴走により、ホンダは1968年に3000㏄で空冷、強制冷却ファンなしという狂気のエンジンを投入して来ます。そして結局、7月の第6戦フランスGPで一度だけ出走して、ドライバーが事故死して終わるという考え得る限り最悪の結果に終わりました(後にもう一度、9月のイタリアGPで予選だけ出走したが)。
これがRA302
と呼ばれる車になります。当然、その空冷エンジンはRA302E
となりますが、1966年のヨーロッパF-2で無敵の快進撃を決めた1000㏄エンジンの名前もRA302Eであり、すなわち同じ名前で全く異なる二つのエンジンがホンダには存在するので要注意。片や傑作エンジン、型や歴史に残る失敗作ですが、両者ともに設計は久米さんなので、最初の設計方針がダメだと技術者がどんなに頑張ってもどうしようもないのだ、といういい例かもしれません。
ちなみにフランスGPで事故により焼失した後、本田宗一郎総司令官の執念でもう一台造られイタリアGPで予選だけ走った車が、このコレクションホールにあるはずなんですが、今回の見学時には残念ながら見る事ができませんでした。
そして同時に空冷F-1に徹底的に反対した中村監督が従来の車からの正常進化型の制作も進めてました。これがRA300
に続いてローラ社に車体の開発を依頼したRA301となります。こちらに搭載された常識的な水冷エンジンはホンダ製で、設計はF-1番長の川本さん。
この車が第二戦から最終戦まで投入され、サーティスの運転で2位一回、3位一回と二度の表彰台を獲ったものの最後まで優勝は無しの結果に終わるのです。
イマイチな結果に終わった1968年ですが、この年のF-1エンジンは1966年のヨーロッパF-2で無敵の快進撃を見せたエンジン設計チーム、久米さんと川本さんが設計を担当していました。ただし既に見たように両者で一つのエンジでは無く、ほんとど無意味と言っていい空冷エンジンを久米さんが、主力になる水冷エンジンを川本さんが担当と言う、ここでも戦力の分散投入が行われる事になります。さらに久米さんが空冷エンジンに悩みぬいてノイローゼ気味となり二度の失踪をした後(涙)、川本さんが一人で両者のエンジンの面倒を見る事になります。こうなるともはやまともな開発は不可能となってしまうのです。

ホンダ第一期の事実上の最後の車、RA301(空冷RA302は第6戦 フランスで一回走ったのみなので無かったに等しい)。
この年の第一戦南アフリカGPは正月元旦開催と言うメチャクチャなスケジュールだったため、前年後半に登場したRA300
で戦い、第二戦、5月12日のスペインからこのRA301の投入開始となりました。ちなみに第一期ホンダF-1でもっともカッコ悪い車だと個人的には思ってます。
エンジン前部上の銀色の箱は空気取り入れ用の吸気筒(カタカナ英語スキーの皆さんが言う所のファンネル)を収めたもの。
ただし当然、これではエンジンに空気が入りません。通常は金網で出来た箱状のゴミ避けが乗っているはずで、なんでこんな植物プランターのような箱を乗っけているのかは不明。
それでもとりあえず、この銀色の箱の背の高さから、吸気筒(ファンネル)の背が高い、つまり長くなっており、1500㏄時代のようにお猪口みたいに短くて狂ったような高回転用セッティングで無いのが見て取れます。5年でホンダもだいぶ大人になり、とにかく高回転で回せばいい、という時代を卒業していたわけです。
この車もまた、例によって開発は遅れまくりました。
まず、1968年1月に完成予定だったローラ社が担当する車体は下請け工場の作業遅延などにより2月中旬になってようやく形になりました。さらにこれを2月末に日本に持ち込んでホンダで造ったエンジンと合体させようとしたところ、本田宗一郎総司令官が陣頭指揮を執る空冷エンジンを優先させていたため、水冷エンジンはまだ影も形もない状態であることが判明します。
ところがこの段階でサーティスとローラ社の技術者はテストのために来日してしまっており、彼らはその後、2か月近く日本に足止めを食らい、ホンダの技術研究所に要らぬ不信感を抱かせる結果になってしまいます。当然、これも悪影響の一つとなりました。結局、ホンダの水冷エンジンが組み上がったのは4月の中旬ごろ。そして、ここから車体への搭載、テストコースとなる鈴鹿への運搬が行われます。ただし第二戦スペインGPは5月12日であり、当時の輸送事情ではわずか二日前後のテストでこれをヨーロッパに送り出す必要がありました。
結局、今回もまた、ほとんどまともにテストが出来てないマシンでホンダは戦う事になったわけで、この辺りも本田宗一郎総司令官の悪い部分が出てる所でしょう。
この年からF-1でもタイヤの接地圧向上を目的とする空力装置が車体に搭載されるようになりました。
それがウィングとスポイラーであり、ホンダもシーズン途中の第4戦ベルギーから搭載を開始、その改良を進めます。展示の車体はおそらく第11戦アメリカGPの時の仕様で、後部に翼断面を持つ大型のウィング、フロントに一種の気流遮断板(スポイラー)が付いてます。この辺りのレーシングカーにおける空力装置については後で少し詳しく見ましょう。ついでにカタカナ英語乱発のこの辺り、よくウィングとスポイラーがゴチャゴチャになってるのを見かけますが、両者は別物ですから要注意。
ちなみにさすがはローラと言う感じで、車体は軽量に造られており、そこにエンジンの軽量化に積極的だった川本さんによる水冷エンジンが搭載された結果、車体重量は歴代最低の530㎏前後まで絞られていました。ようやく他のチームに追いついた、というレベルですが大きな進化だったのは確かです(ただし後から完成した空冷RA302はラジエター類が無い分、ホンダ製の車体でも軽く、重量規定の最低値500㎏前後だったとされる)。
また、この年からロータス辺りを皮切りに車にスポンサーのステッカーを車体に貼り、スポンサー料を受け取るようになり始めます。
このRA301でもタイヤやオイル、石油会社のロゴが車体各部に見えてますが、これは中村監督が少ない予算を少しでも補うため、積極的にスポンサー料を取る方向にしたた結果で、これによって一定の活動資金を確保する事に成功したようです。どうも本田宗一郎総司令官の意向に逆らって、ローラ社と独自のマシンを開発できたのは、この辺りの資金があったからではないか、と思うのですが詳細は不明。
すなわち1968年は空力装置とスポンサーシステムの導入が本格的に始まった近代F-1元年とも言える年だったわけです。この年を境にホンダが手を引いたのはある意味、象徴的であるな、と思います。この後、どんどん近代化して行くF-1に当時のホンダがどこまでついて行けたかは、正直、疑問を感じるところではあるのです。

後ろから見るとこんな感じ。エンジン周りはキチンと左右対称になっておらずあまりキレイにまとまってない、という印象です。
ついでにケツのギアボックスの上にミッションオイルクーラーと思われるものがある場合と無い場合があり、どうもコースや天候でいろいろ変えていたようですが、詳細は不明。
前作、入交さんのRA273EではV型エンジンの中央部、両側のシリンダーヘッドの間から出していた排気管をこのRA301Eエンジンからは外側に出すように変更してるのが最大の特徴です。このため排気管の取り回しが写真右に見えてるRA300
とはまるで違うものとなってます。RA273Eの排気管配置では吸排気の効率上昇の妨げになる事が判ったためで、これだけで一定の出力アップがあったようです。
ついでにV6型エンジンを縦に二台つないたような形でV12エンジンとする構造から、片側直列6気筒を左右に並べて12気筒にする常識的な構造に変わってます。最終的に450馬力まで出たとされますが、RA300
の段階でエンジン馬力は420馬力まで出てましたから、やはり高回転高出力より低回転からの立ち上がりと言う、ホンダエンジンの欠点改良に主眼があったように感じられるエンジンです。
ついでによく見るとフロントサスペンションのスプリング、緩衝器がむき出しの外付けになっており、これは退化じゃん、と思ってしまう所です。この辺り、ローラ社なりの考えがあったのか、日本人相手ならこれで十分とナメられていたのか、詳細は不明。
大きなリア ウィングには傾きを調整する支柱がついており、さらに車体では無くアップライト(Upright
/
上下のサスペンションアームを繋いでホイルを固定する縦長なパーツ)に直結されてます。そもそもタイヤの設置圧を上げるための装置なので、初期のレーシングカーではこういったタイヤ周辺に直結構造が普通でした。ただし構造的には弱いので折れる事が頻発し、以後は太い支柱で車体に固定されるようになってゆきます。後に安全対策で高さ制限も行われ、今見るような後部ウィングに行き着くわけです。
ここに展示が無い空冷F-1、RA302についても少しだけ触れて置きましょう。
本田宗一郎総司令官が1968年は空冷で行くと決断したのは、1967年の夏前、つまりイタリアGP
で二勝目を挙げる前の段階でした。その空冷F-1マシン、RA302の車体設計はRA271&272 の設計とRA300
でローラと共同作業を経験した佐野さんが担当します。彼によると、翌1968年は空冷で行く、と聞かされたのはローラでRA300を造ってる最中だったとされますから1967年の夏前にはその決定がなされていたはずです。
これは後の空冷普通車、ホンダ最大の失敗作とも言えるH1300
の開発開始とほぼ同時であり(最終的な規格決定が同年9月だから本田宗一郎総司令官はその前から空冷化を決めていた)、N360
の空冷エンジンの成功に気を良くした彼の暴走でした。

1969年に発売され、ホンダの経営を崖っぷちまで追い込んでしまう空冷エンジン搭載普通車、H1300(写真は4連キャブレター搭載型)。本田宗一郎総司令官の空冷エンジン信仰が引き起こした悲劇ですが、ほぼ同時にF-1でも空冷化が行われたのです。F-1で空冷エンジンというのはポルシェによる前例があったのですが、小型の1500㏄時代の話であり、強制冷却ファンを積んでの運用でした。しかも1964年の撤退までに30戦以上出走しながら、1962年のフランスで一勝しただけです。
そういった現実を見ずに本田宗一郎総司令官は3000㏄のエンジンで強制冷却ファン無し、単純な空冷エンジンの設計を命じます。無理と思われる技術に挑戦する、はホンダのモットーですが、地球上で生きる我々が物理法則を超えることはできません。よってこの辺りは完全に狂ってる、というべきでしょう。
ちなみに車体設計の佐野さんは、エンジン空冷化は本田宗一郎総司令官なりに軽量化対策を考えた結果だったのではないか、としてますが本人はそういった発言を一切残してないので、何とも言えませぬ。同時に彼が入れ込んでいた市販のH1300
に軽量化の意味はほとんど無いので、この説はちょっと怪しい気がします。
「空冷だって水冷だって最後は空気で冷やすんだから、空冷でいいじゃないか」というのが本田宗一郎総司令官の持論ですが、言うまでもなく暴論です。熱力学による冷却手段は、放射(赤外線などの電磁波によるエネルギー消失)、伝導(密着してる物体への熱の伝導)、対流がありますが、エンジンの冷却では放射と伝導により行われ、特に伝導が主になります。
エンジンから熱を奪う接触物質が高密度の液体(たくさんの原子がある)と低密度の気体(エネルギーを受け取る原子が少ない)では液体の方が有利なのは明らかです。が、そんな熱力学の基礎知識が無くても、熱い鉄板をウチワで仰ぐのとバケツで水をかけるのとでは、後者の方が圧倒的に素早く冷却される、という体験的な事実からも簡単に理解できるはずのモノでした。これを本田宗一郎総司令官は無視します。
そしてこの空冷F-1エンジンの設計を命じられたのがエンジン設計のエース、久米さんでした。後の三代目ホンダ社長になるこの方も理論よりは経験で設計をするタイプだったものの、やる前からどう考えてもダメだろう、と感じていたようです。
当然、設計は迷走に迷走を重ね、とても1968年の開幕には間に合わない、それどころかまともに走るのも無理だ、という事が徐々に明らかになりました。それでも冷却ファンの装着すら認めない本田宗一郎総司令官の執念に耐えかねた久米さんは、とうとう出社を拒否、一カ月以上家に籠って出て来なくなってしまうのです(第一回失踪)。その段階で一応、エンジンの完成は見ていたものの、当然、レースで走れるようなシロモノではなく、これによって空冷F-1の開発は完全にストップしてしまいます。
その後、後の二代目社長、当時の技術部門の事実上のトップだった河島さんに説得されて久米さんはようやく会社に戻るのですが、本田宗一郎総司令官の熱意は冷めてませんでした。このため最終的に一度レースに出して、全くダメだと証明するしかないと考え、車体設計の佐野さんと協力して7月のフランスGPに送り込むべく作業を開始します。この段階でせめてまともなオイルクーラーでも、考えたのですが、あくまで自然冷却にこだわる本田宗一郎総司令官の許可が出ず、結局、現地でこっそりこれを取り付けることにするなど、苦渋の決断が続きました。
最終的に中村監督の大反対にも関わらず、ホンダの空冷F-1は現地に運び込まれたのですが参加申し込みが間に合わず、一度はフランスGPでの出走を拒否されます。中村監督はむしろこれを歓迎したのですが、当時、フランスでホンダの代理店を経営していた人物が裏で手を回して、最終的に出走可能にしてしまったのです。
その引き換え条件がフランス人をドライバーとする、であり、そこで選ばれたのがF-1には過去二回しか乗ってないジョー・シュレッシー(Jo
Schlesser)と言う40歳のベテランドライバーでした(日本の資料では英語読みのジョー・シュレッサーとされる事が多い)。
このフランスGP直前、ホンダのF-1チームの基地があったイギリスに持ち込まれた空冷RA302はシルバーストーンサーキットでテストを行っています。なにせ軽量だったので加速はよく、それなりに走ったのですが、それはエンジンを熱を持つまででした。結局、オイルクーラーを積んだくらいでは全く問題は解決しておらず、あっという間に熱で沸騰したオイルが噴き出し、まともに走らなくなってしまう事が判明します。
この時の走行タイムはコースレコードから7秒遅れと言うもので、とてもレースで走れるとは思えませんでした。それでもフランスGPに出場したのは、現地に飛んで空冷マシンの責任者となっていた久米さんが、本田宗一郎総司令官の執念と熱意を知っており、走らせないわけにはいかない、と判断したからだったようです(ちなみに車体設計の佐野さんも現地入りしてる)。
フランスGPが始まると、とにかく熱への耐久性の無いエンジンだったため、中村監督は「絶対に速く走るな」という前代未聞の指示をシュレッシーに与えて予選に送り出したとされます。このため彼はトップから8秒以上の遅れと言うタイムで走り、それでも予選中に三度のスピンを起こしたのですが、これがシュレッシーの腕の問題なのか、RA302の機械的な問題なのかは不明です。
最終的にトラブルに見舞われた一台の前、18台中17位の順位でRA302は本選に進むのですが、不幸にして雨のレースとなりました。本来ならエンジンが冷える条件となるんですが、慣れないドライバーに滑りやすい路面は危険であり、その危険の方が上回ってしまったのです。この結果、レースが始まって僅か三周で、シュレッシーの乗るRA302は高速コーナーでコースアウトしてクラッシュ、炎上、シュレッシーは車から脱出できずに焼死してしまいました。まだ燃料が満載のタイミングで、不幸にして軽量化のためマグネシウムを多用していたホンダの車体は火に弱かった、という不運が重なりました。
ちなみにシュレッシーの甥である、ジャン ルイ ポル シュレッシー(Jean-Louis
Paul
Schlesser)もレーシング ドライバーで1988年にウィリアムズから生涯を通して一度だけF-1に参加しました(エースのマンセルが病欠した代理ドライバーとして)。それがあの因縁のイタリアGPなのです。
この1988年はマクラーレン ホンダが伝説の16戦中15勝を遂げた年なんですが、唯一逃した一戦がイタリアGPでした。この時、ほぼ最後までマクラーレンのセナがトップを守っていたのに、最後の最後、周回遅れだったシュレッシーとの接触に巻き込まれてリタイア、16戦16勝記録を逃してしまうのです。すなわち前年までのパートナーだったウィリアムズのマシンに乗って、ホンダのF-1で唯一事故死した人物の甥に巻き込まれる形でホンダはリタイアに追い込まれ、歴史に残る記録、全戦全勝を達成できずに終わった、という事になります。ついでにこの時のホンダ社長は問題の空冷エンジンを設計した本人、三代目社長となった久米さんでした。

全16戦中15戦、勝率93.7%という驚異の記録を打ち立てた1988年のマクラーレン
ホンダ
MP4/4。その記録を阻んだのは周回遅れで走ってた誰も知らないような二流ドライバー、という意外な結果に終わるのですが、その誰も知らない、たまたまこの一戦を走っていた男が、ホンダのマシンで死んだシュレッシーの甥だったのです。何か因縁を感じる部分ではあります。
話を1968年に戻しましょう。
この事故で久米さんは空冷側の責任者としてシュレッシーの遺族への対応や警察とのやり取りに奔走し、中村さんもそれに巻き込まれる形で両者ともレースどころではない状態に追い込まれます。さらに中村監督の空冷F-1への怒りは久米さんに向けられてしまい、現地でさんざん非難されました。こうして精神的に参ってしまった状態で帰国して見れば、本田宗一郎総司令官の執念は衰えておらず、人が一人死んだのに、まだまだ空冷F-1をやる気満々でした。とりあえずそれに付き合った久米さんですが、最後は本田宗一郎総司令官と全面衝突、再び出社拒否して、今回は一月近く旅に出てしまったのです(第二回失踪)。
この時も再び河島さんが間に入ってホンダを退社する決意だった久米さんは現場に引き戻されます。ただし、さすがに空冷F-1は外されたものの、同じ空冷エンジンのH1300の開発に送り込まれ、頭を抱える事になるのですが…。
後に本田宗一郎総司令官がホンダの技術研究所社長を退任したのは本人の意思という形でしたが、それ以前から久米さんが研究所全体をまとめて本田宗一郎総司令官に退役を求める状況を作り出していたのも事実でした。この辺りの関係の根っこが空冷エンジンを巡る葛藤にあったように思います。
ただし久米さんは本田宗一郎総司令官に最後まで敬意を持って接した人でしたから、この辺りの葛藤は当事者にしか判らない部分がいろいろあるようです。
こうして久米さんが投げ出した空冷エンジン開発を抱え込む事になったのがF-1番長 川本さんでした。当然、水冷の担当でもあり、両者を同時に改良するなんて事実上不可能ですから、この段階でホンダのエンジンの進化は止まった、と思っていいでしょう。
結局、彼はほとんど空冷エンジンに掛かりきりになる事になり、本田宗一郎総司令官の意向により9月7日のイタリアGPで再度空冷F-1を走らせるように求められます。このため8月に二号車を完成させ、17日にはサーティスを日本に呼んでテストを行います。この段階ではさすがにオイルクーラーは装着が認められて最初からつけて走ったのですが、それでもモノにならん、という評価に終わります。が、本田宗一郎総司令官はまだ諦めませんでした。この辺りは、もう完全に狂ってるという感じで、彼の技術者としての評価を著しく下げざるを得ない部分となっています。
結局、イタリアGPへの参加は中止とならずRA302の二号車と共に川本さんが現地に送り込まれるのですが、この二度目の暴挙に現地の中村監督が激怒、空冷マシン出走への協力を完全に拒否し、このため川本さんは、移動のためのトラックの手配から何から自分で行う羽目になりました。
ちなみに、このイタリアGPでは従来の水冷式RA301がポールポジションを獲得、これがホンダ第一期で最初で最後のポールポジションとなりました。その後、サーティス自らが空冷のRA302を走らせたのですが、RA301に比べて6秒以上遅いという状況でした。よってサーティスはRA301で出走する事を選び、RA302は本選では走らずに終わります。
ついでながら、このイタリアGPではイギリス人ドライバーのデーヴィッド・ホブス(David
Hobbs)がホンダのRA301のスペアカーを使って出走、リタイアで終わってるのですが、その参加の経緯はよく判りません。彼に空冷のRA302を与える、という選択肢は検討された形跡がありませんから、最初からRA301での出走と決まっていたようです。
ホンダは最終戦メキシコGPで有償でマシンを貸し出しているので、この時もそうだった可能性が高いのですが確証は無し(ホブスはル・マン24時間の常連ドライバーだったがF-1はこれが初参戦)。ちなみにホンダが最終戦、1968年のメキシコGPで、5位2ポイント獲得となっているのはその有償でホンダからRA301を借りて参戦したスウェーデン人ドライバー、ボニエ(Jo
Bonnier)によるもので、サーティスはリタイアに終わってます。
こうして空冷F-1に引っ掻き回される形で、ホンダの第一期F-1最後の年、1968年はパッとしないまま終わってしまう事になりました。撤退にあたり中村監督は“一時休止”という言葉を使って最後の抵抗を試みましたが、その後ホンダが再びF-1に帰ってくるまで16年、久米&川本のお二人がホンダの中枢に昇り詰めるまで時間を必要としてしまいます。でもって、その第二期のホンダは後に6年連続のコンストラクターチャンピオンのエンジンと言う記録を打ち立てる事になるのです(DFVエンジン全盛のフォード・コスワースの七連覇に次ぐ歴代二位。ただし六連覇はホンダ以外にもルノー、フェラーリ、メルセデスが達成してる。連覇でなければフェラーリの16回チャンプが最多でルノー12回、フォードコスワース10回、メルセデス8回に次ぐ5位)。
ちなみに1968年11月3日のメキシコを持って確かにホンダのF1活動は終わったのですが、実は最後の最後にちょっと変な事をやってます。中村さんはメキシコGPから北上してアメリカに回り、同月の20日、21日にあのインディアナポリス スピードウェイ、世界三大レースの一つ、インディ500マイル レースのコースにRA301を持ち込んで走行テストをやったのです(ちなみに残り二つはF1 モナコGP、,ル・マン24時間耐久レース)。これはヨーロッパのF-1に対してアメリカで人気だったインディーカーレースのコースにホンダのF-1を持ち込んでテストした、という事です。
余談ですがホンダの第一期F-1レースは一度しか観に行かなかった本田宗一郎総司令官ですが、なぜかインディ500マイルは同時期に二回も視察しており、もしかしてやりたかったのか、という気もします。ここら辺りは明確な資料がないので断言はできませぬが。ただしこの最後のインディアナポリスでのテスト走行は中村監督の独断によるもので、本田宗一郎総司令官は関わって無かったとされます。
この時は1500㏄時代のセカンドドライバーだったバックナムが呼び出されてテストを担当しました。当初はサーティスがやる予定だったのですが、彼はインディーカーのライセンスを持って無いためコースを走れなかったのです。ちなみにバックナムはF-1を去ったあと地元アメリカのインディカーに参戦、この時までに一度優勝を経験してました。
ついでに、この年のインディ500ではまだウィング付きのマシンは走って無かったので、どうもこれがあのコースを最初に走ったウィング付きのフォーミュラレーサー車と言う事になってるようです。
参考までにタイムは最速で56秒8。ウィングを外して走ったところ58秒2まで落ちたのでオーバルコース(陸上のトラックのような楕円サーキット)でもウィングは有効という事になります。ついでにインディ500マイルは最速ラップタイムでは無く、最高速度が主に記録されるのですが、この年の最高速は171.6マイル/h(276.1㎞/h)、対してRA301は158.4マイル/h(254/9km/h)でしたから、まあそんな所が、という記録になってます。もっともコースにあったセッティング状態とはいえず、当時のインディーカー用の高い熱量が出るメタノール燃料を使ってない、という事を考えるとそこそこの数字にはなっていた、とも言えますが。