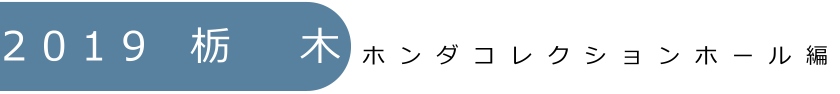
さて、どんどん脱線してゆくホンダコレクションホール旅行記ですが、こうなったら行く道行くぜ、という感じで今回はドライサンプ(Dry
sump)、オイルの乾式循環エンジンの話をして置きましょう。ちなみにサンプはオイル溜めの事。この位日本語にすりゃいいのに、と思うんですが、もはやコレが一般的な呼称になってしまってるので、この記事でもカタカナ英語を踏襲します。この辺り、あまり賢くは無いなあ、と常に思うのですが。
前回見たようにホンダはF-2の参入初年度にエンジン内部が熱でボロボロになるという衝撃的な状況に見舞われます。さらにクランクシャフトまで破断し、普通なら考えられないような壊れ方を見せたのです(クランクシャフトの破断については久米さんは原因は不明としてますが状況からして熱と振動の問題と考えていいと思われる)。
となると、エンジンがキチンと冷えてない、という事になります。エンジンを冷やすのは冷却水とエンジンオイルの二つがあるのですが、冷却水は通常シリンダーから上、エンジンの上半分を冷やすだけですから、その不足でエンジン内部がほぼ全て破壊される事は通常、考えられません。クランクシャフトまで折れるような状況だと、これはオイルによる冷却が出来てない、おそらくオイルがまともに回ってない、という事になります(通常クランクシャフトの内部は中空でオイルが循環する)。
が、なんぼ四輪エンジンの経験が浅いとはいえ久米さんはすでにS500&S600のエンジンを設計し、それらは実際に問題なく走り回ってました。さらに言えばバイク用のレーシングエンジンでなら世界を制したこともある設計者なわけです。よって、そんな初歩的な設計ミスは本来ありえないはずです。
ところが1000㏄とはいえ四輪用のレースエンジンは、市販用の四輪車とも、バイクのレーサーとも違う問題を抱えていたのでした。すなわち曲がる時や減速時に強いGが掛かると、オイルが暴れてエンジン内をまともに循環しなくなる、という問題です。
1992年にイタリアの自動車雑誌「QUATTRORUOTE」が当時のフェラーリ市販最速車F-40と1992年型のフェラーリF-1の走行テストをやった事がありました。
それによるとF-1車が高速コーナーを曲がる時に掛る横Gは実に4.31G(F-40は1.29G)
、ブレーキング時に前方向に掛るGは最大で3.7G
(F-40は1.17G)とどちらも強烈なGが掛かってました。1G=重力加速度ですから、重力の約4倍の力、体重60㎏の人なら240㎏近い力が横や前方に向けて掛かる事になります。1960年代のレーシングカーはそこまで高速で曲がる、止まるはできなかったので、おそらく半分以下の力しか掛かってませんが、それでも重力と同じか、2倍近い力が水平方向に掛るのです。ちなみにより高速化した2019年現在のF-1ではコーナリングで最大5G、ブレーキングで最大4Gを超えるGが掛かってると見ていいでしょう。
これだけのGを受ける乗り物は宇宙ロケット、戦闘機、アクロバット飛行機と空を飛ぶもの以外ではまずあり得ません(事故時は除く)。
しかもコースを一周するだけで何度もこの高Gを受け続けながら、2時間も運転を続けるのはレーシングカー以外にまずないでしょう(近年のF-2やスーパーフォーミュラは90年代のF-1に近いコーナリング速度を出すので恐らくこの数字に近いGを受けてる)。
最大Gこそ半分くらいですが、それでも2時間近くに渡りこれだけのGを受け続けるF-1ドライバーはある意味戦闘機パイロット並みかそれ以上ににタフなお仕事であり、F-1ドライバーの首が太いのはこのGに耐えるためです。特に頭部はヘルメットをかぶるため首への負担はより厳しいのです。
でもってドライバーの肉体と同時に、車体にも同じGが掛かっています。つまり水平方向に重力の数倍の力が加わっている、という状態で、当然、エンジンも同じです。人間の首よりはるかに頑丈な金属製のエンジンなら4Gくらい平気と思ってしまいますし、実際、そうだったのですが(近年のF-1エンジンはより強力なGが掛かるので一定のG対策は必要なはずだが)、エンジンの中には水平方向の力、横Gが掛かると悪影響を受けるものがありました。
それが潤滑と冷却のためエンジン内を循環するオイルです。ガソリンの流れも一定の影響を受けますが、少量であり強力なポンプで押し出して噴霧し、気体にしてしまえばそこまでの影響は受けません(ちなみにこれもキャブレターが不利な理由の一つ)。
対してオイルは最初から最後まで液体のままエンジン内を巡回してその潤滑、そして冷却を行いますが、ドンブリに入れたサラダオイルを左右に揺らせば判るように、液体は容易に水平方向からの力の影響を受けて暴れるのです。そして通常のエンジンではこの対策がありません。そんな力が加わる前提になってませんからね。
それがどんな問題を引き起こすのか。とりあえず、ここで通常のエンジンにおけるオイルの循環方式、湿式循環(ウェット サンプ/Wet
sump)エンジンの構造を見て置きましょう。図では単気筒構造のエンジンを横から見てると思ってください。

大まかに言ってしまうと、オイルは重力(すなわち1Gで生じる力)で上から下に落ち、一番下にあるオイル受け皿(オイルパン Oil
Pan)に溜まります。ここにオイル溜まりを造るので湿式(Wet
sump)循環なわけです。そしてそのオイルパンに溜まったオイルを循環ポンプでくみ上げ、フィルターで不純物を濾過して最後エンジンに送り込みます。ポンプはあくまでエンジンの上部(頂上部のカムシャフト周辺とその下のピストン&クランクシャフト周辺の二系統)までオイルを送り出すだけで、後の循環は重力による自由落下に任せる事になります。
ここで問題になるのは一番下のオイル溜め、オイルパンに溜まったオイルです。これは洗面器にオイルを貯めてるようなものですから、先に見た水平方向の強烈なGが加わると暴れまくります。通常、クランクケースの底に蓋があって溢れ出ないようにはなってますが高速コーナーやブレーキングで4G、重力の4倍もの力が掛かったら当然クランクケース内にまで溢れて暴れまくります。
するとオイルを汲み出すポンプの吸入口がオイルの外、空気中に飛び出してしまい、空気を吸い込む事態が生じます。当然、オイルの代わりに空気が循環系統に入り込んだら全く潤滑も冷却もできませんから、これが繰り返されるとエンジンは熱で焼き付き、破損する事になるのです。これが初年度のホンダF-2エンジンに起きていたトラブルでした。
一時的な対策としてはオイルパンの中に複数の仕切り板を入れて暴れるのを抑える方法があるのですが、完全には抑えられず、その効果は限度がありました。
ちなみに、この欠点を最初に指摘したのもまたブラバムなのです。ホント、只者じゃないんですよね。久米さんが後々までブラバムに対して感謝してましたが、それももっともだと思われる貢献をしています、この人。ちなみにホンダはF-1でも当然全く同じ問題を抱えており、先に見た1965年のシーズン中に行った大幅改良の中で、オイルパンへの仕切り板を入れる、という対策を行っています。これはブラバムからの指摘を久米さん経由で知った本田宗一郎総司令の判断だったとされます。
でもって、欠点はそれだけでは終わりません。
オイルの潤滑も単純に1Gの重力だけに頼っているため、横からのそれ以上の力が加わると、壁に押し付けられ流れが悪くなります(粘性のある流体なので完全には止まらないが)。よって大きな水平方向の力が加わわりまくるレース用エンジンには無理があるのです。ではどうするか、という事で出て来たのが乾式(Dry
sump)循環エンジンとなります。図にするとこんな感じです。

両者は当然、いろいろ異なるのですが、最大の違いは強力なオイル回収ポンプを使ってエンジンの底にオイル溜まりを造らない点です。これによってオイルが暴れるのを抑えるのと同時にポンプによる回収漏れが起きるのを防ぎます。
まず上から落ちて来たオイルはすぐさま多段回収ポンプ(カタカナ英語スキーの皆さんが言う所のスカベンジポンプ/Scavenge
pump)によって吸引され、オイルタンクに貯めこまれます。これは汲み上げるなんていう生易しいものではなく、多段ポンプを使って強烈な掃除機のような吸引力を発生させて吸い込み、オイルパンの中にオイル溜まりが出来て暴れたり、オイルの回収漏れが起きる余地が無い状況にしてるのです。
この強力な吸引力を得るため、多段式、最低でも2段(stage)、最大だと5段近くまでの強力な多段ポンプを採用するのが普通です(軸流式ジェットエンジンのタービンのように縦並びに複数の回転式ポンプを組み込むものが多い)。
その吸引力によってピストンリングによって密閉されたエンジン下部の空間内は外気に対して負圧(吸い込む力)を与えられます。よって上部からエンジンに送り込まれたオイルは重力だけではなく、この吸引力によって強引にエンジン下部にまで流入する事になり、その循環を安定させているのです。
当然、この構造だと回収ポンプはオイルだけで無く大量の空気を吸い込むのでこのままでは空気が入り込んでかえって危険です。よって途中に空気を取り除くオイル分離器(Separater)が入り、ここで空気を抜いた後、オイルは全てオイルタンクに送り込まれます。そしてオイルタンクも単純な空洞ではなく、いくつもの仕切り板が中に入っており、オイルが暴れるのを防ぎます。
ただしオイルタンクから後は湿式とそう変わらず、送出ポンプ(プレッシャー ポンプ/Pressure
pump)から押し出されてオイルフィルターを通過、エンジン上部にまでオイルは送り込まれてエンジンに入ります。後は先に見た回収ポンプの負圧でエンジン内をオイルは循環する事になるわけです。このため送出ポンプは回収ポンプに比べると非力で、通常単段式の単純なものが使われます。
これらによってオイルが暴れて空気が流入、その循環が途切れるのを防ぎ、さらには途切れずエンジン下まで循環するようにしているわけです。
でもって乾式循環、ドライサンプの利点はさらにあります。
まずオイルタンクを別に設けるので、これを大きくすればオイルの量を大幅に増やせるのです。同じ熱を吸収するならより大量のオイルがあった方が有利ですから、これは大量の熱を発するレース用エンジンでは重要です。さらにオイルクーラーを組み込めば、その効果はより大きくなります。
実際、後にホンダは地獄の空冷F-1エンジンで大量のオイルをオイルクーラーで冷やす事で対策とし(失敗に終わるが)、既に見た地獄の空冷エンジン市販車、H1300
でも同じことをやってます。ちなみにホンダではH1300というスポーツ車でも何でもない車で乾式循環、ドライサンプエンジンを採用した後、長年、これを市販車では採用して無かったのですが、2016年に復活した二代目NSXでほぼ50年ぶりにドライサンプを使ってます。それでもこの車、ちょっと遅いんですけどね…
さらにドライサンプではエンジン下部のオイルパンが無いので場合によっては10㎝近く全高を抑えられます。これは重心を低くしたいレース用エンジンでは重要な点で、これによってブラバムのデザイナー、トーラナックから指摘されていた重心が高い、という問題を解決したのです。
ポルシェ911の空冷エンジンがドライサンプを採用してるのは冷却対策と、この重心の低下の両方の効果を狙ったものです。

最終的に熱問題が解決できなくなり液冷になってしまう911シリーズですが、空冷時代はドライサンプ化でそれに対処していました。今でも根強いファンがいる空冷ポルシェは市販車でドライサンプを積んだ代表的な車でしょう。
もう一つ、エンジンの下部、ピストンから下を負圧にする事でエンジンのトルクと馬力が上がる、という効果も生じます。
その理屈は単純です。シリンダー内はピストンヘッド横に巻き付けられたピストンリングで密閉されるため、これを挟んで上下の密閉空間に分かれます。圧縮、燃焼を行うのはピストンヘッドから上の空間ですが、ピストンは上下する以上、実はエンジン下部でも圧縮が生じるのです。が、下部構造での圧縮は単に抵抗として働くのみでシリンダー上部の爆発燃焼で生じる圧力、すなわちトルクの発生に対してはマイナスでしかありません。
ところが乾式循環、ドライサンプではエンジン下部の空間の空気を回収ポンプで強制的に吸いだして負圧を発生させており、通常のエンジンよりピストンが下降する時の圧縮抵抗を抑える事ができるのです。当然、回収ポンプが強力なほど、その効果は上がります(厳密にはピストンを押し下げる力、エンジンのトルクはピストンヘッドを挟んだ上下の圧力差で決まるから下側の圧が低い方が有利、という事)。
実際、You
tubeで公開されてる実験によると、全く同じ構造のエンジンで乾式と湿式(5段式回収ポンプ)の両方を比較したところ、3000回転から6000回転の時の平均トルクで約6%、馬力(hp)で約30%もの向上が見られたとされます。さすがに馬力で30%はちょっと怪しい気がしますが、とりあえずトルクが上がり、さらに回転数も上がって馬力も上がる、というのは間違いないようです。
ちなみに全てのポンプはクランクシャフトから動力を得て回ってますから、多段式のポンプはより多くの出力を食いつぶすのですが、それを十分に補える出力上昇が得られる、という事でもあります。
すなわわち、ドライサンプ化によって、エンジンの熱問題、出力の上昇、そして重心の高さを一気に解決してしまった事になります。これはホンダのエンジン開発部隊にとっても驚きだったようで、ほぼ同時に開発されたF-1用の3000㏄エンジンでも乾式循環、ドライサンプ方式が採用されました(こちらは入交さんの設計)。
欠点としては部品数の増加と複雑な構造からコストの上昇、そして重量の上昇がありますが、金より速度のレーシングカーでなら問題なく耐えられるコスト上昇で、重量増もそれを補う出力増が見込めるので大きな問題にはなりません。もっともコストが重要な市販車ではよほどの理由がないと採用されませんが。というか、公道走る市販車に2G以上掛かる事は無いので、よほどの高出力が求められ、重心を低くしたいという高級スポーツカーで無いと積んでもあまり意味がありませぬ。