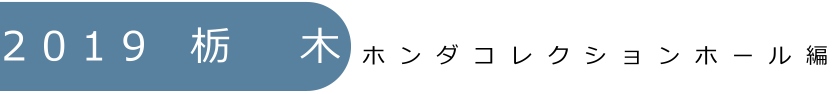
儂儞僟偼戞堦婜擇椫悽奅俧俹偐傜偺揚戅屻丄夛幮傪忋偘偰巐椫儊乕僇乕傊偺扙旂傪寁傝傑偟偨丅
偙偺偨傔媄弍尋媶強偺擇椫晹栧偵偍偗傞恖堳偼戝暆偵尭傝丄1970擭戙偵擖傞偲嵟惙婜偺1/3偲側傝丄偝傜偵1973擭偵偼榓岝偺尋媶強杮幮偐傜暘棧偝傟傞傛偆側宍偱擇椫愱栧偺挬夃尋媶強乮HGA乯偑愝棫偝傟傑偡丅
偙偺偨傔尦慶僫僫僴儞丄俠俛750FOUR偑1969擭偵戝僸僢僩偟偨傕偺偺丄埲屻偺儂儞僟偺擇椫偼偳偆傕僷僢偲偟側偄丄廬棃偺媄弍帒嶻偺怘偄偮傇偟丄偲偄偆傛偆側忬嫷偑挿偔懕偔偺偱偡丅偙偺娫偵巐椫晹栧偱偼僔價僢僋丄偦偟偰傾僐乕僪偺戝僸僢僩傪旘偽偟偰傑偡丅
偙偙偵僇僣傪擖傟偹偽偲摦偄偨偺偑丄俠倁俠俠僄儞僕儞偺姰惉屻丄挬夃尋媶強偵堏傝擇椫偺媄弍奐敪晹栧偺愑擟幰偲側偭偰偄偨擖岎徍堦榊偝傫偱偟偨丅摉帪丄傑偩30戙敿偽偩偭偨擖岎偝傫偼摨婜偺弌悽摢偱偁傝丄挬夃偵堏偭偨捈屻偺1974擭偵偼媄弍尋媶強偺庢掲栶偵廇擟偟偰偄傑偟偨丅儂儞僟偺擇椫晹栧偺暅妶偑斵偵戸偝傟偨丄偲巚偭偰偄偄偱偟傚偆丅
屻偵僶僀僋巗応偵偍偗傞憇愨側斕攧嫞憟丄儎儅僴偐傜儂儞僟傊偺愰愴晍崘偱巒傑偭偨1970擭戙枛偐傜1980擭戙慜敿偺HY愴憟偱傕擖岎偝傫偑恮摢巜婗傪幏傝丄帠幚忋丄儂儞僟偺彑棙偵廔傢傜偣偰傑偡偐傜乮偨偩偟壨搰幮挿偺慡柺揑側僶僢僋傾僢僾偑偁偭偨乯丄桪廏側恖偱偼偁偭偨偺偱偡乮偦偺戙傢傝夁搙側妱堷斕攧側偳偵傛傝儂儞僟傕柍彎偱偼偡傑側偐偭偨偗偳傕乯丅
偪側傒偵偙偺弌悽嫞憟偵偍偄偰擖岎偝傫偵懕偄偰偄偨偺偑1963擭摨婜擖幮偺俥-1斣挿丄巐椫晹栧偺媄弍愑擟幰偲側偭偨愳杮偝傫偱乮2擭抶傟偰1976擭偵媄弍尋媶強偺庢掲栶廇擟乯丄屻偵椉幰偼媣暷幮挿偺屻宲幰丄巐戙栚儂儞僟幮挿偺嵗傪弰偭偰嫞憟偲側傝丄嵟廔揑偵1990擭丄愳杮偝傫偑偦偺嵗傪彑偪庢傝傑偡
偪傚偭偲扙慄偡傞偲丄擖岎偝傫偼愳杮懱惂偺壓偱杮幮偺暃幮挿丄偦偟偰媄弍尋媶強幮挿偵廇擟偡傞偺偱偡偑丄愳杮偝傫偲宱塩曽恓傪弰傝懳棫偟偨偲尵傢傟偰偍傝丄偦偺寢壥丄儂儞僟傪嫀傞帠偵側傝傑偟偨丅
偦偺屻丄俧俵偵堏傠偆偲偟偨偺偱偡偑丄摉帪偼傾儊儕僇偺儔僀僶儖夛幮偵峴偔偺偼擔杮揑側彜摴摽偵斀偡傞丄偲偝傟偨柺傕偁傝拞巭丄姰慡偵暿嬈奅偩偭偨僎乕儉夛幮偺僙僈偵堏偭偰偦偺宱塩偵僩僪儊傪巋偡帠偵側傝傑偡丅
偝傜偵屻偵擖岎偝傫偼埉僥僢僋偺幮挿偵傕側傞傫偱偡偑丄偙偙偱傕巕夛幮搢嶻偵敽偆戝暆尭帒傪傗偭偰偍傝丄塣偑埆偄偺偐杮恖偺宱塩擻椡偵栤戣偑偁傞偺偐敾傝傑偣傫偑丄偲傝偁偊偢儂儞僟偲偟偰偼愳杮偝傫偱惓夝偩偭偨偺偐傕偟傟傑偣傫丅
偝傜偵扙慄偡傞偲丄椉幰偼摨婜擖幮側傫偱偡偑愳杮偝傫偼戝妛堾懖偺偨傔丄擖岎偝傫偺曽偑3嵨庒偔丄丄偦偺師偺幮挿傕慱偊偨偼偢偱偟偨丅幚嵺丄愳杮偝傫偺愓傪宲偄偩屲戙栚丂媑栰幮挿偼擇恖偲摨婜偺1963擭擖幮偱擖岎偝傫偲摨擭楊偱偟偨偐傜偦偺壜擻惈偼偁偭偨偼偢偱偡丅偍偦傜偔擖岎偝傫傪媄弍尋媶強幮挿偵偟偨偺偼丄偦偆偄偆堄枴傕偁偭偨傛偆側婥偑偡傞傫偱偡偑乧丅偑傑傫偱偒側偐偭偨傫偱偟傚偆偐偹偊乧丅
側偺偱1963擭擖幮慻偼3恖偺幮挿岓曗偑偄偨帠偵側傝丄偦偺撪2恖偼幚嵺偵幮挿偵傑偱忋傝媗傔偨丄偲偄偆杒搇恄対宲彸幰憟偄偺傛偆側悽奅偑揥奐偝傟偰偄偨偺偱偟偨丅
偝偰丄榖傪栠偟傑偟傚偆丅
挬夃尋媶強偱擇椫偺奐敪愑擟幰偩偭偨擖岎偝傫偼丄偦偺媄弍揑側掆懾懪攋偲攧傝忋偘偺夞暅偵偼儗乕僗傊偺暅婣偑堦斣岠壥揑偱偁傞丄偲敾抐偟傑偟偨丅儗乕僗偵彑偮偨傔偺媄弍揑側拁愊偼丄斵傕3000cc
悽戙偺俥-1僄儞僕儞奐敪偵娭傢偭偰傑偟偨偐傜乮師夞埲崀丄屻弎乯丄椙偔抦偭偰傑偟偨丅偦偟偰僶僀僋偼幵埲忋偵儗乕僗偱彑偮偙偲偵傛傞僀儊乕僕岦忋丄偦偟偰攧傝忋偘傊偺峷專偑柧妋偩偭偨偺偱偡丅
岾偄丄榓岝偺巐椫晹栧偺媄弍尋媶強杮晹偱傕儗乕僗暅婣偺婡塣偑崅傑偭偰偄傑偟偨丅
壨搰偝傫偑杮幮幮挿偵側偭偨偁偲丄媄弍尋媶強偺幮挿偵側偭偰偄偨媣暷偝傫偑偦偺婙怳傝栶偲側偭偰偄偨偨傔丄榖偼嬶懱惈傪懷傃偰棃傑偡丅偳偪傜偐偲偄偆偲尰幚庡媊幰偱儗乕僗偵偦傟傎偳擬怱偱偼側偐偭偨壨搰幮挿傕嵟廔揑偵梊嶼偵尷搙傪晅偗丄巗斕幵偺奐敪偵塭嬁傪媦傏偝側偄丄偲偄偆忦審偱偙傟傪嫋壜偡傞偺偱偡丅
偙偺寢壥丄儂儞僟偺擇椫幵晹栧偑巗斕幵CB750FOUR傪儀乕僗偵偟偨懴媣儗乕僗梡儅僔儞丄RCB1000傪奐敪丄1976擭偐傜懴媣儗乕僗偵嶲壛偟偰丄偄偒側傝僠儍儞僺僆儞傪妉偭偰偟傑偭偨帠偼偡偱偵弎傋傑偟偨丅偑丄僛儘偐傜偺奐敪偱偼柍偄偨傔儗乕僗儅僔儞偐傜巗斕幵傊偺媄弍揑側僼傿乕僪僶僢僋偑庛偔丄傗偼傝悽奅俧俹偵嶲愴傪丄偲偄偆帠偵側偭偰偄偭偨傛偆偱偡丅
偙偺偨傔丄奀榁戲偝傫偺乽俥-1丂抧忋偺柌乿偵傛傟偽1977擭10寧31擔偵榓岝偺媄弍尋媶強偱擇椫丄巐椫偺儗乕僗暅婣偵懳偡傞夛媍偑奐偐傟傑偟偨丅偙偺惾偱擇椫晹栧偺媄弍愑擟幰丄擖岎偝傫偺庡摫偱擇椫偺悽奅俧俹偼偁偭偝傝寛掕偝傟丄1979擭偐傜嶲愴偲偄偆慄偱榖偑傑偲傑傝傑偡丅懳偟偰巐椫偺俥-1暅婣偼丄巐椫偺媄弍愑擟幰偱偁傞俥-1斣挿偺愳杮偝傫偑廃埻偺僲儞僉側堄尒偵寖搟丄傊偦傪嬋偘偰戝峳傟偵側傞偺偱偡偑丄偦傟偼傑偨屻偱怗傟傑偡丅
偲傝偁偊偢丄偙傟傪庴偗丄儂儞僟偼1977擭11寧偵乽1979擭偐傜悽奅俧俹500噒僋儔僗傊偺暅婣乿傪愰尵丄拲栚傪廤傔傑偡丅偦偺寁夋偺憤愑擟幰偼擖岎偝傫丄偦偺壓偱奐敪尰応傪摑妵偟偨偺偼屻偵榋戙栚幮挿偲側傞暉堜埿晇偝傫偱偟偨丅
偦偺怴宆儅僔儞偺奐敪偼夛媍偐傜3偐寧屻偺1978擭2寧丄挬夃尋媶強乮HGA乯偵偍偄偰憤惃100恖嬤偄恖悢傪廤傔丄偐側傝偺婯柾偱僗僞乕僩偟傑偡丅偟偐偟丄偙偙偐傜儂儞僟偼悽奅俧俹傊偺暅婣傑偱丄偝傜偵偼暅婣偟偰偐傜傕悢擭娫丄偐偮偰側偄堬偺摴傪曕傓偙偲偵側傞偺偱偡丅
NR僽儘僢僋偲屇偽傟傞帠偵側傞偙偺奐敪僠乕儉偺奐敪愑擟幰乮LPL乯偵巜柤偝傟偨暉堜偝傫偑僄儞僕儞偺曽岦惈傪寛傔偨偺偱偡偑丄4僒僀僋儖僄儞僕儞偑娕斅偺儂儞僟偱偁傞偙偲丄偝傜偵1976擭偛傠傑偱偺悽奅俧俹偱偼傑偩4僒僀僋儖500cc
偱傕彑偰偨帪戙偩偭偨偙偲側偳偐傜丄摉帪庡棳偵側偭偰偄偨2僒僀僋儖丂僄儞僕儞傪嵦梡偟側偄帠偵寛掕偟偰偟傑偄傑偡丅
偙偺寢壥丄4僒僀僋儖偺懭墌僺僗僩儞偲偄偆懠偵椶傪尒側偄堎宍偺僄儞僕儞偺奐敪偑巒傑傝丄偦偟偰偦傟偼嵟屻傑偱枮懌偺備偔宍偵偼側傜側偐偭偨偺偱偡丅

儂儞僟偺12擭傇傝偺俧俹儗乕僒乕丄儂儞僟NR500偺1崋婡丄1979擭戞11愴丄僀僊儕僗俧俹偐傜嶲愴偟偨0倃宆丅偪側傒偵NR偼奐敪僾儘僕僃僋僩柤丄New
Racer丂偺摢暥帤傜偟偄偱偡丅
懭墌僺僗僩儞僄儞僕儞偱桳柤側儅僔儞偱偡偑丄幵懱慜敿晹傕偄傠偄傠曄傢偭偰偄傑偡丅偙偺揰傪墶偐傜偺幨恀偱妋擣偟傑偟傚偆丅

傑偢偼僇僂儕儞僌偑惓柺晽杊晹偲幵懱壓晹偲偱擇暘妱偝傟偨峔憿偵側偭偰偄傞偺偵拲栚丅偝傜偵壓懁偺僇僂儖偺僱僕巭傔偑偄傠偄傠摿庩側偺傕尒偰偔偩偝偄丅
偙傟偼僄價妅僼儗乕儉偲屇偽傟傞丄堦庬偺傾儖儈儌僲僐僢僋峔憿偵傛傞傕偺偱偡丅
僴儞僪儖偐傜屻傠偱幵懱壓懁傪暍偆僇僂儕儞僌偼敔宆偺傾儖儈惢偲側偭偰偄傑偟偨丅偙偺晹暘偺奜斅偼栺1噊偺岤偝傪帩偪幵懱嫮搙傪晧扴丄偝傜偵偙偺拞偵擖傟傞僄儞僕儞偵傕嫮搙傪晧扴偝偣偰堦庬偺儌僲僐僢僋峔憿偲側偭偰偄傞偺偱偡丅偙傟偵傛傝僼儗乕儉傪廬棃傛傝昻庛側丄偡側傢偪寉偄傕偺偵偟偰傕嫮搙傪堐帩偱偒傞傛偆偵偟偰偄傑偡丅偨偩偟摨帪偵僄儞僕儞傪敔宆偺儌僲僐僢僋晹暘偐傜崀傠偝側偄偲惍旛傗挷惍偑弌棃側偄偲偄偆寚揰傕書偊偰偄傑偟偨丅
偦傟偵壛偊偰丄偙偺僼儘儞僪僒僗偼偳偆偄偆峔憿側偺丄偲偐擱椏僞儞僋偺壓偵偁傞偺傑偝偐儔僕僄僞乕丠偲偐媈栤偑師乆偵弌偰棃傑偡丅
僼儘儞僩僒僗偼摉帪偱偼捒偟偄搢棫宆偵偟偨寢壥丄偙偆偄偭偨宍偵側偭偨傛偆偱偡偑丄側偤摏偑擇杮暲峴偟偰抲偐傟偰慜懁偵僗僾儕儞僌偑尒偊偰傞偺偐丄偦傕偦傕壗偱慜懁偩偗幵椫僇僶乕偲堦懱壔偟偰傞偺偐丄枹偩偵偳偆偄偭偨峔憿側傫偩偐巹偼抦傝傑偣傫丅
偦偟偰擱椏僞儞僋壓偺崟偄傕偺偼傑偝偵儔僕僄僞乕偱乮徫乯丄僒僀僪儔僕僄僞乕偲屇偽傟偰傑偟偨丅偙傟偑壗傪慱偭偨傕偺側偺偐巹偼傛偔抦傝傑偣傫丅晛捠偵峫偊傟偽椻媝偵晄棙側偼偢偱偡偑乧
偮乕偐丄偙偺儔僕僄僞乕攝抲丄儔僀僟乕壩彎偟傑偣傫丠傕偟儔僀僟乕偼僗乕僣偱戝忎晇偩偲偟偰傕丄惍旛堳丄婋尟偡偓傑偣傫丠偮偄偱偵偁傑傝摢偺椙偔側偄旜嶈乮壖柤乯偑偙偺僶僀僋傪搻傫偱憱傝弌偟偨傜妋幚偵壩彎偟傑偣傫丠旜嶈乮壖柤乯戝僺儞僠偠傖偁傝傑偣傫丠
偝傜偵尵偊偽丄僇僂儖忋偱悅捈偵愗傝棫偭偨抁偄晽杊僈儔僗傕婥偵側傝傑偡丅偙偙偱婥棳傪忋偵悂偒忋偘傞帠偱儔僀僟乕偵晽偑摉偨傜側偄愝寁偱丄慜柺搳塭柺愊偑彫偝偔側傝嬻婥掞峈偑尭傞丄偲偝傟偰傑偡丅偟偐偟丄偦傟偼偡偝傑偠偄棎婥棳傪敪偟偰偄偨偼偢偱丄帪懍100噏偁偨傝偐傜忋偱偼媡偵憡摉側嬻椡掞峈尮偵側偭偰偄偨偲巚傢傟傑偡丅媡岠壥偩偭偨傫偠傖側偄偐側偁乧丅慜晹搳塭柺愊偩偗偱扨弮偵嬻婥掞峈偼尭傝傑偣傫偐傜丄偪傖傫偲晽摯幚尡偲偐傗偭偰偨傫偱偡偐偹乧
偮偄偱側偑傜丄偙偺NR偼慜柺搳塭柺愊丄惓柺偐傜尒偨戝偒偝偺彫宆壔偵偐側傝婥傪巊偭偰偍傝丄廬棃偺儗乕僔儞僌僞僀儎傪2僀儞僠彫偝偔偟偨16僀儞僠儂僀乕儖傪嵦梡偟偰傑偟偨丅偙偺曈傝傕丄偍偦傜偔晽摯幚尡偲偐偱僉僠儞偲棳懱椡妛揑側棤晅偗丄庢偭偰側偄婥偑偟傑偡偹偊乧丅
偲傝偁偊偢埲忋偺揰偼梻擭偺1980擭宆偺儅僔儞偱偼傎傏慡偰忢幆揑側儌僲偵曄峏偝傟偰偟傑偭偰偄偨偺偱丄傗偼傝偁傑傝岠壥偼柍偐偭偨偺偩偲巚偄傑偡乮椳乯丅偦偟偰丄偦傫側儅僔儞偱偡偐傜丄僨價儏乕偲側偭偨1979擭偼悽奅GP戞11愴僀僊儕僗偐傜屻偺2愴偵偩偗嶲壛乮戞12愴僠僃僐偱偼500噒偺儗乕僗偑柍偐偭偨乯丄弶愴僀僊儕僗偱偼2戜偲傕儕僞僀傾丄嵟屻偺僼儔儞僗GP偼梊慖棊偪偱廔傢傝傑偟偨丅
偝傫偞傫側悽奅俧俹暅婣偩偭偨丄偲尵偊傞偱偟傚偆丅

乬揱愢偺乭4婥摏懭墌僺僗僩儞僄儞僕儞偺庡側峔憿晹丅
墌宍偱偼側偄丄懭墌僺僗僩儞4偮偱V宆4婥摏側傫偱偡偑丄僺僗僩儞壓偺僐儞儘僢僪偼奺2杮丄僾儔僌傕2杮丄偝傜偵僶儖僽偼奺8偮偱偡偐傜乮僗儁僢僋忋偼8僶儖僽DOHC偲偄偆慜戙枹暦偺僄儞僕儞偲側偭偰傞乯丄婎杮峔憿偼8婥摏偺懡婥摏僄儞僕儞偱偁傝丄偦偺婥摏傪2杮偢偮崌懱偝偣偰懭墌偵偟丄4婥摏偵傑偲傔偰偟傑偭偨傕偺丄偲偄偆偺偑尒偰庢傟傞偱偟傚偆偐丅扨弮偵僴僀僷儚乕僄儞僕儞傪憿傞偩偗側傜丄傎傏柍堄枴側峔憿側偺偱偵丄傢偞傢偞儂儞僟偑偙傫側曽幃傪慖傫偩偺偵偼丄摉慠丄棟桼偑偁傝傑偟偨丅
傑偢丄僄儞僕儞偺暔棟揑側椡丄夞揮椡偱偁傞僩儖僋乮俶乯傪媮傔傞幃傪尒偰抲偒傑偟傚偆丅
僄儞僕儞僩儖僋乮俶乯亖乮惓枴暯嬒桳岠埑椡乯亊乮攔婥検乯亊乮敋敪夞悢乯乛乮2兾乯
嵟弶偺惓枴暯嬒桳岠埑椡丄僺僗僩儞傪墴偟壓偘傞埑椡偼丄偳傟偩偗崿崌婥傪庢傝崬傫偱敋敪偝偣傞偐偱傎傏寛傑傝丄僶儖僽傪懡偔偟偰堦婥偵戝検偺崿崌婥偲庢傝崬傓丄傑偨偼埑弅斾傪忋偘傞偙偲側偳偱堦掕偺忋徃岠壥偑摼傜傟傑偡丅師偺攔婥検偼500cc偲寛傑偭偰傑偡偐傜丄偙傟偼摨僋儔僗偺僄儞僕儞側傜慡偰嫟捠偱偁傝憂堄岺晇偺梋抧偼偁傝傑偣傫丅
嵟戝偺栤戣偼敋敪夞悢乮椡傪惗偠偨夞悢乯偱丄摨偠峴掱悢撪偵攞偺夞悢偺敋敪擱從傪峴偆2僒僀僋儖僄儞僕儞偼4僒僀僋儖偺攞偺僩儖僋偑弌傑偡乮幚嵺偼2僒僀僋儖僄儞僕儞偵偼偝傑偞傑側僄僱儖僊乕懝幐偑偁傞偺偱偦偺嵎偼傕偆彮偟彫偝偄偑乯丅偙偺扨弮側暔棟朄懃偵傛傝丄4僒僀僋儖僄儞僕儞偼埑搢揑偵晄棙側偺偱偡丅媡偵攞偺擱椏傪擱傗偡2僒僀僋儖偼擱旓偱晄棙側偺偱偡偑丄抁嫍棧僗僾儕儞僩儗乕僗偺悽奅俧俹偱偼偙偺揰偼傎偲傫偳栤戣偵側傝傑偣傫偱偟偨丅偮傑傝4僒僀僋儖僄儞僕儞偑堦曽揑偵晄棙偵側傝傑偡丅
偪側傒偵偙偺幃偼杮棃丄椡偱偼側偔巇帠仌僄僱儖僊乕乮倂仌俤乯偺検丄僕儏乕儖乮俰乯傪媮傔傞傕偺偱偡乮扨埵丒師尦偼Nm偱僩儖僋偵摍偟偄丅偨偩偟壛懍搙儀僋僩儖偺岦偒偺娭學偱僩儖僋偼僄僱儖僊乕偵偼側傜側偄乯丅
埑椡扨埵傪懱愊乮攔婥検乯扨埵偱妱傞偺偼丄椡偺偐偐偭偨嫍棧傪媮傔傞偺偵摍偟偄偺偱乮亖N乮僯儏乕僩儞乯亊m乮儊乕僩儖乯乯丄偙偺幃偱偼僺僗僩儞偺忋壓塣摦嫍棧偺棟榑抣傪媮傔偰傞帠偵側傝傑偡丅偦偺屻丄僩儖僋偼僋儔儞僋幉偱墌塣摦偺椡偵曉娨偝傟傑偡偐傜丄僩儖僋偺戝偒偝傪媮傔傞偨傔嵟屻偵2兾偱妱偭偰夞揮幉偺敿宎傪弌偟偰傑偡乮墌廃偼2兾r乯丅
埲忋偐傜丄儗乕僗拞偺懍搙偱懳峈偡傞偩偗偺攏椡傪壱偖偵偼丄僩儖僋偺惓枴暯嬒桳岠埑椡偐丄偦偺屻偺夞揮悢偺偳偪傜偐傪攞丄偁傞偄偼椉幰偺忔嶼偟偨悢傪攞偵偡傞偟偐偁傝傑偣傫乮懍搙傪寛傔傞攏椡偼僩儖僋亊夞揮悢乯丅偦傟埲奜偺悢抣偼摦偐偣側偄偺偱偡偐傜丅
偑丄摨偠攔婥検偱惓枴暯嬒桳岠埑椡傪攞嬤偔傑偱忋偘傞偺偼暔棟揑偵晄壜擻偱偁傝丄傛偭偰夞揮悢偺忋徃偑尰幚揑側懳嶔偲側偭偰偒傑偡丅偙偺応崌丄僩儖僋偑敿暘側傫偱偡偐傜丄摉慠2攞偺夞揮悢偑媮傔傜傟傑偡丅
夞揮悢傪忋偘傞偵偼懡婥摏壔偑嵟傕庤偭庢傝憗偔丄棟憐揑偵偼攞偺8婥摏偑昁梫偲側傝傑偡丅偦傟偱傕懡婥摏壔偼儂儞僟偺摼堄偲偡傞媄弍偱偟偨偐傜丄摉弶偼側傫偲偐側傞丄偲巚傢傟偨傛偆偱偡丅
偲偙傠偑悽奅GP偱偼500噒偺僄儞僕儞偼4婥摏偺傒偱僊傾偼6懍傑偱偲偄偆婛掕偑偁傝丄偙偺偨傔奐敪偼偄偒側傝埫徥偵忔傝忋偘傑偡丅
摉帪偺暯嬒揑側2僒僀僋儖丂500噒GP儅僔儞偺惈擻偼杴偦8噑m嬤偄僩儖僋傪弌偟1枩夞揮傑偱夞偟偰100攏椡埲忋偱偟偨丅偙傟偑4僒僀僋儖偩偲僩儖僋偼敿暘偺4噑m慜屻偑尷奅偱偡偐傜攞偺2枩夞揮傑偱夞偝側偗傟偽攏椡丄偡側傢偪懍搙揑偵偼捛偄偮偗傑偣傫丅
儂儞僟偑1967擭偵搳擖偟偨嵟屻偺4僒僀僋儖4婥摏丂500cc儅僔儞丄RC181偑嵟戝偱傕1枩2000夞揮偩偭偨帠傪峫偊傞偲丄偐側傝偒偮偄悢帤偱偡丅慜夞徯夘偟偨嬃堎偺6婥摏350噒僄儞僕儞丄RC174E偱傕1枩7000夞揮傑偱偱偡偐傜丄傗偼傝懡婥摏壔丄8婥摏壔偼晄壜旔偲偄偆帠側偺偱偡丅偟偐偟僄儞僕儞婯掕偵傛傝丄偦傟偼偱偒傑偣傫丅
偝傜偵2僒僀僋儖僄儞僕儞偼峔憿偑娙扨側偨傔丄摨偠攏椡側傜4僒僀僋儖偵斾傋偰20噑埲忋偼寉偔偱偒偨偲偝傟傑偡丅偙傟偼幵懱廳検偺15亾埲忋傪愯傔傞悢帤偱偁傝丄柍帇偱偒傑偣傫丅
傛偭偰丄偦偺廳検嵎傪曗偆昁梫偑偁傝丄傛傝戝偒側幙検傪摦偐偡埲忋丄傛傝戝偒側乽椡乿傪敪惗偝偣傞昁梫偑偁傝傑偡丅偲偙傠偑4僒僀僋儖僄儞僕儞偱偼弮悎側椡偱偁傞僩儖僋偼敿暘偟偐偁傝傑偣傫丅偦傟傪曗偆偼偢偺僊傾傕6懍屌掕偱偼僊傾斾乮尭懍斾乯偺挷惍丄僥僐偺椡偱偱偙傟傪戝偒偔偡傞偵傕尷搙偑偁傝傑偡丅
傛偭偰偳傫側偵攏椡傪忋偘偰嵟崅懍搙偑偁偑偭偰傕丄弮悎偵椡丄僩儖僋偺戝偒偝偑栤戣偵側傞壛懍偱偼晄棙偱丄摿偵掅懍帪偺壛懍偼尩偟偔側傞偼偢偱偡丅偡側傢偪偳傫側偵嵟崅懍搙傪忋偘偰傕丄偦偙偵払偡傞慜偵捈慄偼廔傢偭偰傞丄偲偄偆忬嫷偵側傝彑晧偵側傝傑偣傫丅偄傢備傞棫偪忋偑傝偱偮偄偰峴偗側偄丄偲偄偆忬懺偱偡丅僊傾斾傪壛懍廳帇偵愝掕偡傞丄偲偄偆庤傕偁傝傑偡偑丄6懍傑偱偟偐巊偊側偄偺偱丄偦偆側傞偲崱搙偼嵟崅懍搙偑棊偪偰偟傑偄丄攏椡傪忋偘偨堄枴偑側偔側傝傑偡丅
偙偙傑偱晄棙側忦審偑暲傇埲忋丄晛捠偵峫偊傟偽2僒僀僋儖偱峴偔傋偒偩偲巚偆偺偱偡偑丄儂儞僟偼偁偊偰堬偺摴傪慖傫偩偺偱偡丅偙傟傪桬婥偲屇傇偐偼屄恖嵎偑偁傞偲偙傠偱偡偑丄昅幰揑偵偼椺偺嬻椻僄儞僕儞偲摨偠丄暔棟朄懃揑偵晄壜擻側帠偵挧傫偩姶偑嫮偔丄側傫偱偦偆偟偪傖偭偨傫偩傠偆丄偲巚偆晹暘偱偼偁傝傑偡丅
偦傕偦傕僺僗僩儞偼戝偒偔廳偔側傞偺偱崅夞揮偵岦偐側偄偼偢偱偡偑丄僔儕儞僟乕偺儃傾乮捈宎乯傕戝偒偔側傞偺偱媧攔婥僶儖僽偺柺愊傪戝偒偔偱偒丄偙傟偱堦婥偵戝検偺崿崌婥傪媧偄崬傫偱擱從偝偣傞帠偱崅夞揮壔傪慱偭偰傑偡丅摉慠丄媧婥乮庢傝崬傔傞崿崌婥乯偑憹偊傟偽惓枴暯嬒桳岠埑椡偑戝偒偔側傝丄僩儖僋傕憹偊傑偡偐傜妋偐偵儊儕僢僩偼戝偒偄偺偱偡丅
偙偺偨傔偵婥摏偁偨傝8僶儖僽偲偄偆僗僑僀媧攔婥婡峔傪嵦梡丄偙傟偵傛偭偰僩儖僋偼4.6噑傑偱忋偑傝丄夞揮悢傕2枩夞揮偺払惉偵偼幐攕偟偨傕偺偺1枩8000嬤偔傑偱忋偘傞偙偲偵惉岟偟傑偡乮嵟廔揑偵偼19500夞揮傑偱払惉偟偨乯丅
偑丄偦傟偱傕悽奅GP偱偼慡偔彑偰傑偣傫偱偟偨丅
棟榑揑側惈擻尷奅埲慜偵丄暋嶨側偙偺婡峔偼僩儔僽儖懕偒偩偭偨偺偱偡丅悽奅GP暅婣偺1979擭偵2愴偩偗弌憱偟偨傕偺偺丄堦搙傕姰憱柍偟丄1980擭偼3愴偩偗弌応偟偰2夞偺姰憱偑惛堦攖丄1981擭偼夵慞偝傟傞偳偙傠偐偝傜偵埆壔偟偰6愴弌応偱姰憱1夞偵廔傢偭偰偄傑偡丅嵟屻偵憱偭偨1982擭偺2偮偺儗乕僗偼傑偲傕側僨乕僞偡傜尒偮偐傝傑偣傫偱偟偨乮懡暘姰憱柍偟乯丅
偙偺寢壥丄儂儞僟偼4僒僀僋儖僄儞僕儞傪掹傔丄1981擭偐傜晛捠偺2僒僀僋儖僄儞僕儞偵傛傞NS500偺奐敪傪奐巒丄1982擭偵偙傟傪搳擖偟偰丄傛偆傗偔擭娫傪捠偟偰傑偲傕偵弌憱偱偒傞傛偆偵側傝丄偦偺屻儊乕僇乕僠儍儞僺僆儞偵婣傝嶇偔帠偵側傝傑偡丅
梋択偱偡偑丄柍拑偲傕巚偊傞偙傟偩偗妚怴揑側帠傪傗偭偨偺偼丄悽奅GP暅婣偵偁偨傝丄NR僽儘僢僋偵偼埲壓偺壽戣偑壽偣傜傟偰偄偨偐傜偐傕偟傟傑偣傫丅
1.丂儗乕僗傪捠偠偰妚怴媄弍傪惗傒弌偡偙偲
2.丂彨棃偺妀偲側傞恖嵽傪堢偰傞偙偲
3.丂3擭埲撪偵悽奅僠儍儞僺僆儞偵側傞偙偲
偙偺栚昗傪宖偘側偑傜丄庒偄僗僞僢僼偑拞怱偲側偭偰偺姰慡側怴婯奐敪偩偭偨偨傔丄傗偼傝柍棟偑弌偨偺偩傠偆側偁丄偲巚偄傑偡丅幚嵺丄偦偺奐敪偼柪憱傪廳偹丄1979擭偺悽奅俧俹暅婣傪愰尵偟側偑傜丄NR500偑傑偲傕側帋尡憱峴偵惉岟偟偨偺偼偦偺1979擭偺5寧偱偟偨丅偙偺寢壥丄偡偱偵尒偨傛偆偵偙偺擭偺悽奅俧俹偼傢偢偐2愴偩偗偺嶲愴偱丄偦偟偰姰憱傕偱偒偢偵廔傢偭偨傢偗偱偡丅
偪側傒偵1979擭偺僔乕僘儞廔椆屻丄僀僊儕僗偺僪僯儞僩儞僷乕僋偱僥僗僩憱峴傪偟偨偲偙傠丄僐乕僗儗僐乕僪偐傜1廃偁偨傝2昩抶傟偺僞僀儉偟偐弌側偄偲偄偆徴寕偺帠幚偑敾柧偟傑偟偨丅彑晧偵側傜側偄儗儀儖偱偁傝丄娭學幰偼棊抇偟偨偲巚傢傟傑偡丅