
こちらはイギリス謹製初等練習機、デ・ハビラント社のDH.82Aタイガーモス。
いわゆるサンダーバード6号です(笑)。
こちらもまあ、世界中でお馴染みではありますが、
コンディションは非常にいい機体です。
ただし、この機体は解説板そのものがなく、A型ではない可能性もあり。
10年前の写真を見ても、単にタイガーモスとしか看板に書いてませんし…。
とりあえず自国の機体にはウルサイ、イギリスの人間がA型、
と断言してるのを見たので、その意見を採用しておきます(手抜き)。
第二次大戦前、1931年初飛行の複葉練習機ですが、
タイでは1951年ごろ、すなわち朝鮮戦争の時期に導入してます。
なんでまた、という感じですが詳細は不明。
イギリス空軍での完全退役が1952年なので、
その前後の払い下げ機を安く買ったのかなあ。
34機ほど導入したようで、ある程度の運用はしてたみたいですが、
さすがに10年使って1961年には全て退役となってます。
つーか、1960年前後の段階での機体の入れ替わりが多いな、タイ空軍。
ベトナム前夜、という事で援助もらいまくったのかしらむ。

なんだか近所のオジサンが1週間で造ってしまった趣味の機体にも見えるのが
タイガーモスの偉大なところ…なのか(笑)?
機体横に開いてるカマボコ型の穴は足掛けなんですが、
普通は後ろ、主翼の上から乗り込むはずなので、なんだこれ(笑)。
タイガーモスの燃料タンクはコクピットの上、上翼の天井部なので、
ひょっとして給油作業用?
ラジアル(円形)エンジンではないので、大きな開口部はないですが、
同社の空冷エンジン、ジプシーメジャーを積んでいます。
余談ですが欧米の場合、航空機メーカーが
エンジンまで造ってしまうのは少数派で、
特に1000馬力エンジン時代以降で一定の成功を収めたのは
このデ・ハビランドとドイツのユンカースくらいでしょう。
イギリスだとブリストルもそうですが、ここはエンジンも航空機も
正直パッとしないです(笑)。
そもそも1000馬力を超えるような航空エンジンの製造は、
片手間にできるような仕事ではないのでしょう。
アメリカではカーチス・ライト社がやってましたが、
エンジン部門(Wright Aeronautical Corporation)と
航空機部門(Curtiss-Wright Airplane)は実質的に別会社でしたし、
1000馬力時代以降の航空機はやはりパッとしませんしね…。
日本の事情?いや、…よく知りませんね、私は…ハハハ…。
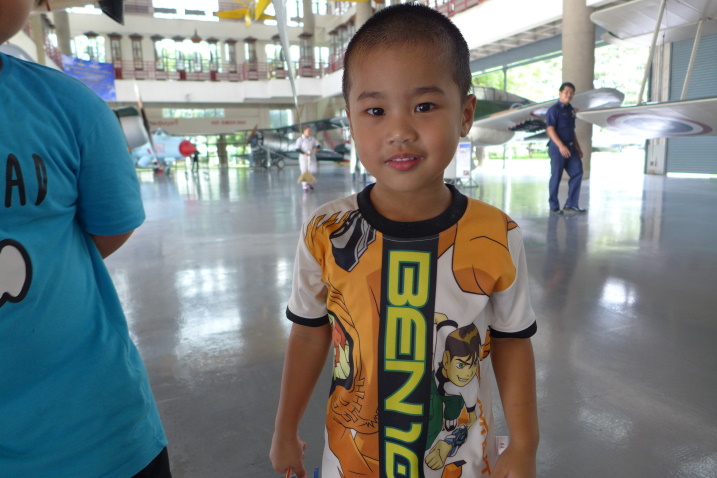
でもって、ここでまたもやちびっ子コンビに遭遇。
イガクリ君が一生懸命話しかけてくれるのだが、スマヌ、
おっちゃんはタイ語はわからんのだ…。
ちなみによく見ると、そのTシャツ、ベン10(ベンテンと読む)じゃないの。
名前の通り、日本のアニメや特撮の強烈な影響を受けた
アメリカのアニメ(カートゥンに分類されてるが)ですね。
(一人で10種類の仮面ライダーに変身できるようなアニメと思えばいい)
タイでも放映されてるのか、それともオーストラリア土産なのか。
でもって、ここでも彼らと宇宙における
人類の存在意義と神の愛の問題について話し合った結果、
またも時間がどんどん経過していしまい、どう考えても
4時の閉館までに全部見れないよな、と悟る。

…とりあえず、見学を続けましょうか。
再びカーチスのホークシリーズですが、
前回見たホークIIIの後継機として輸出されたカーチス ホーク75Nです。
ただしこちらは陸軍機ですが。
まあ、見ればわかりますが、
P-36ホークを固定脚にしてしまった廉価版ですね。
さらに主翼下にはマドセンの23mmというこれまた珍しい
機関砲のガンパックが搭載されてます。
脚とガンパック以外は基本的にP-36のままのはずなので、
この頭に液冷エンジンのアリソンのV-1710をつければ、
固定脚のP-40 ウォーホークが……できるのか?
タイは1939年に25機を導入、後に日本から手に入れた隼と並んで、
第二次大戦中のタイ空軍主力戦闘機でした。
なので連合軍の爆撃機の迎撃にも飛んでおり、
B-29やB-24を迎え撃ったアメリカ機、という妙な存在でもありました。
さすがに23mmあれば相当な破壊力だと思うのですが、
戦果があったのかはわかりませぬ。
ちなみに中国軍でも同じ固定脚のホーク75を採用してましたが、
こちらはライセンス生産で中国で組み立てたため
75Mという型番になっております。
(0から造ったのではなく、部品を持ち込んでの組み立てだと思うが…)

後ろから見るとこんな感じ。
1935年初飛行ですから、Me109と同世代ですが、
あっちが終戦まで進化を続けて主力戦闘機を勤めたのに対し、
こちらはP-40に発展して終わりでした。
まあMe109の場合、最後の方はほとんど別の機体になってしまってますが…。
展示はなぜか胴体後部の機体持ち上げ穴に棒を通して支柱で支え、
尾部を上に持ち上げた状態になってます。
これ、通常はエンジンの位置を低くして整備する時や、
地上で標的に向けて行なう機関銃の試射と
火線の調整時に使うものなんですが、演出の一種ですかね。
ちなみにP-36&ホーク75もまともな機体は世界で3機しかないので、
これも貴重といえば貴重。
特に脚が畳めない廉価版で現存するのは、この機体だけです。
ちなみに残りはデイトンのアメリカ空軍博物館と、
イギリスのダックスフォードにあり、両者ともかつて旅行記で紹介してます。
なので、夕撃旅団は現存P-36完全制覇となるわけです。
…何がスゴイのか、自分でもわかりませんが(笑)。
ついでにこの機体横のハヌマーンのイラスト、
先のホークやコルセア、さらにはF8Fにもありましたが、
ホントに現役時代から描かれていたのかはわかりません。
少なくとも私はそういった写真を見た事がないのです。
どうでもいいといえば、その通りなのですが、ちょっと脱線します。
タイには戦後、軍属に近い変な漫画家が居て、
この人がアメリカの資金援助を得て、なぜか日本で設立されたばかりの
東映動画に仕事を持ち込んだ事があります。
(発注者はバンコクのアメリカ大使館だが、おそらく金はCIAが出してる)
1957年に「ハヌマンの新しい冒険」というタイトルで完成したこのアニメ、
私は未見なのですが、日本を代表するアニメーター、
大塚康生さんの著作「作画汗まみれ」の新版の方に、
そのタイの漫画家が描いたハヌマンのイラストが出てるのです。
で、これがこの博物館の機体に描かれたハヌマンにそっくりで、
CIAをバックに持っていた(映画は反共産主義的な教育映画らしい)
その漫画家が展示にあたって勝手に描いちゃったんじゃないか、
という可能性も若干はある気がしてるんですよねえ…。
まあ、あくまで推測の域を出ませんが。
NEXT