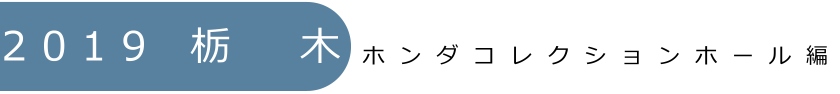
ここからは1986年の車、ウィリアムズ・ホンダFW11を少し詳しく見て行きましょう。久しぶりの展示車解説ですな。
前年のFW10で初めてカーボンファイバーモノコック シャシーを採用したウィリアムズですが、その正統進化とも言えるのがこのFW11でした。前年から始まった青、白、黄色のカラーリングはこの年も引き続き採用され、これは後に1990年代後半まで続き、10年以上に渡って一目でウィリアムズのマシンと判る特徴となります。ちなみに後にホンダが撤退した後もスポンサーを続けたキャノンのロゴが登場したのも、前年1985年からでした。
この年のエンジンはさらなる小口径(ロングストローク)化が進んだRA166Eでした。前年のRA165Eの82(口径)×47.3(全長)mmから79(口径)×50.8(全長)㎜に変更、さらに全幅を10㎝
縮めてよりコンパクトにまとめ、その仕事率は900馬力以上、耐久性を無視できた一発勝負の予選でなら1200馬力以上を叩き出したとされます。しかもシーズン後半にはさらに馬力が向上、レース本番でほぼ1000馬力、予選では1500馬力出たと言われてますから、まさにモンスターエンジンです。
ちなみにマンセルは2019年にFIAの機関誌「Auto
magazine」のインタビュー記事で、ホンダのターボエンジン、RA166Eは予選では1500馬力だった、と証言してますからホントに出たと見ていいようです。一説には予選だとBMWターボはさらに馬力が出ていた、という話もありますから、ほとんど狂気の世界で、おそらくF-1史上最強のエンジンの戦いだったのがこの年なのです。マンセルによると「コーナーに入るたび、当時のマシンはドライバーを殺そうとした」そうな。そこでホンダは勝った、という事になります。
さすがにこれは行き過ぎ、という面がありましたから、これを抑制するため1986年は搭載燃料が前年の220リットルから195リットルに減らされました。ただしこれは低燃費と高馬力を両立させていたホンダエンジンには有利に働き、この年は16戦中9勝とほぼ圧勝に終わります。コンストラクターズ2位に終わったマクラーレンはプロストによる4勝だけでしたから、倍以上の勝ち星を挙げた事になり、圧勝と言っていいでしょう。
このホンダの圧勝ぶりから翌1987年から厳しい燃費に加えてターボ過給圧にも制限が掛かることになり、この1986年からその話し合いがチームと主催者側の間で行われ始めます。ここでひと悶着があるんですけども、その点は次回に。

ややモサっとした印象があった従来のウィリアムズの車に比べると、だいぶ洗練された印象があるのがこのFW11でした。
ようやく80年代後半のターボ車らしい形になった、とも言えます。ただし、それ以外の点は質実剛健、石橋を他人に叩かせてから渡るウィリアムズらしい、特に特徴のない車となっています。わずか5年後にアクティブサスやセミ・オートマチックを始めとする最先端技術を一気に導入、数年間にわたってF-1を支配する事になるウィリアムズと同じチームとは思えないほど保守的な車な印象ではあります。
さらに言えば後輪サスペンション問題は完全に解決されたとは言えず、サスペンションは固めにされ、その結果のタイヤ摩耗にはまだ悩まされています。このため他のチームよりも多くのタイヤ交換が必要となって順位を落とす、という事態が何度も発生する事になりました。その最悪の結果がオーストラリアGPにおけるマンセルの後輪バーストで、前回見たようにこれでドラバーズチャンピオンを獲り損ねる結果となりました。とりあえず1986年までのウィリアムズの車体はそれほど優れたものでは無く、彼らはホンダのエンジンで勝っていた、と考えていいでしょう。
ただし、一定の進化をしていたのも事実でした。前回見たようにホンダは1984年のFW09を購入してエンジンテストを日本で行っており、その運転を担当していたのが後に日本人初のF-1ドライバーとなる中嶋悟さんです。そして1986年12月のシーズン終了後、このFW11を日本に持ち込んで、ピケがエンジンテストを行った際、翌年からF-1デビューが決まっていた彼もこの車を運転する機会がありました。中嶋選手はその時の印象として「それまで乗っていた84年モデルに比べるとまるで別の車のように乗りやすかった」と証言していますから、2年間でかなりの進化はしていたのでしょう。
ただし、そんな時代のウィリアムズですから、この車で十分、と思ったら以後は新規開発を停めてしまい、翌1987年はこの改造型FW11Bで戦う事にするのです。それでも87年はコンストラクターズチャンピオンとドライバーズチャンピオンの両者を獲得したのだから十分と言えば十分なのですが、そういった守りの姿勢、勝つためなら何でもやる姿勢に欠ける部分がホンダの桜井さんに嫌われ、1987年をもってウィリアムズとホンダの提携は打ち切られる事になります。

横から見るとこんな感じ。
排気タービンがエンジンの左右に分かれて搭載されるツインターボゆえ、過給機の吸気口はサイドポンツーン上に煙突のように飛び出しいますが、展示車のような形状はシーズン終盤、第15戦メキシコと最終戦オーストラリアだけで採用されたものです。よって実はほどんどのレースではこれが付いてません。さらにこの形状になった後、1986年は一勝もできてないのです(笑)。展示する車としては、正直、どうかなあという感じですが…。さらに言うならタミヤの1/20
FW11 はこれが無い初期型なので、模型の参考にもなりませぬ…。
この煙突型吸気口が無い初期型(といっても全16戦中14戦をこれで戦ってるのだが)では、車体横の
canon の最初の n と o
の文字の下辺りに切り欠きを付け、その穴から真横にタービンへと吸気する形にしてました。空気抵抗も減るし、直線吸気だから効率もいいのですが、それだと走行時の風圧による圧縮効果が得られないので、この形状に変更したのだと思いますが、これなしでも十分な戦果を上げていたのもまた事実です。
この辺りは翌年1987年のFW11Bにもこの形状は引き継がれたため、そのデータ取りのために1986年の終盤二戦はこの形状にした可能性もあります。このため1986年終盤2戦のFW11と1987年のFW11Bを見分けるのはヒヨコの雌雄を判別するくらい面倒なものになっています。少なくとも私は自信がありませぬ。マンセルがチャンピオンを獲り損ねたのでゼッケンも同番号のままですし。
ちなみにこの時代は自然吸気車でもこのFW11のようにドライバーの頭上に空気取り入れ口、インダクションポッドを置かず、後ろは真っ平らにするのが普通でした。吸気はエンジンの吸気管(Air
funnel)上に穴を開けただけ、あるいはエンジン剥き出し、という豪快なものになってます。この辺り、当時は前面投影面積を限りなく小さくした方が有利、という設計思想があったように見えます。が、1989年の全車NA化から、現代のF-1のようなインダクションポッド式になって来ます。ついでに2014年以降のターボ車は真ん中に一個だけ置かれたシングルターボなので、インダクションポッド式で問題ありませぬ。
ついでに、サイドポンツーンの横、canonの文字の前の大きな穴はラジエター&オイルクーラーの空気抜き穴。
その前半分でネジ止めされてる板は開口部の大きさ調整用で、高温になる夏場のサーキット、あるいはエンジンが熱を持つ全開走行が多い高速コースなどではこれを外し、全開にしてラジエターの冷却効果を上げます。
逆に気温が低いとき、または低速でそれほどエンジン温度が上がらない時は展示のようにフタを付けて排気口を小さくし、冷えすぎてエンジンパワーが低下しないようにしてます。展示はおそらく最大の板で、より小さいもの、さらに全部外して全開にする、などいくつかの段階があったはず。
ついでながら、エンジンは冷やさなきゃなんだけど、冷やし過ぎてもいけないというのが常識なんですが、ホンダは独自の理論でターボエンジンはある程度冷やした方がいい、という運用をやっていた説があります。残念ながら事実関係の確認は取れませんでしたが…。
また、ターボエンジンですから過給機で圧縮して高温になった空気を冷やし、より大量に気筒に空気を詰め込むための空気冷却器、インタークーラーも搭載されてます。これはラジエターの後ろにあり、同じ空気取り入れ口内の仕切り板により別流路で空気を導入するんですが、なぜか後部の空気抜き穴がありません。この理由は未だに私は知りませぬ。
ホンダは1986年のシーズン途中からインタークーラーの温度管理をコンピュータ制御にするのですが、空気抜き穴は最初から無いままであり、それとは関係ないはず。インタークーラーもそれなりに高温になるので、普通は空気抜き穴が必要だと思うんですけどね…。

後方から。
ホンダはエンジンの幅も前年から10㎝近く狭めているので、後方のカウルはより絞り込まれて空力的には有利になってます。
ついでながら2010年代以降のF-1はホイルベース(前後輪の中心間距離)が3.5m以上、車体全長は5m以上あります。これはあの巨大な日産GTRと比べても全長で40㎝以上長く、2トントラックがレースやってるような間延びした寸法となっています。対して1980年代のF-1はホイルベースで3m以下、全長でも4.5m以下と60㎝以上は短いので、ずっとコンパクトで精悍な印象があります。タイヤも太いですしね。車体とタイヤサイズはこの時代に戻した方がはるかにカッコよくなると思うんですけども。
といった感じで、今回はここまで。