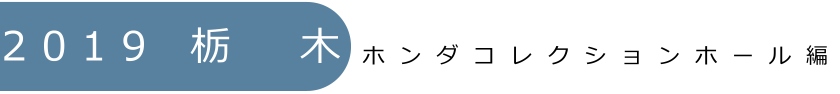
さて、今回からはホンダF-1全盛期の前半、ウィリアムズのチームと組んだウィリアムズ・ホンダ時代を見て行きます。
前回見たように1983年から、自らがオーナーだったスピリット チームのF-2改修シャシーでホンダはF-1に参戦しました。が、早くもその年の最終戦、南アフリカGPからはウィリアムズ チームにエンジンの供給を始めるのです。この時は5位入賞で終わりましたが、翌1984年の開幕戦ブラジルで2位、第9戦 ダラスGPで復帰後初勝利を収めています。ドライバーはどちらもケケ・ロズベルグ(Keijo
Erik "Keke"
Rosberg)。ちなみにダラスでF-1GPが開催されたのはこの年が最初で最後であり、よってホンダエンジンは未だにダラスGPにおける唯一の優勝エンジンだったりします(ちなみにアメリカでは不人気なF-1のため、CAN-AMレースと二日連続の開催となった。このため、前日のレースで路面が荒れていたところに猛暑でアスファルトが溶け始め、あらゆる意味で前代未聞の荒れたレースとなり、その大混乱を制したのがベテランドライバーのロズベルグだった)。
余談ですが前年一杯でホンダが手を引いたスピリット チームも1984年にハートエンジンを搭載、独自に参戦してました(どうも川本さんが密かに資金援助したらしい形跡もあり)。ただし一台だけの参戦で、一度も入賞できず、翌1985年の開幕から3戦戦ったところで資金が尽き、チームは消滅する事になります。

そのダラスGPで優勝したウィリアムズ ホンダ
FW09。エンジンは川本さん世代の
ホンダ ターボエンジン RA164E。
前年にホンダが走らせたスピリットの201Cに比べると全体がキチンとカウルで覆われ車高も低めに抑えられるのが見て取れます。1980、1981と2年連続でコンストラクターズ チャンピオンを、そして1980年と82年にはドライバーズ チャンピオン(ジョーンズとロズベルグ)を獲った強豪チームだけに、全体が洗練されてるという感じですね。
ただしこれはスピリットの201Cがあまりにもひどかったための印象で、丸くて厚みの大きい先端部などは当時としても古臭く、さらにシャシーは未だに完全なアルミハニカム構造でした。当時はまだ軽くて頑丈なカーボンモノコックへの移行期ではあったのですが、トップチームの多くがカーボンファイバー モノコック、あるいは一部だけアルミハニカムで残りはカーボンといった車体に移行していたいのに比べると、明らかに時代遅れでした。この辺りは当時のウィリアムズの保守性の表れで、こういった保守性が原因の一つとなって、後にホンダはウィリアムズと手を切る事になります。
展示の車はそのダラスGPの優勝車で、ドライバーはケケ・ロズベルグ。二年前、1982年のドライバーズ チャンピオンだった人ですね。ちなみにケケは、2016年にメルセデスに乗ってドライバーズチャンピオンとなったニコ・ロズベルグの父親で、最近は随分と多い、親子でF-1ドライバーの一人です。そのニコが産まれたのはウィリアムズ・ホンダ時代の1985年でした(翌86年にマクラーレンに移籍後、ケケは引退)。
さらに余談ですがケケ・ロズベルグはかなり変わった記録を持つF-1ドライバーでした。
デビューから初勝利まで5年かかったのですが、1982年の第14戦スイスGPで念願の初優勝を記録すると、この一勝だけで同年の世界チャンプになってしまいます。参加チームの参戦拒否騒動、相次ぐドライバーの事故死による混乱(あのジル・ビルヌーブが事故死した年である)、これらの大混戦の中で、コンスタントに2位、3位と入賞してポイントを稼いだ結果でしたが、さすがにこれは異例でした。
F-1初期の1958年にフェラーリのマイク・ホーソン(John
Michael "Mike" Hawthorn
)も1勝だけでチャンプになってますが、この時代は全11戦であり、1982年の16戦に比べるとレース数が少なかったのです。なので1982年のケケのドライバーズ チャンピオンは極めて異例であり、そもそも未だに年間1勝でチャンピオンになったのはこの二人だけです。さらに言えばケケは生涯を通してでも5勝しかしてないワールドチャンピオンでした。
1990年代以降の近代F-1だと年間5勝未満のチャンピオンですら皆無であり、どうも歴代ワールドチャンピオンの中ではかなり見劣りがするなあ、という気がします。一定レベルの速さを持っていた人ではあるんですけど、ワールドチャンプの肩書がふさわしいかと言うとなあ…という感じですね。
ついで言うと、第二期歴代ホンダのドライバーの中でこの年のラフィット、そしてロズベルグは共に極めて評価が低く、特にマンセルのようにマシンの開発に献身的なドライバーをホンダが知った後は、自己中心的でメカニックと情報交換もしないケケの評価はガタ落ちだったようです。このため、彼はホンダが本格的に勝ち始めた85年を持ってウィリアムズから事実上追い出される事になります。
話を戻しましょう。
ホンダとウィリアムズの契約成立は意外に遅く、すでに1983年のシーズン開幕後、6月になってからでした。この辺りの事情を少し見て置きます。
ホンダは最初からエンジンだけの供給を考えており、1982年中には相棒となるチーム探しが始まってましたが、F-2で十分な戦力を見せていたホンダエンジンに興味を示したチームは複数ありました。さらにホンダは無償でエンジンを提供する、という条件でしたから資金繰りに悩む多くのチームには魅力的な提案だったのです。この話に積極的に乗って来たのがマクラーレンとウィリアムズだったのですが、15年間の中断によりホンダは当時のF-1チーム事情に疎く、しばらく様子見の状態となります。まだエンジン設計が終わってない、という面もあり、川本さんはそれほど焦って無かったようです。
そんな時、ホンダの関係者の一人が、あの第一期ホンダF-1の恩人、ジャック・ブラバムと飛行機で乗り合わせるという幸運に見舞われ、ホンダは彼にコンサルタントの仕事を依頼します。すでに彼はF-1のチーム運営から離れていましたが(ブラバムチームは別オーナーになっていた)、その豊富な人脈はホンダにとって有難いものだったのです。結局、ブラバムの情報によってマクラーレンはポルシェとも交渉中であり、ホンダの相手に相応しいのはウィリアムズだろう、という決定が下されます。
これを受けて1983年に入ると川本さんがその交渉を開始しました。
が、チームのオーナー、フランク・ウィリアムズも長年レース業界で苦労していた人ですから一筋縄で行く相手ではなく、ウィリアムズに有利な条件を含む契約の締結を主張、これに激怒した川本さんが事実上の絶縁状を送り付け、両者にらみ合い、という状況になってしまいました。結局、二カ月近く経ってウィリアムズが折れてその条件を撤回、1983年6月に3年間エンジン供給の契約が成立します。
直後の7月にスピリットのシャシーでホンダはF-1復帰を果たすのですが、当時、フォード・コスワースの自然吸気エンジンの戦力不足に悩まされていたウィリアムズは少しでも早くホンダのターボエンジンを欲しがり、このため同年最後の南アフリカGPでウィリアムズ・ホンダとしてデビューを果たす事になりました。
ちなみに当時のウィリアムズは後輪を四輪にした6輪F-1を本気で開発していたのですが、1983年の規定(レギュレーション)から車輪は四つまでと制限されたため、これを投入できず、あわてて従来の車を改良して参戦、そのため車体の開発が遅れていた、という面がありました。逆に言えば、もし1983年に規定が変更されて無ければ、ホンダエンジンの6輪マシンが誕生していた可能性もあるのです。

FW09はその1983年最終戦でデビュー、翌1984年まで投入されたマシンです。
まだまだ80年代前半ですから全体にモサっとした感じなのは仕方ないですが、それでも全体的にもうちょっと洗練されても…と思ってしまう所。さらに川本さん世代のホンダ ターボも優秀なエンジンとは言い難く、まだまだ全盛期前のマシンという感じではあります。ちなみにアンダーステアの強い(ハンドルを切ってもあまり曲がらない)扱いにくい車だったという話もあり。
ドライバーの頭の上までカバーが付いてますが、これは転倒時の保護用支柱を囲っただけで、空気取り入れ口は付いてません。ちょっと見づらいですがサイドポンツーンの一番後部の端から上に飛び出してるのが排気タービン用、すなわちターボエンジン用の空気取り入れ口。
展示車はダラスGPの優勝車ですから、初期型の無印FW09ですね。これはケケ・ロズベルグがダラスで優勝しただけでなく、初戦のブラジルで2位に入賞したタイプでもあります。以後も初優勝のダラスGPまで、ロズベルグは4位を二回、6位を一回獲得、同僚のジャック・ラフィット(Jacques-Henri
Marie Sabin
Laffite)も4位と5位を一回ずつ獲得してますから一定の完成度を持っていたようです。ただしケケが4回、ラフィットが5回と半分近くをリタイアで終わってますから、決して安定して速い車ではありませんでした。
さらに優勝した次の第10戦イギリスGPからは改良型の09B
になるのですが、こちらのマシンはさらに悲惨で7戦中で完走できたのはケケとラフィットがそれぞれ1回だけ、後は全てリタイアで一度も入賞すらできない、という結果に終わります。全てホンダエンジンのせいでは無いとはいえ、7戦中5戦が2台揃えってリタイアですから勝負以前の問題であり、こうなるとその戦力不足は明らかでした。
そういった状況の中、新たにホンダの「総監督」として桜井さんが登場、市田さんをレースエンジン開発に復帰させ、新世代のホンダ ターボエンジンの開発を始める事になるわけです。
ついでに1984年はデビュー二年目のポルシェ ターボエンジンを搭載したマクラーレンが圧倒的な強さを見せ、16戦12勝の圧勝でコンストラクターズとドライバーズ(ニキ・ラウダ Andreas
Nikolaus "Niki"
Lauda)の両チャンピオンを獲ってしまいます。これと比べるとウィリアムズ・ホンダの戦闘力不足は明白でした。
そもそもダラスでの優勝は、摂氏38度という前代未聞の猛暑となって他のマシンが熱問題のために全力で走れなかった事、加速が短い曲がりくねった市街地閉鎖コースでホンダエンジンに向いていた事、そしてロズベルグがそういった市街地コースを得意としていた事、といった幸運が重なった面がありました。実際、ロズベルグの予選順位は8位に過ぎず、決して速いわけでは無かったのです。彼の優勝は他のマシンが次々と暑さで脱落した結果、という面がありました。
ちなみに多忙だったF-1番長、当時のホンダF-1部門責任者だった川本さんはなんとか時間を確保してこのダラスGPを見学、その目の前で自分の設計したエンジンの初勝利とホンダF-1第二期初勝利を目撃する事になりました。ちなみに前年の夏に事実上の四輪レース部門の責任者代行だった宮本さんが心臓病の疑いで現場を離れて以降、設計面を川本さんが見て現場はメカニックの土師(はじ)さんが担当する分業体制でした。ただし84年まではまだF-2にも参戦してましたから、二人の多忙ぶりは想像を絶するものがあったはずです。これが後に桜井総監督の登場に繋がるのですが、この点はまた後で。
さらに余談ですが、このダラスGPで予選1位、ポールポジションを獲っていたのがあのマンセルでした。ホンダのF-2
復帰で最初にハンドルを握った彼はロータスのドライバーとしてF-1に参戦しており、ダラスではポールからスタートしてレース中盤まではトップを維持してました。その後、高温による熱中症と思われる状態でレース後半になると順位を落とし、タイヤの摩耗にも悩まされた結果、最終ラップに入るころには6位前後まで、すなわち当時の入賞ギリギリの順位まで落ちてました。
そして不幸な事に、最後のチェッカーフラッグ直前でマンセルの車は壁に衝突、これによってゴールライン直前でマシンは故障して止まってしまいます。するとマンセルはマシンを飛び降り、38度を超える猛暑と強烈なアスファルトからの照り返しの中、車を手で押してゴールラインを目指し始めるのです。当時のルールは今よりかなり緩く、おそらく手で押してゴールしても認められたのでしょうが、結局、その直後に熱中症と脱水症状で彼は昏倒してコースに倒れてしまい、周囲に抱えられてコースから去る事になりました(ゴールラインを超えられなかったが最終的に6位入賞扱い)。
当時の日本ではF-1の中継は無く、私がこれを見たのは1990年代に入ってビデオでなんですが、なんとういう闘志だろう、と身の毛がよだつような感動を覚えたのを今でも鮮明に覚えてます。後に見るようにマンセルはウィリアムズ・ホンダで悲劇のドライバーとなり、最後は1992年にウィリアムズ・ルノーに乗ってホンダの第二期にとどめを刺すドライバーです。人間性にいろいろ問題のある人なんですが(笑)、とにかく勝ちたい、すこしでも上の順位でゴールしたい、という闘志は本物で、これこそF-1ドライバーだ、と今でも個人的には思っています。個人的にはホンダエンジンで走ったドライバーの中ではセナより好きな一人です。セナも静かなようで闘志のカタマリですが、ちょっと暗いんですよね。

後ろから見る。かなりスッキリとまとめられています。
この車もリアウィングは左右の垂直板で支えるタイプで、後部の太い銀色のパイプで車体に固定してるわけです。
リアウィングの左右に小さいウィングが追加されてるのは曲がりくねったダラスのコース対策で、少しでもダウンフォースを稼いで後輪の接地圧を高め、カーブを高速で走り抜けるためのもの。こういった工作が許されたのも、当時の規定がまだまだ緩かったからです。
ウィング下に見えてる小さい箱は例によってミッションオイルクーラーだと思われます。ついでにこの時代のF-1はまだ後部のブレーキランプがありません。