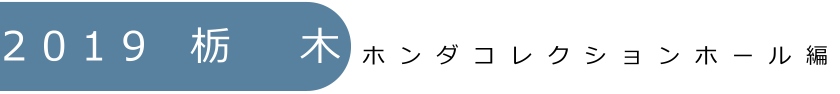

RA-272を正面から。
ピカピカなのでワックスを掛けてあると思われます。ちなみにホンダがレーシングカーの車体にワックスを掛ける、というのを知ったのは参戦二年目の第三戦ベルギーグランプリ(ホンダが1965年に参戦したレースとしては二戦目)からだとエンジン設計に参加&現地でレース活動を支えた丸野冨士也さんが証言してます。ちなみにそのベルギーGPでギンザ―が6位入賞、ホンダに初めてのポイントをもたらしました。
ただしこれが空力抵抗対策だとは考え付かず、単にマシンをキレイにしてるのだと思っていたようで、どうもホンダは第一期の最後までオシャレの問題としてマシンにワックスを掛けていた可能性が高いです(笑)。丸野さん本人も最後に整備漏れがないかを確認するためにワックスがけをやってたと、と証言してますし。
正面のラジエター空気取り入れ口はかなり下向きに絞り込まれてますが、これは後期型の特徴で、前期型では逆に上向きの構造でした。どうもこの辺りの改修には中村さんが関わってるようなんですが、下向きにした方が冷却効果がある、という事でこの形になったようです。

参考までに同じ角度から見た前年型のRA-271。
前輪の支柱&ラジエター(外からは見えない)から先のフロントカウル部はモノコックシャシーから独立した樹脂製のカウル、すなわちただのガランドウなので形状変更が容易であり、このためかなり変更が加わってるのが判ります。平面的なRA-271に対し、やや楕円に近いRA-272
という感じでしょうか。
フロントサスペンションがRA-271は上向きの傾斜、RA-272
では下向きの傾斜になってるのは、例の後輪の支柱高さ調整と併せ、こちらも車体を少し上に持ち上げてるのだと思われます。この辺り、エンジン取付位置を10㎝下げてしまったので、ケツをこすらないように、という配慮もあったんじゃないか、と思うんですが確証は無し。
またRA-271にある鼻先の赤いホンダのロゴマークが、ギンザ―のRA-272
では無くなってしまってますがこの理由は不明。実際、メキシコ戦ではギンザ―のマシンはホンダマークを付けてなかったのですが、同僚のバックナムのマシンには普通に付いてましたから、輸送中に剥がれちゃったとかですかね。

真後ろから。エンジンカバーが短くなり、露出が多くなった分、RA-271とはだいぶ印象が変わってます。
よく見ると車体下にも2本の排気管が見えてますが、これは横置きエンジン前部の6気筒分のもの。3本ずつ集合させて2本にしてるのは上部の集合排気管と同じ。
横置きエンジンの欠点の一つがこれで、当たり前ですがV12エンジンの半分、6気筒分は前側に位置します。そこから車体後方にまで排気管を引っ張りまわして来なくてならず、さらに等長集合排気管(カタカナ英語スキーの皆さんが言う所のエキゾーストマニホールド)ですから各管の長さを揃える必要があり話はもっと厄介になります。このため外からは見えませんが、この前部排気管の取り回しも複雑で、さらにRA-272後期型
では大きく変わってます。
ちなみにこの下側の集合排気管はエンジン下部にあるオイルパンを避ける構造になっており、すなわちまだドライサンプになってません(後期型では詳細不明だが恐らくやって無い)。それじゃダメじゃん、という点は次回のF-2の話で少し触れます。
ついでにエンジン後部から出て来る上部排気管(エンジン後部6気筒分)は相変わらず長いのですが、支柱はやや短く、より目立たないものになってます。
サスペンションもRA-271から大きく変わった部分で、上下分割支柱、変形ダブルウィッシュボーン(上がIアーム支柱、下が逆V字形支柱)ながらスプリングの入ったダンパー部が外に出た原始的な形状になりました。これは整備性を優先したためで、これによってサスペンションの調整は容易になった…というかようやく他のチームのマシンに近いものになったのです。
当然、空気抵抗は増えるのですが、前輪ほどの影響は無いので、当時のF-1では後輪はこの形のものが多いです。ただしこの後、1970年代に登場した前後ウィング、さらにウィングカー、グランドエフェクトカー、そしてそれらが禁止された後のフラットボトムでも後部ダンパーが引き起こす乱流は空力接地圧(ダウンフォース)の発生に致命的な悪影響を及ぼすため、再び車体内収容式(インボード)型に戻って行きます。
後ろから見ると、サスペンションが直接エンジンに取り付けられる、すなわち車体後部には車体(シャシー)構造が全く無く、エンジンがその構造を直接担当してるのが判ると思います。これは横置きエンジンのホンダならではの苦心の妥協策だったのですが、全体の構造の単純化につながるので、後にあのロータスなどがこの構造をパクッてます(ロータス49や微妙に構造が異なるが基本的な思想は同じフェラーリ312Bなど)。
意外に知られてませんが、ホンダのマシン、その独自性のいくつかは、後に多くのチームで模倣されてるのです。従来のゴム袋式の燃料タンクではなく、モノコックの中に隔壁で一室を造り、そこを燃料タンクにする構造も3000㏄F-1時代に最初にホンダがやってますしね。

運転席。正面の風防ガラスが良く見ると二段構造になっていて手前に伸びてる部分が運転席周辺の空気の整流効果を行ってます。ただしこの時代のホンダ、というかF-1における空力は極めて怪しく、まともな風洞実験をやってるとは思えないのでその効果は不明。さらに風防ガラスの取り付けネジはむき出して、ノンキな時代ではあったのだなあ、と思われます。
メーター類は意外に多く、真ん中の一番大きいのがエンジン回転計(タコメーター)、左端が油温、その隣が水温、回転計を挟んで右側は燃料関係(燃料&燃料圧?)だと思います。オービスも白バイも居ないサーキットでは速度違反で捕まる事は無いので速度計は無し。実際、走ってる時に今何km/h なのかはどうでもよく、相手より速いか遅いかだけが問題となるレーシングカーに速度計は不要なのです。
車体前部、日の丸のところで車体に大きな隙間がありますが、その手前と前輪の支柱部分までがジュラルミンモノコック(次回説明)部、そこから先はただの樹脂製のカバーです。前輪に繋がる蛇のようなパイプ、前回ブレーキ関係だと思うけど不明、と書きましたが、どうやらブレーキ液用のパイプと見ていいようです。
画面左下手前に先に説明した後輪支柱の上下に別れた取り付け部が見えてます。これ、結構空気抵抗になりそうなんですが、ホントに必要がったのかなあ。
運転席脇の左右を走るホースはラジエターの冷却液のもの。フロントに置かれたラジエターで冷却して後部のエンジンに送り込むためこういった長いホースが必要だったのです。おそらく右の金属パイプが高温でラジエターに送られるもの、左の樹脂製ホースが冷えた後、エンジンに送り返されるものでしょう。
で、一目で判ると思いますがホースは完全に剥き出しで運転席の高い位置を走っており、これ触ったら確実に大やけどです。ドライバーはもちろん、整備員も危険にさらされる設計で、なんぼ極限を求めるレーシングカーでもこれはどうか、という部分です。他に場所は無いので、多くのマシンがこういった構造を取ってるのですが、通常はここにカバーを付けて剥き出しにはしません。このマシンの欠点の一つでしょう。
ちなみに設計者の佐野さんは東大工学部航空学科の出身で、ああ、なるほどと思ったり(笑)。あそこの皆さんの設計は戦中から戦後にかけて性能さえ出ればいいのだ、オレの優秀さを見よ、乗ってる人間がどうなろうか知った事か、という面が非常に強いのです。まあ、一種の伝統なんでしょうねえ…。個人的には東大工学部空工学の出身の皆さんが設計した乗り物はあまり乗りたいと思いませぬ。
さらに余談ですが、この時期からホンダは航空機関係の一流のどころの人材をかき集め始めます。佐野さんは1960年入社ですが、その3年後、例の北斗神拳伝承者兄弟クラスの人材がそろった1963年では、入交さんと吉野さん(五代目社長)が東大工学部航空学科の出身ですし、吉野さんは入社後はしばらくガスタービンの研究をやってましたから、どうもホンダは航空機部門への進出を狙っていたんじゃないかという気もします。東大の航空学科系の教授連とも付き合いがありましたしね。
実際はホンダが密かに航空機の開発を開始するのは後の久米社長時代、1986年からなので、20年以上の時間差があるのですが。
といった感じで、ホンダの1500㏄F-1の時代は初勝利と共に終わり、3000㏄の時代を迎えるのですが、同時にホンダにとってはより大きな成功体験となるヨーロッパにおけるF-2選手権の圧勝が始まります。次回はその辺りを見て行きましょう。
とりあえず今回はここまで。