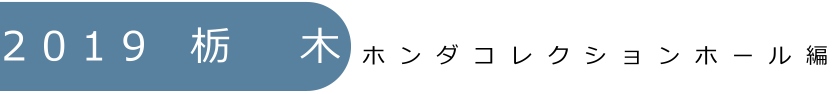

このホンダコレクションホールの入り口は極めて質素でした。
こういった施設では、つい本田宗一郎総司令官の銅像とか肖像画とか飾りたくなるであろうところをしっかりと自制し、いらぬ個人崇拝を徹底的に廃してる辺り、見事だなあ、と思いました。本田、藤沢の御両人が見ることができたなら、満足したんじゃないかと思います。
ある意味で巨人であり、天才であり、狂人であった本田宗一郎総司令官は功罪共に極めて大きいのですが、その引き際は見事でした。全体的には藤沢副社長がシナリオを書き、本田宗一郎総司令官はそれに乗せられた、という部分があるのですが、明らかに判っていながら黙って自分から乗って行ったと思われる部分があり、やはり見事だなあ、と思います。
もはや旅行記ではない、という感じですが、せっかくですから、その辺りを少し見て置きましょう。
ホンダ、すなわち本田技研工業では研究開発部門が1960年から「本田技術研究所」という独立した別組織の株式会社になっていました。つまりホンダの社内に研究部門は存在しないのです。この別会社である研究所の社長も本田宗一郎総司令官が兼務しており、むしろこちらが彼の仕事にとって中心的な地位でした。
この研究部門の分社化は営業のボス、藤沢専務(後に副社長)の主導によるもので「時代が求める品物を自らの手で、積極的に掘り出していくべきだ」という彼の主張が影響してました。すなわち、流行を追うのではなく、他所の会社のヒット作をまねるのでもなく、自分の頭で考えて時代の先端を行け、という事であり、これは本田宗一郎総司令官の考えと非常に良く似ていました(同じような考えを持っていた人物にソニーの創業者の一人で経営者であった盛田昭夫さん、そしてアップルのスティーブ・ジョブスが居る。ただしジョブスはソニーから影響を受けた(というかおそらく盛田さんの著作、MADE
IN JAPAN
を読んでる)からだが)。
ちなみに、1967年末に藤沢さんが行った講演の中で以下のような発言があります。
「ホンダは、松明(たいまつ)を自分の手でかかげて行く企業である。
日本の自動車企業には前を行く者の持つ明かり、その明るい所について行くものが多い。が、たとえ小さな松明であろうと、自分で作って自分たちで持って、みんなと違ったところがありながら進んでいく、これがホンダである」
まるで本田宗一郎総司令官の発言のようですが、これが藤沢副社長の発言であり、二人が根源的な部分で深く共闘していたのだ、という事が判ります。藤沢さん、ただの営業屋じゃないのです。
ホンダという会社は本田宗一郎総司令官の天才性による所が大きいのは事実ですが、実際にその基盤となっている企業体質、思想などは半分以上が藤沢副社長によるものだと思っていいでしょう。
例えば日本の企業の中ではかなり早い段階から国際展開をしていたホンダですが、これも藤沢副社長の決断によるものでしたし、以前もちょっとふれたマン島TTレースを目指す事を明らかにした宣言文も、実際は藤沢さんが書いたものでした。
このためホンダの本社で経営を取り仕切っていた藤沢専務(当時)は、本田宗一郎が研究に没頭出来て、さらに独創的な後継者をそこで育成できる純粋な研究開発部組織の設立を考え始めます。ちなみに、二人の社内での呼称は本田宗一郎総司令官が“親父”、藤沢副社長が“叔父上”で、ほぼ同格の存在として下からは見られていました。
(言うまでもなくヤクザ用語で、当時はやっていた仁侠映画の影響かと思われる。自分の組織の長が“オヤジ”であり、その兄弟分となってる別組織の長が“オジキ”、叔父上である。技術部門の長が本田宗一郎総司令官、営業部門の長が藤沢専務と言う事)
余談ですが藤沢さんは当時全訳が出たばかりのチャーチルの「第二次大戦回顧録」を徹底的に読破していた人であり、変なところで変に軍事的な知識を持ってたりします。さらには私も未読のドゴールの回顧録も読んでいたようで、この人はこの人でスゴイ人なんですよ。ちなみに、どちらの著者も狂人なので、本田宗一郎総司令官を理解するのにも役立ったはずです(笑)。世の中の社長が山岡荘八の「徳川家康」とかをありがたがって読んでる時代に、この人は違う世界を見ていたのです。
ちなみに研究所設立3年前の1957年株主総会で本田宗一郎総司令官は企業の研究開発に触れているのですが、
「実験研究は、バランスシート(経営上の数字のこと)にじかに反映するようなものではなく、効果を実測することのできない極めて地味な性質のものですが、この意義は極めて大きいものがあります」
と21世紀に入っても十分耐えうるどころか、未だにこれ以上は無いであろう見事な説明を行っています。この辺りはホントに掛け値なしでスゴイ人なのです。
こうしてホンダがまだ四輪に進出する前の1960年、独立した別会社として本田技術研究所が埼玉の和光に設立されます(出資額はホンダ本社が50%、本田宗一郎総司令官が25%、藤沢専務(当時)が25%なので事実上の子会社だが一方的な力関係ではない)。
ちなみにこの技術研究所の独立にホンダの労働組合は強硬に反対、藤沢さんがその折衝にあたってるのですが、当時の資料を読んでもなんで反対してるのか、よく判りませんでした。世の中によく居る、とにかく反対しとけ、という皆さまだったんですかね。
こうして本田宗一郎総司令官はホンダ本社と研究所の両方の社長を兼務しながら、実際は常に埼玉県和光の研究所の方に居て陣頭指揮を執っていました。H1300の開発、F-1マシンの開発で彼が徹底的に現場に介入したのはホンダの社長としてではなく、この技術研究所の社長としてだったのです。
ちなみに技術研究所には社長とは別に研究所長の役職があり、本来ならこちらが現場の総責任者だったのですが、経営者である本田宗一郎総司令官は現場への介入を繰り返しており、研究所の体制は何から何までほぼ彼の独裁でした。
つまりこの研究所は本田宗一郎総司令官が「俺の造りたい車を、俺の考えた技術で、俺の造りたいように造る、俺の会社」だったわけです(なにせ大株主でもあるのだ)。

その独裁制はオートバイ時代と軽自動車開発時代まではそれなりに上手く回っていました。
が、より高度な技術力が求められる一般乗用車への進出では勘と経験だけに基づく総司令官による頭指揮には無理が出て来ました。その結果としてH1300が商業的に大失敗、その時代の終焉を向える事になるのです。特にH1300の開発では多くの研究者がこんなの無理だと思いながら最後まで苦闘した結果が商業的な大失敗だったので研究所全体の士気まで低下してしまう事になりました。
一方で、藤沢副社長の縄張りだったホンダ本社の体制は、すでに1970年から大きく動いてました。
1970年4月の株主総会で本田、藤沢の二頭体制に加え、河島(後の二代目社長)・川島(後に副社長)・西田(同副社長)・白井の四人の専務が任命され、徐々にその権限がこの四人に移されつつありました。1970年中にはすでに四専務が事実上の経営判断を行い、藤沢副社長は最後の裁可を出すだけになっていたようです。
が、1970年の技術研究所は事情が違いました。社長である本田宗一郎総司令官はまだまだ先頭に立って指揮を執っていたのです。すでにH1300で彼の技術者としての限界は見えていたのですが、本人はまだヤル気で、これに対して研究所内では倦怠感に近い雰囲気すらあったようです。
この結果、研究所内で本田宗一郎司令官には引退してもらおう、という動きが出て来ます。その推進派の中心に居たのが空冷エンジンで苦しめられ、二度も失踪事件を起こしたあの久米さんでした。そういった人物が後に三代目社長になってしまうのだからスゴイ会社ではあります。とりあえず現場からはもう本田宗一郎総司令官には引退してほしい、という声が日増しに強くなっていたのです。
こうなると本来なら技術部門の事実上のトップであった河島さんが本田宗一郎総司令官にその引導を渡すべきと思われていたのですが本人が固辞したらしく、結局、経理、営業畑の出身だった四専務の一人、西田通弘さんがその説得に向かいます(ちなみに河島さんが本田宗一郎直系の立場であるのに対して西田さんは藤沢直系の人材だった)。
二人が昼食を共にした席で、技術研究所所長からの退任、後進への禅譲を西田さんが切り出したところ、意外にもあっさりと本田宗一郎総司令官はこれを受け入れ、その場で引退が決まったとされます。ちなみに本田宗一郎伝説の一つ、引退を勧められた時に「よくぞ言ってくれた」と泣いたとされるのはこの時で、ホンダ本社社長引退の時ではありません。この辺り、よく混乱されてるので注意。ただし、本田宗一郎総司令官が泣いて感謝した、という話は引退を勧めた西田さん本人の証言以外は無いようなので、ホントかどうか個人的には半信半疑ですが…
この結果、1971年4月、本田宗一郎総司令官は技術研究所社長の地位から身を引くことになります。後任には零細企業時代からの社内たたき上げ、ドリーム号系のオートバイエンジンの設計担当者であり、初代二輪世界GPチームの監督でもあった技術部門のトップ、河島喜好さんが指名されました。ちなみに既に何度か触れてるように河島さんは後にホンダ本社の二代目社長にもなるのですが、この研究所社長から本社の社長となる、というのは以後、ホンダ社長就任の定番コースとなり、これは八代目社長である八郷さんによって初めて破られるまでずっと続いてました。
余談ながらエンジン屋でない最初の社長が七代目 伊藤さん、そして研究所社長でもない最初の社長が八代目 八郷さんで、この二人が社長になった結果、現在のホンダがどんな状況にあるか、を考えると古い慣習というのはなんでもかんでも破ればいいものでは無いんでしょうね。
とりあえず、この1971年4月の技術研究所社長からの引退により、本田宗一郎総司令官が「オレの考えによって、オレの造りたい車を造る」ための会社だった技術研究所が、その呪縛から解放される事になります。シビックの開発開始は1970年夏からでしたが、それが本格的に始動したのは本田宗一郎司令官の退任前後、1971年からとなりました。
このため、ホンダとしては初めて、本田宗一郎総司令官による「オレの好きなようにやる車造り」ではなく、現場の人間が主導して発案された車造りが行われた事になりるのです。
余談ながら当時の研究所のメンバーがH1300を造ってる鈴鹿工場の見学に行ったら、ラインを流れて来る車体はほとんどなく、ここまで売れてないのかと驚いた、と語ってますから、ホンダとしてはギリギリの線、まさに9回裏ツーアウトの状態だったのでした。
幸いにして本田宗一郎総司令官の呪縛を逃れた研究所のメンバーはそれまでのうっ憤を晴らすかのようにシビックの開発に邁進、これで大ヒットを飛ばして、それまでの不調がウソのようにあっさりホンダを世界的な自動車メーカーにしてしまったわけです。
ちなみに本田宗一郎総司令官は一連の失敗を「損失が大きかったが、全部従業員の血と、肉となっているのが本田技研だ」と述べております。確かにそういった面はあるものの、大きすぎでしょう…。実際、四輪車撤退直前まで追い込まれてますし。
ただし本田宗一郎総司令官は研究所から引退しても、ホンダ本社、本田技研工業社長の地位の方は維持していました。が、そもそもそちらの仕事に関しては興味も影響力も薄く、このため、例の四専務が事実上、会社の切り盛りをしていました。
そして1973年3月に藤沢副社長が会社を後任に譲る時期が来たと判断、「自分は引退する」と本田宗一郎総司令官に伝え、それを聞いた本田宗一郎総司令官は「二人一緒だよ、俺もだよ」とあっさり答え、本田技研工業の社長も辞める事になりました。
ちなみにこのやり取りもまた、先の西田さんが間に入ったのですが、彼の証言だと、本田宗一郎総司令官はもう少し長いセリフを言ったことになってます。が、どうも西田さんの話は微妙な部分がいろいろあるので、ここでは藤沢さん本人の証言を採用します。
こうして1973年10月に本田、藤沢の両巨頭は社長、副社長を引退、会長職にもとどまらず、すべてをまだ45歳だった河島新社長と西田、川島の二人の副社長に譲って身を引いてしまったのでした(代表権のない最高顧問として会社には残った)。
見事な進退だったと思います。
この辺りの段取りを取ったのはほぼ全て藤沢副社長であり、もし藤沢副社長が居なければ死ぬまで本田宗一郎総司令官は研究所社長だった可能性もある気はします(笑)。が、それでも藤沢副社長から遠回しに我々はもう引くべきだ、と告げられると即座に全てを悟り、なんの未練もなくすべてを禅譲してしまった点はやはり見事でしょう。
ちなみに藤沢副社長はほとんど表に出ず、本田宗一郎総司令官が陽なら藤沢副社長は陰、という印象が強いのですがこの人も只者ではなく、そして両者のキズナは外部からではよく理解できない、不思議なものであったようです。ちなみにそれほど密に顔を合わせなかった二人ですが、奥さんどうしが親密でこれも両者の円滑な関係に役立った、という話があります。
相手を完全に信用していたため基本的に没交渉であり、このため不仲説さえあった二人ですが、引退が決まった後、1973年の9月にホンダ社内向けに発行された「監督者広報 特別号」に藤沢福社長が寄稿した文章を読むとそんな単純なものでは無いなあ、と思い知らされます。以下に主な部分を抜粋します。
「社長は技術、私はお金に関係する仕事、これがスタートで始まった。二人とも勝手放題、思ったとおり決裁もすれば行動もする。一致することは"会社を大きくすること"。双方のすることに疑念、指示、苦情は一切ない。顔を見合わせれば、未来への夢のような話ばかりである。これほど楽しいことはない」
「社長に私の構想を前もって話をするとか、了解を得るとかしたことはありません。畑違いの人であると同時に、あの人の頭は技術のことでいつもフル回転です。(中略)ですから、私の部門まで指示をされるようでは、これだけの急激な技術の上昇はなかったでしょう。また、私も自由な発想がやれないようでしたら会社にはいなかったでしょう。もちろん、こんな大企業の副社長になど思いもよりませんでした。いずれにせよ、この人と逢え、思う一杯にやれ、恵まれた人生を過ごさせてもらいました」
「その後(引退決定後)あるとき、顔を合わせた。こっちへこいよと、目で知らせられたので一緒に連れ立った。
「まァまァだナ」と言われた。
「そう、まァまぁさ」と答えた。
「幸せだったナ」と言われた。
「本当に幸福でしたよ、心からお礼を言います」と言った私に、
「俺も礼を言うよ、良い人生だったナ」
とのことで、引退の話は終わりました。いつも、こんな話しかしない二人の間だけど、顔を見るだけでもけっこう楽しい」
こういった関係にある極めて有能な二人という実例を私はあまり知らないのですが、見事な関係のように見え、かつ外部の人間にはおそらく永遠に理解できないであろう部分があったように思います(大政奉還前の西郷と大久保の関係が一番近いかもしれない。両者が相手を嫌っていながら明確な役割分担を果たした有能な同志という例ではナポレオンとタレイラン、ビスマルクとモルトケなどがあるが)。
この辺り、本田宗一郎総司令官は神格化さえされるほど研究されてますが、藤沢副社長とホンダと言う会社についてはまだまだ研究余地が大きいようにも思います。まあ、旅行記で突っ込む話とは思えないので、この点に関してはとりあえずここまで。
(*余談であるが、藤沢副社長の表記はホンダのサイトでは藤“澤”となっている。が、本人の著作における表記、それ以外の資料でも藤沢が普通なので、ここでは藤沢と表記した)