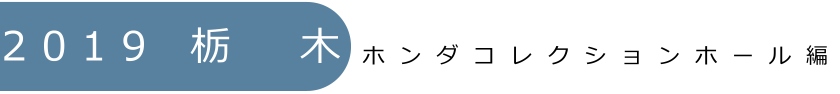
さて、前回見たように桜井「総監督」は1984年後半の就任当初、川本さん世代の大口径(ショートストローク)ターボエンジンの改良を試みたものの、 監督就任第二戦のヨーロッパGPの段階で早くも小口径(ロングストローク)新型エンジンの開発を決意します。ただし、その新型エンジン投入までの道のりは決して平たんではありませんでした。
10月7日の第15戦
ヨーロッパGPを視察してショックを受けた桜井さんと市田さんは日本に帰るとさっそくホンダのF-1関係者、設計、加工、組み立てのなどに関わっていた人員を集め対策会議を開きます。現場からは後藤さんも呼び出されて会議に参加したようです。この時期のホンダF-1関係者はまだまだ少人数で、「F-1地上の夢」によると会議の参加者は40名前後、桜井さんの「ゼロからの挑戦」によるとさらに少ない30名に過ぎなかったとされます(おそらく桜井さんの30名説が正しい。この時期のホンダF-1チームは総員で40名しかおらず、一部はまだイギリスに居たと思われるので)。
ここで桜井さんが翌1985年から新型エンジンへ変更を宣言するのですが、会議に出ていたF-1番長 川本さんがこれに激怒、現在のエンジンの問題点も調べずいきなり新型エンジンなんて認めねえ、ロングストロークがいいなんて聞いたこともねえ、と宣言して会議から出て行ってしまうのです。
自分が設計したエンジンが完全に否定された事、ホンダのエンジン設計思想の根幹、大口径(ショートストローク)までも否定された事、さらに少なくとも一度は勝ってるエンジンであり(しかも本人の目の前で)、キチンと改良を重ねればまだ戦える、という考えが川本さんにあったのがこの激怒の原因と見られます。ちなみに桜井さんによると、この時の会議はもつれにもつれ、本来は技術的な問題の議論だったはずなのが、最後は不毛な精神論的な論争になってしまったそうな。その最後に川本さんは席を蹴って出て行ってしまったわけです。
が、これはすでに設計の現場を離れ、管理職どころかホンダの経営陣に加わりつつあった川本さんの限界であり、時代から取り残された設計屋さんの発想だったと言っていいでしょう。実際、この辺りの事は後に本人も認めてます。が、とにかく川本さんが拒否宣言をしてしまった事で新型エンジンの設計は危ぶまれました。
ただし桜井さん達もこっちはこっちで、川本さんが反対しようが構わんからやっちまえ、と設計を開始、既に書いたように年内に市田さん率いる設計班が新型エンジンの設計をまとめ上げてしまったのです。ただしさすがに上司の川本さんの意見を全く無視するわけにも行かず、そして奇跡のような傑作エンジンが産まれるとはさすがに誰も予想して無かったため、同時進行で川本さん世代のエンジンの改良も行いました。
ちなみに桜井さんと市田さんが新型エンジンの設計を勝手に進めてる事に川本さんも気が付いていたのですが、まあ昔はオレも同じような事やったしな、という事で見逃しています。一方、桜井さんは桜井さんでエンジン部門の最高責任者の立場は変わってませんから、普段の仕事や会議で上司である川本さんとしょっちゅう顔を合わせながら何も言わずに押し通していたようです。後に桜井さんがこの間の川本さんの態度を「大人であった」と評してますが、この時代のホンダの強さはこういった自由度にあったようにも思います。
とりあえず旧型エンジンの改良も市田さんが担当し、間もなくエンジンテストの結果からピストンの剛性不足が信頼性欠如の原因である事を突き止めます。が、実験で原因が判明したものの理論上は十分な強度があるはずで何で壊れるのか全く判りませんでした。
悩んだ末に、頑丈にすれば何とかなるだろうと、ピストンの厚みを三割ほど増やしてしまいます。高速でぶん回すレース用エンジンでピストンを重くするのは非常識だったのですが、これがまた大当たりだったのでした。
理由は不明なれど(笑)、エンジンの信頼性が上がっただけでなく、燃費も良くなってしまったのです。さらにエンジンの耐久性が得られたのでターボの過給圧を上げる(空気と燃料を大量に押し込んで燃やす)事が可能になり、出力も上がりました。同時に問題だった冷却系の改良も行い、一定の性能向上には成功したのです。
ある意味、川本さんの「改良の余地あり」という考え方も正しかったのですが、それでも以前よりはマシという話であり、他のチームのエンジンに対して優位に立ったわけではありませんでした。
実際、1985年は第4戦のモナコまで改良型の川本さん世代エンジンが投入され続けたのですが、初戦ブラジルでいきなり二台ともリタイア、以後も全くいい所がなく、優勝どころか3位以上の表彰台入賞もできず、散々な成績で終わります。
一方、新型エンジンは開幕直前の1985年2月中に各部品が完成しながら組み上げ作業が停まってしまうという予想外の事態が発生、開発が遅れてました。これは現場監督だった整備担当のベテラン、土師(はじ)さんがエンジンの組み立てを拒否したためです。F-1番長 川本さんが許可していない新型エンジンを現場で勝手に作るわけにはいかない、というのがその理由でした。理屈はその通りなのですが、この辺りの事情は旧世代代表であった土師さんによる桜井さん率いる新世代メンバーへの反抗、という面が少なからずあったと思われます。
実は1985年を迎える前に桜井さんはF-1チームの人員一新を目論み、現場監督の土師さんも交代を予定していました。が、第二期の最初から、そして人員が足りずに最も厳しい時期のF-1&F-2チームを切り回して来た土師さんをいきなりチームから外す非情人事に川本さんが反対、これを思いとどまった、という経緯がありました。ところがここで桜井さんが恐れていた、古い世代との衝突が早くも発生してしまった、とも言えます。
このため最終的に桜井さんがエンジン部門の責任者として全責任を持つ、という事で人を集めてなんとか3月中旬に完成させ、ようやく月末から試験に入ります。1985年の開幕戦は4月7日のブラジルでしたからもはや間に合わないのは決定的でしたが、そのテストで奇跡のようなエンジンであることが判明したわけです。

少なからず運もあったものの、出力、信頼性、そして燃費まで全ての面で優秀だったホンダの新世代ターボエンジン。写真はターボ最後の年の1988年に投入されたRA168E型。
新世代ターボでは気筒を長くしたものの、片側3気筒ずつのV字の角度は80度、川本さん世代のエンジンと同じでした。よって高さ的にやや不利なはずなんですが(重心が高くなるからカーブで暴れる)、補器類の調整で全高を抑える工夫があったのか、それともその辺りは目をつぶったのか、エンジンの全高のデータが見つからんかったので不明です。
左右に飛び出してる楽器のホルンみたいな部品が排気タービン、いわゆるターボ過給機。シリンダ―頭部から出る強烈な排気によってタービン(羽根車)を回して吸気を圧縮、大量の空気を一気に気筒(シリンダー)に押し込む事で強力な出力を得ています。
V6
エンジンの左右に二つ、3気筒に一つのツインターボにしてるのは、小型タービンの羽根の方が軽くてすぐ回り反応がいいから。この辺りは「湾岸ミッドナイト」の読者の方なら、ああ、と思う所でしょう(笑)。
単に出力増強だけなら単発で大型のシングルタービンの方が有利なのですが、それだと内部の羽根が大きく重くなり、排気ガスを受けて過給機が回り始めるまで時間がかかり不利なのです。加速が命のレース用エンジンではアクセルを踏めばすぐにドカンと過給が効いて来る、いわゆる「アクセルのツキがいい」のが理想であり、レース用ターボ過給器の始祖、ルノ―が1980年代初めに軽いツインタービン設計を採用して以降、これが標準的な形態となりました(ただし2014年以降の新世代ターボはシングルタービンだが、これはあえて高出力化を避けてる面があると思われる)。
このホンダの新世代ターボエンジンは1985年に投入された最初のRA165Eから、常に改良され続けました。
その結果、1986年のRA166Eで初コンストラクターズチャンプを獲り、1987年のRA167Eでコンストラクターズ&ドライバーズの両タイトルを獲得、そしてマクラーレンにチームが変ったターボエンジン最後の年、1988年のRA168E
で年間16戦中15勝、勝率93.8%という驚異の記録を打ち立てるのです。
ちなみに第二世代のホンダエンジンは1+気筒数+西暦の最後の一桁、という命名になってます。最初の1はF-1の1。なのでRA168E
はF-1用6気筒、1988年型エンジン、という意味です。RAは第一期のところでも書いたようにRacing
Automobileの頭文字。最後のEは当然、エンジンのEです。第二期はエンジンのみの参戦ですから最後のEは要らない気もしますが、なにか理由があったんですかね。
話を1985年の新型エンジン開発に戻しましょう。
土師さんの「反乱」は以後も続き、なるべく早く新型の投入を望んでいた桜井さんと旧型エンジンにこだわっていた土師さんは対立する事になります。
5月19日の第4戦モナコまでは現場の意見を尊重して旧型エンジンで戦った桜井さんですが、エースのロズベルグが初戦から三戦連続リタイア、ようやく完走したモナコでもポイント圏外の8位、この年から加入して好調だったマンセルも5位が2回のみ、モナコでも7位に終わってもはや限界が見えたと考えます(「F-1地上の夢」のモナコで二台ともリタイアという記述は誤り)。
ちなみに新型エンジンがすでに実戦投入可能な段階に来てると川本さんが知ったのはその直前でした。モナコGPの前にマンセルが日本に来て新型のテストを行ってその性能に驚き、帰国後にウィリアムズチームのボス、フランク ウィリアムズに報告をしていたのです。驚いたフランクがそんなにいいエンジンがあるなら早く寄こせと川本さんに直接連絡を入れたため、それが川本さんに知られてしまったのでした。
すでにホンダの経営陣の一人として多忙だったF-1番長はこの事を全く知らず、現地に飛んで不在だった桜井さんの代わりに設計を行った市田さんを呼び出し、その辺りを確認します。気の毒な市田さんは、桜井さんの代わりにどんだけ怒られるんだろう、と覚悟を決めて出頭したようですが、意外にも「結果がよかったならそれでいいじゃないか」の一言で新型エンジンは承認されてしまうのです。
この辺りが川本さんの度量なのでしょうが、同時に1985年になっても全く勝てない現実に、本田宗一郎総司令官に次いでレースで勝ちたくて勝ちたくてしかたない彼が現実的な判断をした、という面もあったように思います。
ちなみにご本人は後に「必ず時代は変わって行くし、その時は常識とか調和とかとは無関係に力強くて若々しいものが勝って行くのはどうしようもない事」と述べており、この「新しい力と自分の旧式化」の理解において、本田宗一郎総司令官より川本さんの方が技術者としての器が上だった、と個人的には思っております。
こうした背景もあり、モナコGPから一カ月近く時間が空く6月16日の第5戦、カナダGPから新型エンジンの投入を桜井さんは決定したのです。ところがここで土師さん率いる現場チームが「新型エンジンではスタートする保証もできません」と反対を表明します。
当時は予選から新しいエンジンを次々と投入しており、8台は必要だった所に新型エンジンは3台しか現地に持ち込めて無かったので、無理もない意見ではありました(ただし3台というのは桜井さんの証言による。「F-1地上の夢」によると5台になってる)。そうは言っても、それではもう勝てないのも明白であり、新たな挑戦の拒否の先にあるのは衰退だけなのも事実でした。
このため予選までは旧エンジンで、本選のみ新型エンジンで走る事になります。その決勝では、ケケ・ロズベルグのターボ過給器が原因不明のトラブルを引き起こし8周目にピットイン、原因が判らないまま一度電源を切って再始動したら生き返る、という事態が生じます。これで順位は20位前後にまで落ちてしまうのですが、そこからロズベルグは怒涛の走りを見せ、スピンによるタイヤ損傷で予定外のピットインまでやりながら最後は4位まで順位を上げてしまいます。
レース後、ロズベルグはあのスピンが無ければ勝っていたレースだと桜井さんに述べており、タイムから逆算すれば確かにその通りだったのです。これでホンダチームは新型エンジンの性能に自信を深めます。ただしエンジンの供給は以後も不安定で、常に8台のエンジンが確保されたのは8月4日の第9戦のドイツ以降となりました。
そしてそのカナダ戦に続く第6戦、一週間後の6月23日のデトロイトGPでロズベルグが前戦の言葉通り1985年の、そして新型エンジンの初優勝を決めます。が、ここからホンダの強力すぎるエンジンにウィリアムズの車体のサスペンションが耐えきれない、という問題が出始め、以後はポールポジションは取れても勝てない、という悪循環に陥ってしまうのです。ここでホンダの、というか日本のF-1
第一号、1965年のRA‐271を設計した佐野さんが再びホンダのF-1の歴史に登場するのですが、その辺りはまた次回。
とりあえずデトロイトGPの優勝後も、土師さんが引き続き現場監督を務めていましたが、コンピュータを使ったエンジンの技術革新が進む中で投入された新しいスタッフと衝突を繰り返し、桜井さんとの対立も続きます。このため桜井さんが7月のイギリスGPで現場監督からの引退を勧告、後任にコンピュータやデータを使ってのセッティング強い、新世代の後藤治さんを内定します(後に桜井さんの後継者となる人)。
が、この段階でも土師さんがかたくなに引退を拒否、9月まではやらせてくれ、と桜井さんを押し切ってしまったようです。ここでは大先輩に遠慮した桜井さんですが、結局、その後も現場は混乱し続け、以後のテストにも支障が出る事態となりました。
結局、この問題はF-1番長 川本さんが自分の最後の仕事として解決する事になったようです。川本さんは8月に入ると現地チームが居るイギリスに飛び、自分もF-1からは一切手を引くから、一緒に引退するように土師さんを説得、これをもって土師さんは第10戦オーストリアGP前に現場を去る事になりました。
その後、オーストリアGPを訪れた川本さんは自らと土師さんのF-1引退を現場で宣言し、全権を桜井さんに移譲する事を明確にして身を引くのです。
その時、川本さんは私は長くレースに関わり過ぎてもはや柔軟性を失いつつある、と告白した後「これでは進歩がないから年寄りは退く」という言葉を残し、あれほど大好きだったF-1の現場を去りました。この辺りの行動は本田宗一郎総司令官の引退を思わせるものがあり、ホンダの伝統なのかもしれません。
同時にその後を継いだ桜井さん、そして当時のホンダ社長 久米さんと併せ、個人的にはこの時代のホンダの人材の厚みに戦慄すら感じます。この時期のホンダとソニーに経営陣に太平洋戦争やらせたら勝ってたんじゃないか、というくらいの人材が綺羅星のごとく集まってるのです。なので下手な三国志の英雄や、日本の戦国武将、そして幕末の志士より、この時代のソニーとホンダの人間を調べるのはよほど面白いですぜ。後にアップルのジョブスが参考にした日本企業の黄金期ですからね。
だからこそ私はこの異常な旅行記を書いてるのだ、とも言えます。