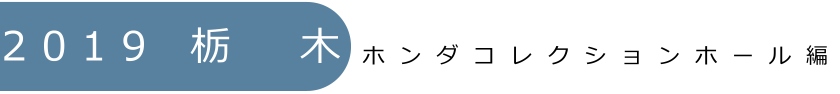
話をヨーロッパF-2に戻しましょう。
参戦3年目、1982年は川本さんの意向で2チーム体制となり、そのために設立されたのがスピリット チームです。
ホンダによる100%出資で、ライバルだったマーチ、トルーマンのチームから主要スタッフとドライバー(後のF-1ドライバー、ブーツェンとヨハンソン)を引き抜く、という豪快な手法で設立されたものでした。ラルトチームの運営に不満だった川本さんの判断によるもので、複数のチームで競争させればさらに勝てるはずだ、と考えた結果でした。ちなみにこの時のライバルチームからの引き抜きがあまりにあっさり成功したため、なんだコイツら義理とか忠誠心とかないのか、と川本さんはレース業界のシビアな人事に驚いたそうな。
が、この2チーム化はうまく行きませんでした。
原因は大きく分けて二つ。一つは両者が競い合うほど熱心にレースを展開しなかった事、つまり勝ちたいという情熱に欠けるチームだった事。ドライバーはともかく、チーム運営のスタッフは決してレースに情熱を傾けてるとは言い難く、それどころか新たに設立したスピリットのチームでは予算をレース以外に横流ししてる疑惑さえ出て来ます。さらにラルトはこの年のシャシー開発が遅れまくり、結局、一勝もできずに終わりました。この辺りがスピリットをF-1のテストチームとして翌1983年に移行させ年度途中で解散、ラルトも1984年のF-2終了をもって関係打ち切りとした原因でしょう。
二つの目の敗因はタイヤでした。前年からヨーロッパF-2に参戦していた日本のブリヂストンタイヤを両チームで採用してたのですが、予選では十分速いものの、本選ではすぐにタレてまってグリップが無くなる、という症状に悩まされるのです。このため開幕からミシュランのタイヤを履いたチームに大きく差を付けられてしまいます。この点に関しては後に川本さんが、両チームをブリヂストンにしてしまったのは自分のミスだ、と述べています。
こうして全13戦の前半6戦ですでに大きく出遅れました。2位には何度かなったものの、優勝はスピリットのブーツェンによる1勝のみ、という結果に終わります。その後、スピリットはいろいろセッティングを変え、後半でブーツェンがなんとか2勝するのですが、このブーツェンによる3勝がこの年の勝利の全てとなりました(全2勝とする「F-1
走る地上の夢」の記述は間違いなので注意)。結局、2チーム4台で参戦して、前年より少ない勝利数しか上げられなかったのです(前年はサックスウェルが数戦骨折で欠場してるから、実際はさらに少ない出走数である)。
ただしブリヂストン側に言わせると、キチンと推薦したタイヤを使用せず、グリップはいいけどすぐにタレてしまうタイヤをチームが選んでいた、という事になるらしいですが…
こうしてこの1982年はマーチのワークスチームに敗北、フル参戦した年では唯一、チャンプを逃してしまいます。
この結果にがっかりしたF-1番長の川本さんでしたが、すでにF-2を3シーズン走った事で(1980年度は4レースしか走って無いので事実上は2シーズン半だが)F-1への移行を決断、1983年の参戦を目指して動き始めました。
ただしホンダに取って不運だったのは、これが市販車のラインナップを大幅に更新する時期に重なってしまった事でした。
ホンダ初のV型6気筒エンジン搭載の高級車レジェンド、そして4気筒DOHCエンジン搭載の若者向けのスポーティーな新型車、インテグラの発売が1985年に予定され、両車は新型エンジンの搭載が決定してました。さらに同年のアコードのモデルチェンジでも一部の車両に新型の2000㏄エンジン搭載が予定されていたのです。これらの新開発エンジンの開発でエンジン部門は手一杯となりつつありました。
このためレーシングエンジン部門の設計担当だった市田さんがレジェンドのエンジン開発チームの責任者に引き抜かれ(というか川本さん自らが任命したのだが)、F-1参戦直後のエンジン設計担当は、F-1番長 川本さんと例のF-2エンジン設計合宿に巻き込まれた若い北元徹さんの二人が中心に回してゆく事になります。とりあえずこの辺りのF-1参戦前後の状況についてはまた次回、詳しく見て行きましょう。

1985年に発売となったインテグラ。これも四輪車の記事では無視した車ですが結構カッコよく、この時期から1990年代初頭までがホンダデザインの絶頂期ではないかと思います。
実際はクイント インテグラで、クイントの二代目となるのですが、クイントは全然売れなかった誰も知らないホンダ車の一つですし(発売時に生きてた私ですら長年知らなかったし、実は未だに実車を見たことが無い)、実際、以後はインテグラの名で売られて行きますので、ここでは初代インテグラとしておきます。エンジンから何から、完全新型ですし。
前回見た、市田さんをレーシングチームから連れ去ってしまったレジェンドとこの車が同年発売、しかも両方とも新型エンジン搭載、という事でこの時期のホンダのエンジンチームには全く余裕が無かったのでした。

さらに同じ1985年にモデルチェンジとなった新型アコードでも一部が新型エンジンだったため、その混乱に拍車を掛けます。21世紀の現在から見ると、おどろくほどパカスカと新型エンジンが投入されてたいい時代、とも言えますが。
すでに研究所副社長となっていた川本さんですが、自分の縄張りとも言えるエンジン部門にレース活動で迷惑をかける事を避けるため、この時期、ほとんどの人材を市販車に廻してしまい、この結果、F-1は参戦開始の1983年から翌84年まで今一つな結果に終始します。が、この新型エンジン攻勢が終わると川本さんの跡を継いでエンジン部門の責任者になっていた桜井さんがホンダの「総監督」として投入され、同時に市田さんがレースエンジン部門に復活、ホンダエンジン無敵伝説を創り上げることになるのです。
F-2に話を戻しましょう。
1983年はスピリットをF-1シャシー開発に廻し、F-2は再びラルトの1チーム体制となりました(出走は新加入のパーマーと残留したサックスウェルの2台体制)。タイヤもミシュランにし、ラルトに対してもこの年にチャンプを獲れなければエンジン供給も資金援助も打ち切る、と宣言して臨むのです。
が、この年も当初は勝てず、全12戦の内、前半の6戦を終えて2勝、2位3回という結果に終わってました。悪くはないように見えますが、川本さんは完全に不満で、レースチームの事実上の責任者となっていた宮本さんを自宅に呼び出します。そしてそれまで常に日本国内で仕事をしていた宮本さんに対し、現場を見ろ、勝つまで日本に帰って来るな、と言い渡してヨーロッパに送り出してしまうのです。ああ、ホンダですね(笑)。
ちなみにこの段階で、川本さんはホンダ本社の常務にも就任してましたから、多忙で動けない自分と思ったように勝てないチームとにいら立っていたのかもしれません。
こうして6月12日の第7戦、スペイン戦の直前から現地入りした宮本さんですが、現地監督のメカニックのボス、土師さんに会ってみると、どうやら問題解決のメドが立っていることを知ります。この年からミシュランタイヤに切り替えていたのですが、ミシュランの提供するデータがBMWエンジンに沿ったものだったため、より高馬力でタイヤに負担の大きいホンダエンジンにはあっておらず、タイヤ選択に問題がある事が徐々に明らかになって来ていたのです。
このため、スペイン戦以降はタイヤ戦略を変え、ミシュランが推薦するタイヤではなく、グリップはやや落ちるものの、より硬くて長時間タレないタイヤを選択する事にしたのです。
さらにミシュランはフランスの会社ですから当然頭の中はおめでたいラテン系で、フランス語しか話せないスタッフしか送り込んでませんでした。よってイギリスのチームであるラルト、そして日本のエンジンメーカーで、国際語である英語しか判らないホンダとコミュニケーションが取れてませんでした。このため、まともにタイヤのデータを解析することすら困難だったのです。これを知って驚いた宮本さんがミシュランと交渉、ようやく英語の分かるスタッフを派遣してもらいました。
この結果、第7戦のスペイン、ハラマサーキットでは優勝は逃したものの2位、3位となり、次の第8戦、6月25日に行われたイギリス、ドニントンパークのレースでパーマーが優勝、そして以後は最終戦の第12戦まで怒涛の5連勝を決め、全6勝でチャンピオンを獲得する事になります。ちなみに同僚のサックスウェル、翌84年のチャンプも1勝してるので、この年のホンダは12戦7勝した事になりました。
その怒涛の連勝が始まった直後の7月のイギリスGPで、ホンダは15年ぶりのF-1復帰を果たすのですが、この辺りはまた次回。
ちなみに勝つまで帰って来るなと言われて日本を追い出された宮本さんは、実際に1983年のF-2チャンプを獲るまで日本には帰れんだろう、と思っていたのとF-1、F-2のどちらもホンダのチームは同じメンバーで回してたので死ぬほど忙しく、現地に留まり続けます。
ところが、第9戦、イタリアでのレースの前に突然、妙にやさしい声のF-1番長 川本さんの電話が入りました。実は以前に受けた健康診断で、宮本さんの心電図に異常があったのですが、これを川本さんが発見して驚き、もう日本に帰って来るように、という内容でした。このため、宮本さんはF-1デビュー戦が終わった7月24日のF-2
第9戦レースに立ち会うと、日本に帰国、さらにストレスの多いレース担当を外されてしまいます。
以後、多忙な川本さん自らがレース全体を見て、現地では土師さんが一人でF-1もF-2も面倒を見る、という無茶苦茶な体制でこの年は終わるのです。この状況でよくF-2
の後半戦で5連勝もしたな、とも思います。
これが解決されるのはホンダの新車ラッシュが終わった1984年秋、桜井さんが川本さんの役割を引き継いでからでした。

そしてF-2最後の年、1984年も再びホンダがチャンプを獲ります。その84年のラルトの車、RH-64-84。
サスペンションの取り付け部とか、F-1に比べるといろいろ簡易な構造なのも見て置いて下さい。
ちなみに1984年の最後の三戦だけはミシュランではなく、試験的にブリヂストンタイヤに戻して走ったのですが、2勝&3位1回と満足のゆく結果がでてます。ブリヂストンタイヤが進化したのか、ここまで強いマシンだともはやタイヤなんてどうでもいいのか、その辺りはよく判りませんが。
コレクションホールに展示してるあるのはゼッケン1番、この年のチャンプとなったサックスウェルの車。この年のホンダエンジンは350馬力出ていたとされ、
開幕6連勝、最終的には11戦9勝という圧勝で終わります。ちなみにドライバーの頭上に吸気口がなく車高が低いため、なんだかF-1のターボカーみたいですが、当然、ターボ車ではありませぬ。エンジン上部がむき出しで、そこから直接、吸気管が空気を吸い込んでる単純な自然吸気エンジンです。運転席の後ろ、なぜか展示では銀の蓋が乗っかっている所の下エンジンがあり、吸気筒がそこから上向きに突き出ています。
ちなみに日本でF-1中継が始まった1987年以降はターボ車が昔ながらの低い車体なのに対し、自然吸気のNA車はドライバーの頭の上に吸気口がある車高の高いスタイルだったため、両者の識別点としてドライバー席から後ろの車高を上げてる資料をたまに見ますが誤りです。1980年代前半まで、頭の上に吸気口の無い、こういった低いスタイルの自然吸気車はF-1でも普通でした。

1989年の以降の自然吸気時代のF-1では、胴体後部のエンジン上のカウルをドライバーの頭の上まで引き上げ、ここにエンジン用空気取り入れ口を置いたため、これが自然吸気エンジンF-1の標準デザインと思われてる事があります。が、この構造は自然吸気エンジンのメカニズムとは無関係です(有利になる点がいくつかあるが、それはターボでも変わらない)。実際、1986年以前の車では、自然吸気でもターボ車と同じ低い車高の構造で、こんなものは付いてませんでした。逆に2014年から復帰したターボエンジンF-1にも、こういった頭上空気取り入れ口があります。なので上に吸気口があるかどうか、車高の問題はターボかNAかという点に関しては無関係なのです。
話をヨーロッパF-2に戻しましょう。
1984年においてホンダに勝てないBMWがF-2エンジン生産から撤退する事を宣言してしまったため、ラルト以外は全てBMWエンジンだったF-2というカテゴリは消滅をよぎなくされます。よって以後、翌1985年からはF-1のエンジンレギュレーション変更で使われなくなるフォードコスワース 3000㏄エンジンを流用したF-3000へと発展解消される事になるわけです(1985年までF-1のNAエンジンは3000㏄だったのでこの一年のみはF-1と同じ排気量だった。ただし現実にはF-1はほとんどが大馬力ターボ車であり、NAで走ってる車はほぼ無く、この結果、両者はキチンと差別化された)。
それに伴い、F-1への注力を考えていたホンダはこのカテゴリから撤退、F-3000
でも残留したラルトとは決別します。ただし、既に見たように日本では1986年までF-2が存在したので、そちらへのエンジン供給は続けてました。
この点に関して、ホンダは勝ち過ぎだ、やり過ぎだ、という批判がヨーロッパ方面で起こったとされます。が、負けて逃げ出すヤツが問題なので、それなら勝負の場に出てくるなこのマヌケ、という所でございますな。この点、ヨーロッパ方面のモータースポーツ関係者の頭が弱いだけ、と考えて問題ないでしょう。ちなみにこの点に関してF-1番長 川本さんは「レースの世界でバランスだ強調だとかこきやがっても、そんな事知らねえとぼくは思ってますよ」と述べてます。正論でしょう。
と言った感じでホンダの第二期F-2は見事な戦績を残して終わりを告げます。次回から、いよいよ第二期F-1を見て行きましょう。