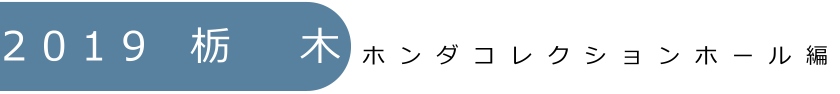
さて、いよいよホンダF-1第一期の最終年、1968年に入ります。
1967年に発売された軽自動車N360の大ヒットにより経営的には一息ついたものの、この年が始まる前からホンダの置かれた状況はすでにF-1活動の継続を許さない事が明らかになっていました。念願だった普通乗用車への進出、そしてこの時期にホンダが本格的に取り組み始めた低公害車対策エンジンの開発のため予算も人員も不足、レースなんてやってる場合ではない、という状況に追い込まれつつあったのは誰の目にも明らかだったのです。
ホンダの経営危機を救った大ヒット作、N360は1967年の登場。そして次に発売を予定してる普通乗用車(後のH1300)の開発がより大掛かりになるのは明らかでした。さらに1966年ごろから日米で自動車の排気ガスに関する規制、公害対策の法案が成立、ホンダは低公害エンジンの開発にも人員を割かれてしまいます(ただしCVCCの開発が始まるのはマスキー法が成立した1970年からでこの段階はあくまで基礎研究)。
このため、無敵と言っていい大活躍を見せた二輪の世界GPからは1967年に撤退、ほぼ全戦全勝に近い成績を収めていたF-2も1966年までで撤退してます。最後に残ったのがF-1だったのですが、これは唯一世界チャンプを獲ってないF-1でも勝ちたいという本田宗一郎総司令官の執念と、「人生賭けてレースやっちゃった」中村監督の予算、人員配置の工夫によるものでした。この二人の情熱が最後の一年、1968年の挑戦を可能にしたと言っていいでしょう。
が、現場ではなく後方で技術的な興味を中心にF-1を見ていた本田宗一郎総司令官と、現場に居てF-1の現実をイヤと言うほど見せつけられ、勝つために必要な現実的な選択を優先した中村監督の間の溝は、この年に至って最大のヤマ場を迎えてしまうのです。そして両者の対立から大混乱の内に最後の年も終わってしまう事になります。
これは空冷エンジンの採用とホンダ製の車体にこだわった本田宗一郎総司令官と、水冷エンジンと車体は技術を持ってるローラ社の開発という現実的な選択をした中村監督、という形で表面化します。このため、ホンダはただでさえ少なくなっていた人材と予算を空冷、水冷の二つの車に分散投資する形になり、不完全燃焼のまま最後の一年を過ごす事になるのです。
さて、その第一期最終年の動きを見て行く前に、ホンダのF-1第一期を公平な視点で見るため、その出走回数とリタイア回数を見て行きましょう。ホンダは5年間で2勝しており、これは無名に近い自動車メーカーとしては奇跡に近い事でした。ただし後に中村監督が語った様に、まともにやってれば最後の1968年はチャンプを狙えた、という話はホントか、というのを考えて見ましょう。

各年度におけるマシンと、その出走回数、そしてリタイア回数の一覧です。+記号でつなげた数字は二年に渡って参戦した場合の初年と翌年の出走数です。最後の1968年はRA301で全戦走ったほかに、空冷のRA302
が一度だけ出走してるので二台併記となります。
さて、これを見るとホンダのリタイア回数が異常に多いのが判るでしょうか。そしてそのリタイア率は5年間を通じて全く改善されてないのです。
ちなみに5年間でホンダは全36戦戦い、その内リタイアしたのは21戦(二台出走で一台だけリタイアも含む。1965年のリタイア率が二つあるのはギンザ―が60%、バックナムが100%なため)、そのリタイア率は実に58.3%、出走したレースの半分以上でリタイアしています。すなわちまともに走ったレースは全体の半分も無いのです。これが5年間続いたのだから、あまり褒められたものではありませぬ。
参考までに中村さんが本気でチャンプを狙いに行った最終年、1968年にドライバーズ&コンストラクターの両部門を制したロータスフォードのエース、グラハム・ヒルは12戦全戦走ってリタイアは4回、すなわちリタイア率は33.3%でありホンダのエース、サーティスの半分となっています。
ホンダがリタイア率33.3%以下だったのは二回だけ、どちらも急造マシンだったRA272改と、RA300で数戦走った時のみで、年間を通しては一度もありません。このように、そもそも完走すらできないのでは、チャンプを獲る以前の話でして、ホンダの努力と活躍は認めるところですが、やはりまだまだ実力不足であった、と言わざるを得ない所でしょう。
よって、もしこのまま参戦を続けてもおそらくチャンプは獲れなかったろうな、というのが公平な評価、という感じではないかと思います。特にこの年以降はあの傑作エンジン、軽量で高馬力のフォード・コスワースDFVの全盛期を迎えますから、より困難だったはずです。そういった事を念頭に置いたうえで、混沌の1968年を見て行きましょう。