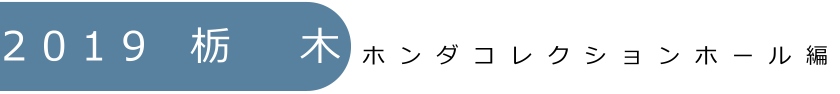

正面から。ゼッケン3番はブラバムのマシンです。鼻面にホンダの赤いエンブレムが付いてるのにも注目。
ホンダが担当したのはエンジンだけで、シャシー(車体)はブラバム・レーシングによるものです。彼らはその販売も行っており、当時のF-2には多くのチームがブラバムのシャシーで参戦してました。ただし、最新型は自分たちだけで使い、販売してたのは前年の旧型シャシーでしたが。
このBT18は基本に忠実な堅実な作りで、スプリングが外部むき出しのダブルウィッシュボーン・サスペンション、リア・ミッドエンジン、鋼管による中空骨組み構造(スペースフレーム)という設計になっています。デザイナーは後に1980年代のホンダF-2にも深く関わる事になるトーラナック(Ron
Tauranac)。でもってなにせ1000㏄ですから、タイヤは市販車のような太さであり、ラジアルタイヤですらないのです。運転席後部の逆Uの字形の鉄棒は背もたれではなく、事故で車体がひっくり返った時、ドライバーが押しつぶされないようにするための支柱。
このマシンが活躍した1966年のF-2はまさにホンダエンジンの年だったのですが、その前年、初参戦の1965年は逆に悲惨の一言でした。
ブラバムと契約した直後、1964年秋から久米さんと川本さんは1000㏄のF-2用エンジンの開発に取り掛かりました。彼らはとりあえず1964年の1000㏄ F-2チャンピオンでもあった、ブラバム本人が使っていたコスワース SCAエンジンのデータを性能目標にします。
1964年のF-2、最初の1000㏄ F-2は事実上コスワースエンジンの独壇場であり1970年代のF-1みたいな世界だったので、このエンジンに勝てれば自動的にチャンピオンを獲れる、と考えたのだと思われます。ちなみに後に1960年代後半から10年以上に渡ってF-1を事実上支配してしまうコスワースですが、このF-2用のエンジンが、彼らが初めて本格的に制作したレース用エンジンでした(1964年のF-2にはコスワース以外だとルノーエンジンが数台いたのみで、さらにその戦果は散々だった。ちなみに常に独自路線を行くフェラーリはF-2には参戦していない)。
そのコスワース SCAエンジンはコスワース製ですから当然、元はフォード車用のエンジンで、アメリカからは半独立した状態だったイギリス・フォード(アメリカ フォードが断った第二次大戦世代の航空エンジン、マーリンの大量生産を実現してしまった会社)が1962年に発売したフォード・コーティナ(Cortina)用1200㏄エンジンの排気量を落したものでした。市販車用エンジンをレース用にチューンしたエンジンであり、9000rpmで115hpを出しています。ちなみに市販車用の直列エンジンが元なので、メチャクチャ背の高いエンジンとなっており(この段階ではドライサンプも非採用)、よくこれをレースに使ったな、と思います。
ちなみに「F-1地上の夢」によると久米さんが当初設計していた1000㏄エンジンをジャック・ブラバムが見て声をかけた、とされてますが、この時代のホンダに1000㏄エンジンは存在しません(というかホンダが市販の四輪用1000㏄エンジンを造った事は無い)。よって、これは1966年に発売されるS800
用のエンジンだったのではないかと思われます。
実際、1965年のF-2
用ホンダエンジンのレース時の登録名はS800と記載されており、直列4気筒のDOHC(ただしS800の2バルブに対して4バルブ)でしたから、これはS800エンジンをボアアップして1000㏄エンジンとしたものだと思われます(正確には994㏄)。
ただし、それは1965年型だけで翌1966年に投入された新型は完全新設計エンジンでした。それでもなぜか現地での登録名称はホンダS800エンジン
のままなので、ちょっと混乱しますが…
さらにちなみにホンダでは1965年のエンジンをRA300E、1966年型の新設計F-2用エンジンをRA302E
と呼んでいたようですが、後者はあの1968年の空冷F-1用エンジンと同じ名で混乱しやすいので注意。当然、こっちが先の登場です。なんでこんなヤヤコシイ命名したんでしょう…。RA301が欠番の理由もよく判りません。
でもって久米さんと川本さんコンビは、同年、1964年におけるホンダF-1チームの大苦戦を知っていたものの、こちらもまだ二輪GPの成功から抜け切れておらず、とにかく馬力を出す、という事だけを念頭に置いてその設計を始めました。もっとも効果的なのは既に見たように多気筒化でしたが、残念ながら1000㏄のF-2では規定により直列4気筒以外の使用が禁止されていたのです。
となるともう一つの対策、とにかく大量の混合気を気筒内に取り込んで盛大に燃やし、ピストンを押し下げる圧力を上げる、という方針が採用されます。幸いホンダには当時の世界最先端ともいえる小排気量用のDOHC4バルブ(2バルブに対して吸排気口が倍なのだからより大量に混合気を取り込み、そして燃焼済みガスを排出できる)の技術がありましたから、その対策は容易でした。

ホンダのSシリーズ、S500、S600、S800に積まれていたASエンジン。
1965年型のF-2エンジンはその排気量アップと2バルブのDOHCを4バルブ化、さらにキャブレターの代わりに燃料噴射装置を搭載したものだったと思われます。となると、ホンダとしては市販のS1000も可能だったのではないの?という疑問も出て来ますが、ここではそこまで脱線しません(実際、1970年ごろの雑誌などにそういった噂が出た事があったらしい)。ちなみ無敵無双となった1966年型エンジンは完全に新設計で、ぼぼ別モノになっておりかなり形状が異なります。こちらもホンダコレクションホールに展示がある、という話なんですが私は見つける事ができませんでした…
とりあえず原型となるエンジンはすでに設計が終わっていたので1964年の最後の二か月で彼らは試作までを終えてしまします。そしてさっそくエンジンのテストを行ったところ、あっさり130馬力を記録、とにかく馬力が出ればいいと考えていた彼らは狂喜します(最終的には1966年に1万回転で150馬力まで到達する)。
ところが翌1965年1月にブラバムが自社のシャシーを持って来日、鈴鹿でエンジンテストを行うと(その前に1964年中にホンダの用意したシャシーで一度走ったという話もあるが詳細不明)、彼らは二度のF-1チャンプを獲った男から(この段階ではまだ三度目のチャンプを獲って無い)「速いけど、このエンジンはレースには使えない」と告げられショックを受けます。
結局、ホンダのF-1エンジンが抱えていたのと全く同じ問題、高回転時にはトルクも馬力も出て素晴らしい性能を見せるものの、一度回転が落ちてしまうとそこからの回復が困難である、つまり減速などにより一度エンジン回転数を落とすと、自慢の最高馬力が出るまで非常に時間がかかる、というエンジンになってしまっていたのです。当然、その間に競争相手ははるか先を走って行ってしまいますから、後からどんだけ馬力が出ても、もはや追いつけません。
ただし同時にブラバムはホンダのエンジンに衝撃も受けており、1965年(つまり連勝開始前の段階)の「Motor
Racing」に寄稿した記事の中では
「とても滑らかに走り、印象的なエンジン音であり通常のF-2の倍の爆音が出ていた(It runs
smoothly and sounds very impressive, makes twice as much noise as the
average F2 engine)」「6000~9500rpmと素晴らしく広い出力域を持ち、この結果とても容易に車を運転できる(There is
useful power from 6000-9500 rpm, which is a nice wide band and makes the
car comparatively easy to
drive)」と、キチンと高回転域まで持って行ければ十分な性能を持つことを認めていました。この結果、とりあえずホンダが2名のメカニック(1名は設計担当だった久米さん)を派遣する事を条件に、同年からの採用を決定するのです。
ただしエンジンが大きすぎてブラバムのF-2シャシーに搭載が困難だったため、その小型化も要望したと同じ記事内で触れています。最終的になんとか車体に積めてギアボックスもちゃんと付く(ホンダ製ではなくイギリスのヒューランド(Hewland)6速ギアボックスを使用していた。ホントにエンジンしか造ってないのだ)大きさに調整されたようです。
ブラバムがその可能性は認めたものの、同時に実戦では使えないと指摘された久米さんは、すぐに改良に取り組み、とりあえず燃料周りの見直しが行われます。コスワースがツインキャブレターだったのでホンダではその上を行く四連キャブレターを採用していたのですが、これを同年のF-1エンジン用に開発されたホンダ製燃料噴射装置(カタカナ英語スキーの皆さんが言う所のインジェクション システム)に変更、より安定して混合気を作り出せるようにしました。当時のホンダの燃料噴射装置は極めてお粗末なものだったのですが、それでもキャブレターよりはマシ、という事での採用だったようです。
ただし、この燃料噴射装置のお粗末さから、最適なガソリン濃度が出ずに混合気は薄くなりがちで、その結果、燃料によるシリンダー内の冷却効果が薄れるいという熱問題が発生、この年は最後までこの問題に悩まされ続ける事になるのですが。
その後、1965年のF-2の開幕に備えて三月には久米さんがイギリスに渡り、ブラバムのシャシーにホンダ エンジンを搭載してシルバーストーンサーキットでテストを行います。ちなみにこれはシーズン開幕二日前、三月十八日の事であり、例によってホンダのテストはいつもギリギリ、という状況だったのです。この日、同時にテストしたコスワースのエンジンよりいいタイムを記録し、関係者を喜ばすのですが、テスト後半になるとホンダエンジンはまともに動かなくなり、最後はとうとう完全に止まってしまい、テストは中断となりました。
テスト終了後にブラバムのガレージでエンジンを開けてみたところ、中は熱で破損、完全に破壊された状態であり、これを見た久米さんは愕然とするのです。こうなったら熱対策を含めて、一から造り直さないとレースを完走する事すらできない、というのが明らかだったからですが、すでにシーズン開幕は僅か二日後に迫っていました。どうしようもない、という状況の中、幸か不幸か第一戦は大雨で中止になってしまいます。
ただしレース前の試験走行だけは行われており、ブラバムのタイムはトップから9秒遅れという、二度のF-1世界チャンプであり前年のF-2チャンプでもある彼としては屈辱的なものでした。
次の第二戦は4月3日に開催され、ここで初めてホンダは予選、本選を経験するのですが予選ではトップから7.2秒遅れの19番手(F-1 地上の夢に書かれている「全車中最下位」は間違い。後ろから三番目で当時は横に最大四台並べてスタートだったので最後列スタートだっただけ)でした。そしてレース本番ではやはり熱によりピストンが吹き抜けエンジンを破損、リタイアとなりました。この時、ブラバムから「なんだこのエンジンは」と言われた久米さんは恥ずかしさで赤面するしかなかったとされます。ちなみに予選があった4月2日はブラバムの誕生日だったため、地元の新聞で“最高の誕生日”と茶化されていたので、本人も機嫌が悪かったようですが。
それでもブラバムは我慢してホンダエンジンを使い続けるのですが、その後の二戦もエンジンのトラブルでリタイアとなり、最後は愛想をつかされる形でホンダエンジンの使用は中止になってしまいます。最初の三戦を走っただけでホンダのF-2エンジンはダメ出しをされてしまったのです。このため現地に居た久米さんは絶望のあまり、半ノイローゼのような状態になってしまいました。
ブラバムからエンジン搭載を拒否されたのが4月25日のフランスのレースでしたが、その後も久米さんはイギリスに留まりました。その間にコスワースのエンジンの研究などを続け、日本に残して設計現場を担当していた川本さんとその改良を続けます。この間に前年のF-1監督、中村さんが様子を見に来たフランスでのエンジンテスト中に大ケンカをやってしまい、さらにすでに述べたようにこの年の7月10日に開催されたF-1イギリスグランプリで臨時監督を務めるためにやって来た河島さんとも衝突、本人も半ば自暴自棄になってしまったようです。
が、それでも立ち直っちゃうのがこの久米さんでした。後に空冷エンジン地獄を乗り越え(二度失踪するけど)、CVCCエンジンとシビックを乗り越え、最終的にはホンダの社長にまでなってしまう人ですからね。
この時はケンカの後に河島さんからイギリスに居れば本田宗一郎総司令官からの横やりは入らないから、現地でやりたいようにやってしまえ、と言われ、その通りにする事を決心します。そして秋に帰国するまでに徹底的に改良を進め、その結果、翌年l1966年に彼は歴史を造ってしまう事になるのです。
一方、コスワースエンジンに乗り換えたブラバムもその後パッとせず、この後かろうじて一勝したものの、後は三位に二回入賞するのが精一杯でした。結局この年はチャンプから大差をつけられ年間総合順位は三位に終わる事になります。
そして第15戦、最終戦の一つ前のフランスのレースで、ブラバムはようやくホンダの改良に満足し、そのエンジンの搭載を認めます。この時のホンダエンジンは見事に完走し、優勝は逃したものの二位を獲得、しかも一位とはわずか0.6秒差というデッドヒートの末の二位でした。この年のブラバムはコスワースエンジンでも一勝しかできておらず、ブラバム製シャシーのBT-16に問題があった可能性が高い事を考えると、どうやら十分な戦闘力を持ったエンジンが完成したと言っていい事を意味します。
その後、最終戦、第16戦はホンダは参加せず、久米さんたちは帰国してしまうのですが、翌年に大いに期待できる1965年の締めくくりだったと言えるでしょう。実際、翌年の1966年にホンダエンジンは歴史に残る圧勝を記録する事になるのです。
ちなみにこれはホンダの1500㏄ F-1が初勝利を挙げるメキシコGPの直前であり、このためF-1初勝利の陰に隠れてしまって誰も覚えてない、という幻の記録になってしまうのですが、その持つ意味は重大でした。ホンダの四輪開発チームのエンジンが初めて表彰台に上がったレースでもあるからです。
余談ですがF-1番長にして四代目社長である川本さんは「これでF-1(チーム)を出し抜いたぞと思っていたのに、最後の最後で勝たれちゃったので、こっちとしてはちょっとがっかりでしたね」と、いかにも全盛期のホンダの人間らしい発言を残してます(笑)。これが他のメーカーや1990年代以降のホンダだと「F-1チームも勝ててうれしかったです。おめでとう」的な優等生的発言になっちゃうんでしょうが、そんなノンキな連中がレースで勝つのは奇跡に近いと思われます。死ぬ気で勝ちたいとと思う連中が生き残るのが勝負の世界でしょう。
話を戻します。
翌1966年の新型エンジン設計において、久米さんが意識したのが三戦連続でリタイアした後、ブラバム本人とデザイナーでチーム共同創設者だったトーラナックから指摘された問題点でした(ブラバムのマシン名にBTとあるのは二人の頭文字を取ったから。ちなみにトーラナックがデザインしたF-1マシン、BT20でブラバムは1966年に三度目のF-1チャンプとなる。そして第二期ホンダF-1の先駆けとなる1980年のラルト ホンダF-2の誕生にもトーラナックは関係してくる)。
ブラバムから指摘されたのは既に述べた最高馬力が出る回転数までキレイに加速する必要性、そしてエンジンオイルの循環の問題でした。なぜそんなにエンジンが壊れ、熱の問題を抱え続ける事になったのか、という点の一つのヒントがこのオイル循環問題だったのです。
そしてトーラナックから指摘されたのはエンジンの重心が高すぎる、という点でした。先に述べたようにそもそも大きすぎた上にシリンダーヘッド部が重くて重心が高く、コーナーを曲がる時の車の挙動を乱してしまっていたのです。ホンダはエンジン大好き本田宗一郎総司令率いるエンジンが命の会社ですから、久米さんはシャシーへの影響など考えた事も無く、強い衝撃を受けたとされます。
最初の問題点、一度回転が落ちたエンジンをいかに反応よく高回転まで繋ぐか、というのは燃焼室の形状、そして燃料噴射装置の改良(基本は高圧化する)などの問題を一つずつ潰して行く事で解決されました。
中でも最大の変更となったのは燃焼室とピストンの形状変更でした。1000㏄で四気筒は不変ですからシリンダー(筒)の容積はそのままです。ただし、それまでのホンダの四輪エンジンはバイクと同じスモール・ボア(小直径)でロング・ストローク(大全長)、つまり細くて縦長のシリンダー(筒)だったのを久米さんは全く逆のビッグ・ボア(大直径)のショート・ストローク(小全長)、横幅の広い短シリンダー(筒)へと180度方向転換したのです(両者の掛け算だから排気量は変わらない)。
これが大成功だっため、以後、この設計がホンダの四輪レース用エンジンの基本となります(ただし後に1980年代末の排気タービン過給F-1では再び逆転、スモール・ボア、ロング・ストロークに改良されてからホンダの圧勝が始まる。この辺りは興味深いところ)。
これは主にエンジンの振動対策(つまり壊れにくくする)と高回転化対策だったと久米さんは証言してますが、そのショートストローク化のアドバイスをくれたのはブラバム本人だったとか。この人もただのドライバーじゃないんですよね。
ちなみにエンジンの振動対策と言うとドライバーが我慢すればいいじゃん、くらいに思うかもしれませんがそんな甘いものではありませぬ。1965年のエンジンでは振動が原因で燃料ポンプがバルブからの共振を起して停まってしまい、エンジンが止まる事態が生じていた事が判明していたのです。さらにスロットルワイア―が切れたり(これも当然エンジンは止まる)、カムシャフトが破断するという事故も起きており、これらもどうも振動が原因だ、と考えられました。
さらにエンジンの小型化、重心の中心点への集中がはかられます。次回に見るオイルの流れのように、加速による慣性の変化から生じる力はエンジンにロクな影響を及ばさないのですが、それらは主にブレーキングによる減速と回転運動で生じます。レースではブレーキングと回転運動はほぼ同時にやって来るので、生じる力は回転の力、すなわちトルクであり、これを小さくするには半径を小さくすればいい、すなわちエンジンを小型化すればいい、という事に久米さんは気が付くのです。
この点、自ら学校の勉強が嫌いだったと証言してる久米さんは「慣性力」というエセ科学のような言葉で説明してしまってますが、要するに慣性状態からの加速(等速運動からの停止、またはその逆、そして直進から曲がる事)で発生する力を意味しています。彼の発言を見ると理屈より体験と直感でこれを見抜いてますから、どうもこの辺り、本田宗一郎総司令の技術者としてのDNAを最も強く持っていたのはこの人だったような気がしますね。
ちなみに1966年型のエンジンは久米さんが考えて設計し、川本さんがそれを手伝い、最後の最後にシリンダヘッドの設計にポカミスが発見された時の改修を新村さんが手伝ったので、ある意味ホンダエンジンチームオールスターという設計となりました。ついでに二輪エンジンの無敵化に貢献した吸排気の理論家、八木さんも参加してるのですが、どうも久米さんの証言を見る限り、あまり貢献したというワケでは無いようです(先に見たシリンダヘッドの設計ミスの結果、バルブの開口部を潰して圧縮比を上げたのでせっかくの4バルブながら実はそれほど大きな吸排気が出来たわけでない。それでも完全無敵エンジンとなってしまったのだから恐ろしいという他無い)
そして残りの問題、オイルの循環、エンジンの熱問題、そして重心の高さという点は、ドライサンプの導入によって劇的に改善されます。ホンダとしては初めて、当時のF-2
エンジンでもおそらく初めてで、F-1でも比較的新しい技術だったドライサンプは、もともとは航空機用エンジン技術だったのがレース用エンジンにも採用されたものです。その劇的な効果から、後にレース用エンジンでは標準的な技術となるドライサンプですが、意外によく知られて無いので、次回、この説明をします。
といった感じで今回はここまで。