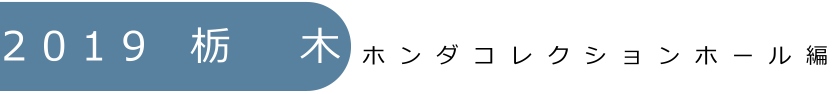

俀椫儗乕僒乕丂RC143丅
儂儞僟偑弶傔偰僶僀僋偺悽奅慖庤尃乮WGP乯偺慡愴偵嶲愴偟偨1961擭丄偦偺戞堦愴偺僗儁僀儞GP偵偍偄偰僩儉丒僼傿儕僗偑儂儞僟偵GP弶桪彑傪傕偨傜偟偨儅僔儞偱偡丅
偪側傒偵僗億僢僩嶲愴乮摿掕偺儗乕僗偺傒偵嶲壛乯偼偦偺2擭慜偺1959擭丄桳柤側杮揷廆堦榊憤巌椷姱偺嶲愴愰尵偱抦傜傟傞儅儞搰TT儗乕僗偐傜巒傑偭偰偄傑偟偨偑丄傑偩枹彑棙偺傑傑1961擭偺僼儖嶲愴傪寎偊丄偦偺戞堦愴偱桪彑偟偰偟傑偭偨偺偱偟偨丅
RC143偼偦傕偦傕慜擭丄1960擭梡偺儅僔儞偩偭偨偺偱偡偑怴宆偺RC144偺奐敪偑抶傟丄1961擭偺弶愴偵傕搳擖偝傟偨傕偺丅偑丄僩僢僾憱峴偟偰偄偨暿僠乕儉偺儅僔儞偑儕僞僀傾偟偨偺偵傕彆偗傜傟丄儂儞僟偺WGP弶桪彑幵偵側偭偨偺偱偡丅
偪側傒偵1961擭偵搳擖梊掕偩偭偨怴宆RC144偼僩儔僽儖懕偒偱嵟屻傑偱姰惉偣偢丄嵟廔揑偵僼儗乕儉偩偗傪棳梡丄偙偺RC143偺僄儞僕儞傪夵椙偟偰搵嵹偟偨2RC-143偲偄偆曄側柤慜偺儅僔儞偱偙偺擭偺125CC僋儔僗偺GP傪愴偄敳偔帠偵側傝傑偡丅偦傟偱傕11愴拞8彑偲偄偆埑搢揑側嫮偝傪尒偣偰僞僀僩儖傪妉摼丄偝傜偵偙偺儅僔儞偵忔偭偨僼傿儕僗傕嵟廔揑偵4彑傪嫇偘1961擭偺125cc僋儔僗僠儍儞僺僆儞偵側偭偰偄傑偡丅
偪側傒偵儂儞僟偼摨帪嶲愴偟偨250cc僋儔僗偱傕埑搢揑側嫮偝傪尒偣丄1961擭偼11愴拞10彑乮偟偐傕戞3愴埲崀昞彶戜撈愯傪9楢懕払惉乯偲偄偆執嬈傪惉偟悑偘傑偟偨丅儂儞僟偺擇椫儗乕僒乕奐敪偼1959擭偺儅儞搰TT儗乕僗嶲愴偐傜巒傑傝丄偦傟偼傢偢偐2擭偱埑搢揑側椡偱悽奅惂攅傪偡傞傎偳偺傕偺偵側偭偨偺偱偡丅偦偟偰偙偺1961擭偵杮揷廆堦榊憤巌椷姱偺斶婅丄儅儞搰TT儗乕僗偱傕儂儞僟偑弶桪彑傪壥偨偡帠偵側傞偺偱偡偑丄偙偺揰偼傑偨屻偱丅
偲傝偁偊偢擔杮偺媄弍偑弶傔偰悽奅偵捠梡偟偨擭偑偙偺1961擭偱偁傝丄偦傟傪惉偟悑偘偨偺偑杮揷廆堦榊棪偄傞杮揷媄尋岺嬈丄偡側傢偪儂儞僟偩偭偨偲峫偊偰偄偄傛偆偵巚偄傑偡丅
偨偩偟屻偵偙偺宱尡傪婎偵1964擭偐傜帺怣枮乆偵巐椫偺F-1GP偵嶲愴偟偨儂儞僟偼戝偄偵嬯愴傪嫮偄傜傟傞偙偲偵側傝傑偡偑乧丅
偪側傒偵嵟弶偺儂儞僟2椫GP僠乕儉偺娔撀偼1973擭偵杮揷廆堦榊憤巌椷姱偺愓傪宲偄偱擇戙栚杮揷媄尋岺嬈乮儂儞僟乯幮挿偲側傞壨搰婌岲乮偒傛偟乯偝傫偱偟偨乮屻偵1966擭僀僊儕僗GP偺堦愴偩偗戞堦婜儂儞僟F1偺娔撀傕偟偨乯丅
偝傜偵偪側傒偵丄偦偺師偺嶰戙栚幮挿偺媣暷
惀巙乮偨偩偟乯偝傫傕摉弶擇椫GP偺僄儞僕儞奐敪僠乕儉偵嵼愋偟偰偄偨恖偱偡丅偝傜偵屻偵揱愢揑側嫮偝傪屩偭偨儂儞僟偺戞堦婜丂F-2慡惙帪戙乮1966-67乯偺僽儔僶儉丒儂儞僟F2僠乕儉偺僄儞僕儞愝寁扴摉幰偲側傝丄摨帪偵儂儞僟懁偺愑擟幰傪柋傔偨恖偱偟偨乮66擭戞嶰愴傑偱丅偙偺擭僽儔僶儉丒儂儞僟偼儓乕儘僢僷F2偱12愴拞11彑乯丅
偦偺師偺巐戙栚幮挿丂愳杮怣旻偝傫偼媣暷偝傫偺壓偱F-2僄儞僕儞偺夵椙傪扴摉偟偨屻丄偦偺屻傪宲偄偱愑擟幰偵廇擟丄偝傜偵戞堦婜儂儞僟F1嵟屻偺3000噒僄儞僕儞偺愝寁傪扴摉偟乮屻偵僀僞儕傾GP偱侾彑傪偁偘傞乯丄偦偺屻儂儞僟偺墿嬥婜丄戞擇婜F1嶲愴傪庡摫偟偰嵟弶偺僄儞僕儞愝寁偲弶戙娔撀傪柋傔偨恖暔偲側偭偰偄傑偡丅
偮傑傝儂儞僟偺幮挿偼戞巐戙栚傑偱儗乕僗愑擟幰傪宱尡偟偨恖暔偑懕偄偨偙偲偵側傞傢偗偱偡丅
屲戙栚埲崀偺幮挿偼儗乕僗娔撀埲奜偑懕偄偰傑偡偑丄偦傟偱傕榋戙栚偺暉堜埿晇乮偁偺暉堜惷晇偝傫偺嶰抝偱偁傞乯偝傫偼丄僶僀僋偺GP儅僔儞丄NR500傗NS500偺奐敪愑擟幰偱偟偨偐傜丄2019擭傑偱偺儂儞僟慡8恖偺幮挿偺偆偪丄儗乕僗娭學幰偱柍偄偺偼3恖偩偗側偺偱偡乮杮揷廆堦榊憤巌椷姱偼崙撪儗乕僗帪戙偵偝傫偞傫嶲愴嵪傒乯丅
偝傜偵尵偊偽枹偩偵慡堳偑媄弍幰弌恎丄偡側傢偪棟宯幮挿偱偁傝丄拞偱傕僄儞僕儞奐敪扴摉幰偑懡偄乮8恖拞6恖乯偲偄偆偺傕傑偨摿挜偲側偭偰偄傑偡丅僄儞僕儞壆偑偙傟偩偗幮挿傪柋傔偨悽奅揑婇嬈偼懠偵偁傑傝柍偄偱偟傚偆丅偟偐傕偦偺撪擇恖乮媣暷丄愳杮乯偼崙嵺儗乕僗偱桪彑偟偨僄儞僕儞偺愝寁幰側偺偱偡丅
偦偟偰僄儞僕儞晹栧埲奜弌恎偺嵟弶偺幮挿丄幍戙栚埳摗幮挿偑尰嵼偵帄傞嵟埆偺儂儞僟傪憿偭偰偟傑偭偨帠傪峫偊傞偲丄側傞傎偳儂儞僟偲偄偆偺偼恖傕暔傕偡傋偰僄儞僕儞偺夛幮偩偭偨偺偩側偁丄偲夵傔偰巚偭偨傝傕偟傑偡丅
儂儞僟F1戞堦婜2擭栚丄1500cc悽戙偺擇戙栚儅僔儞丄儂儞僟RA272偺1965擭嵟廔宆丅偡側傢偪儂儞僟F-1弶桪彑儅僔儞丅
埲屻丄僔儍僔乕傑偱慡儂儞僟偺儅僔儞偼堦彑傕偱偒側偐偭偨偺偱丄桞堦偺僆乕儖儂儞僟惢偱桪彑偟偨幵偱傕偁傝傑偡丅
崱偺F1偲堘偭偰僟僂儞僼僅乕僗乮壓岦偒偵幵懱傪墴偟晅偗偰僞僀儎偺僌儕僢僾傪摼傞乯傪壱偖僂傿儞僌偼側偄偟丄幵懱偺惓柺偵寠傑偱奐偄偰傑偡偑乮儔僕僄僞乕偑擖偭偰傞乯丄傟偭偒偲偟偨F1儅僔儞偱偡丅
奀榁戲懽媣偝傫偺乽F-1抧忋偺柌乿傪撉傫偩偙偲偑偁傞恖側傜戝嫽暠偱偡側丅偁偺杮偼丄傔偪傖偔偪傖側忣曬検側偺偵丄偁傑傝偵柺敀偔偰嶰擔偖傜偄揙栭偟偰撉傫偱偟傑偆撪梕側偺偱丄枹撉偺恖偼拲堄偺忋偱撉傫偱傒偰偔偩偝偄丅
巹丄偙偺悽戙偺儂儞僟F-1偺幚幵傪尒傞偺偼弶傔偰側偺偱嫸婌棎晳偱偛偞偄傑偟偨丅
1965擭偺嵟廔愴丄偦偟偰1500噒僄儞僕儞F1偺嵟廔愴乮梻1966擭偐傜3000噒偵堏峴乯偱傕偁偭偨儊僉僔僐GP偱桪彑偟偨偺偑偙偺RA272丅偨偩偟揥帵偺幵懱偼桪彑偟偨僊儞僓乗偺傕偺偱偼側偔丄儊僉僔僐偱偼5埵擖徿偲側偭偨摨椈丄僶僢僋僫儉偺傕偺丅
偪側傒偵RA偲偄偆偺偼Racing
Automobile偺摢暥帤傜偟偄偱偡丅
偙偺儊僉僔僐GP偼戞堦婜儂儞僟F1僠乕儉傪棪偄偨拞懞娔撀偵傛傞弶彑棙偱偟偨偑丄幚偼斵偼偙偺擭丄捈慜偺儗乕僗傑偱娔撀傪奜傟偰偍傝丄嵟屻偵巙婅偟偰儊僉僔僐偵忔傝崬傫偱偺桪彑偱偟偨乮偪側傒偵儂儞僟偲摨帪偵巊梡偟偰偄偨僌僢僪僀儎乕僞僀儎偵偲偭偰傕弶彑棙乯丅
摉帪丄慜擭偺僨價儏乕擭偑晄挷偱偁偭偨偺偲尰応夘擖傪孞傝曉偡杮揷廆堦榊憤巌椷姱偲徴撍偟傑偔偭偨偙偲偱斵偼F1僠乕儉偺娔撀傪堦搙夝擟偝傟丄崙撪偱怴幵奐敪偺愑擟幰偲側偭偰偄偨偺偱偡丅偑丄F1僠乕儉偼偝傜偵崿柪丄愭偵尒偨傛偆偵屻偺幮挿偱偁傞壨搰偝傫乮摉帪偺奐敪晹栧偱廆堦榊巌椷姱偵師偖抧埵偵偁偭偨乯傑偱娔撀偵堷偭挘傝弌偝傟偨偺偵挷巕偑弌偢丄嵟屻偺嶰愴丄僀僞儕傾丄傾儊儕僇丄儊僉僔僐GP偱偼嵞傃拞懞偝傫偵娔撀廇擟偺巜帵偑弌偰偄傑偟偨丅偲偙傠偑夝擟偵寖搟偟偰偄偨拞懞偝傫偼偙偺梫惪傪嫅斲偟偰偟傑偄傑偡乮偪側傒傾儊儕僇GP偼杮揷廆堦榊偑戞堦婜F1偱桞堦帇嶡偵峴偭偨儗乕僗偩偭偨偑嶴攕乯丅夛幮偺柦椷傪嫅斲偟偰傕僋價偵傕側傜側偄丄偲偄偆偺偑摉帪偺儂儞僟偺偡偛偝偐傕偟傟傑偣傫丅
偮偄偱側偑傜丄屻偺幮挿丄媣暷偝傫丄愳杮偝傫傕夛幮偵晄枮偱堦偐寧埲忋弌幮嫅斲傪偟偨帠偑偁傝丄偦傟偱傕椉幰偲傕僋價偵傕傜側傜偢丄偦傟偳偙傠偐嵟屻偼幮挿偵傑偱側偭偰偟傑偭偨偺偱偟偨丅僗僑僀夛幮偩側偲巚偄傑偡丅
偦傫側忬嫷偱偟偨偑丄偲偵偐偔崿棎偵崿棎傪廳偹傞儂儞僟F1僠乕儉傪尒偰1500噒嵟屻偺儊僉僔僐GP偩偗偼帺暘偑尒傞丄偲傛偆傗偔拞懞偝傫偼娔撀偵巙婅偟偰暅婣丄偦偙偱偄偒側傝彑棙偟偰偟傑偭偨偺偱偟偨乮僪儔僀僶乕偼儕僢僠乕丒僊儞僓乕乯丅傛偔尵傢傟傞傛偆偵崅抧儗乕僗偱嬻婥偑婓敄偩偭偨偨傔丄愴拞偵峲嬻婡僄儞僕儞偺奐敪傪宱尡偟偰偄偨拞懞偝傫偺抦幆偑惗偐偝傟偨寢壥偱偡丅偦傟偵壛偊偰傑偩3夞栚偺儊僉僔僐GP偩偭偨偺偱丄懠偺僠乕儉傕傠偔偵僙僢僥傿儞僌僨乕僞傪帩偭偰偄側偐偭偨偺偑岾偄偟偨偺偩偲巚傢傟傑偡丅
偪側傒偵桪彑偵嬃婌偟偨拞懞偝傫偼埲慜偐傜寛傔偰偄偨僇僄僒儖偺柤暥嬪丄"Veni Vidi Vici"
(棃偨丄尒偨丄彑偭偨乯傪儔僥儞岅偺傑傑懪揹偟偨偨傔乮傑偩崙嵺捠怣偼揹曬偩偭偨乯丄棟宯偽偐傝偺挬夃偺杮揷媄弍尋媶強偱偼扤傕堄枴偑暘偐傜偢丄桪彑偟偨偺偩丄偲敾柧偡傞傑偱偟偽傜偔帪娫偑偐偐偭偨偲尵傢傟偰傑偡乮徫乯丅
儂儞僟弶偺巗斕巐椫幵丄寉僩儔僢僋偺T-360敪攧偑1963擭8寧丄懳偟偰F-1敪嶲愴偑1964擭7寧31擔偺僪僀僣GP偱偡偐傜儂儞僟偼僩儔僢僋偱巐椫巗応偵嶲擖偟偨傢偢偐堦擭屻偵偄偒側傝F1GP偵嶲愴乮偨偩偟嶲愴弶擭偺1964擭偼僪僀僣丄僀僞儕傾丄傾儊儕僇GP偺嶰愴偺傒偱憱偭偨乯丄偦偟偰偦偺梻擭偵偼弶桪彑偟偰偟傑偭偨偺偱偡丅嫲傠偟偄側丄偲偄偆懠偵柍偄媄弍椡偲儗乕僗偵偐偗傞幏擮偱偟傚偆丅
偦傕偦傕摉帪偺儂儞僟巐椫晹栧偺奐敪愑擟幰丂拞懞椙晇偼嬑柋偟偰偄偨僆乕僩嶰椫夛幮偺僋儘僈僱偑搢嶻屻丄1958擭偵儂儞僟偵堏愋偡傞帪偵乽F-1傪傗傞側傜儂儞僟偵擖傝傑偡丅傗傜側偄側傜擖傝傑偣傫乿偲愰尵丄偦傟傪庴偗偨杮揷廆堦榊憤巌椷姱偼乽夛幮偼偳偆偩偐抦傜偹偊偑丄壌偼傗傝偨偄偲巚偭偰傞傛乿偲摎偊丄偦偙偱拞懞偺儂儞僟擖傝偑寛掕偟偨丄偲偄偆宱堒偑偁偭偨偺偱偡丅
偳偄偮傕偙偄偮傕儗乕僗偵嶲壛偟偰彑偪偨偔偰偟偐偨側偄丄偲偄偭偨楢拞偑廤傑偭偰偄偨偺偑摉帪偺杮揷媄尋岺嬈偺巐椫晹栧偩偭偨偲傕尵偊傑偡丅
偨偩偟幮挿偺杮揷廆堦榊憤巌椷姱偼擬椡妛傪僉僠儞偲妛傫偩偙偲偑柍偄偺偱乮帺暘偱曌嫮偦偺傕偺偑寵偄偩偲擣傔偰傞乯丄僇儞偲宱尡偺媄弍幰偱偁傝丄僶僀僋偺4僒僀僋儖250噒僄儞僕儞埵傑偱偑偦偺尷奅偱偟偨丅F-1嶲愴丄偝傜偵偼巗斕幵偺1000CC埲忋偺僄儞僕儞奐敪偲偄偭偨晹暘偱偼丄夁嫀偺惉岟宱尡偵敍傜傟偨帪戙抶傟偺敪憐偲丄偦偺撈嵸揑側棫応偐傜偺奐敪尰応傊偺夘擖偑傓偟傠儂儞僟偺懌瀏偲偱傕尵偆傋偒懚嵼偵側偭偰偟傑偆偺偱偡丅
偪側傒偵偙偺帪戙偺F1儅僔儞偼僇乕儃儞側傫偰偁傝傑偣傫偐傜丄僔儍僔乕乮幵懱乯晹偼寉検嬥懏偺憤傾儖儈惢偑晛捠偱偁傝丄梟愙偑崲擄側偺偱戞擇師戝愴偺愴摤婡偺傛偆偵枍摢昬偵傛傞儕儀僢僩巭傔偵側偭偰偄傑偡丅
偑丄儂儞僟偼扨側傞傾儖儈偱偼側偔傛傝嫮搙偺偁傞傾儖儈崌嬥偱偁傞僕儏儔儖儈儞傪嵟弶偺儅僔儞丄RA-271偱巊梡偟F1GP偵墸傝崬傒傑偡乮偨偩偟僼儘儞僩廃傝偺僇僂儖偼庽帀惢丄幵懱撪晹偺妘暻偼峾惢乯丅偪側傒偵堦晹偺僷乕僣偵偼嶍傝弌偟偺僠僞儞傑偱巊偭偰傑偟偨丅偟偐傕摉帪傑偩怴偟偐偭偨儌僲僐僢僋僔儍僔乕偵傑偱儂儞僟偼壥姼偵挧愴偟偰偄傑偡乮僷僀僾偱扨弮偱婃忎側敔宆僼儗乕儉傪慻傒丄偙傟偵嫮搙傪堐帩偝偣偨忋偱敄偄奜斅傪挘傝偮偗傞偺偑廬棃偺僷僀僾僼儗乕儉幃丄懳偟偰幚嵺偺宍忬偵嬤偄崪慻傪憿傝丄偦偙偵岤傔偺奜斅傪挘偭偰慡懱偺嫮搙傪堐帩偡傞偺偑儌僲僐僢僋幃丅嫮搙丄廳検乮摨偠嫮搙傪堐帩偡傞側傜乯偲傕偵屻幰偑桳棙偩偑傛傝崅偄媄弍椡偑媮傔傜傟傞丅偙偺曈傝偼戞擇師悽奅戝愴捈慜偺峲嬻婡偺恑壔偵偦偭偔傝偱偁傞乯丅
偑丄僕儏儔儖儈儞偺壛岺偼偦傟側傝偺僲僂僴僂偑昁梫側偺偵摉帪偵儂儞僟偵偦傫側傕偺偑偁傞傢偗偑側偔丄寢嬊娞怱偺嫮搙偼楎傝丄傾儖儈傛傝傢偢偐偵廳偔偟偐傕儀儔儃乕偵崅壙偲偄偆僔儍僔乕偵側偭偰偟傑偄傑偡乮屻偵嫮搙妋曐偵偼惉岟偟偨偑崱搙偼峝偔偰壛岺偱偒側偄偲偄偆栤戣偑敪惗丄偦傟側傜尦偺傑傑偱偄偄偲側偭偰偟傑偭偨傜偟偄乯丅
僔儍僔乕奐敪扴摉幰丄嵅栰復堦偝傫偺徹尵偵傛傟偽杮揷廆堦榊憤巌椷姱偵傛傞乽峲嬻婡偼僕儏儔儖儈儞偱憿傜傟偰傞丅僕儏儔儖儈儞偺曽偑偄偄偵寛傑偭偰偄傞乿偺堦尵偵傛偭偰偙偺曽恓偑寛傑偭偨偺偩偲偐丅寢嬊丄偙傟偱儂儞僟偺F1僠乕儉偼偄傜傫嬯楯傪堦偮攚晧偄崬傓偙偲偵側傝傑偟偨丅
偪側傒偵揥帵偺儅僔儞丄嶲愴2擭栚偺RA272偐傜偼偝偡偑偵懴怘傾儖儈惢偵曄峏偝傟偨丄偲偄偆帒椏偑偁傝傑偡偑愝寁幰偺嵅栰偝傫偼RA272傕僕儏儔儖儈儞傪巊偭偨丄偲徹尵偟偰偄傞偺偱丄偙偺儅僔儞傕僕儏儔儖儈儞惢偺壜擻惈偑崅偄偱偡丅
偮偄偱偵儕儀僢僩懪偪偺媄弍傕儂儞僟偵偼側偔丄偙偺偨傔挷晍旘峴応偵偁偭偨埳摗拤峲嬻惍旛偵偦偺嶌嬈傪埶棅偟偨偺偱偡偑丄昞柺偼僉儗僀偵枍摢張棟偝傟偰偄偨偺偵丄摲懱撪懁偼弌偭挘偭偨傑傑側偺傪尒偨杮揷廆堦榊憤巌椷姱偼庤敳偒偩偲搟傝丄嶌嬈偑堦帪拞抐偟偰偟傑偭偨偦偆偱偡丅
愝寁偺嵅栰偝傫偑娫偵擖偭偰丄摲懱撪懁偼嬻椡偵塭嬁偑側偄傫偩偐傜偙傟偱偄偄傫偩丄偲尵偭偰傕擺摼偣偢丄寢嬊丄屻擔丄杮揷廆堦榊憤巌椷姱偑尒妛偵棃側偐偭偨擔偵偙偭偦傝慡嶌嬈傪曅晅偗偰偟傑偭偨偺偩偲偐丅
埲屻丄儂儞僟偺F1偼偙偆偄偭偨杮揷廆堦榊憤巌椷姱偺旕榑棟揑偲偟偐尵偄傛偆偑柍偄墶傗傝偵擸傑偝傟懕偗傑偡丅偦偺嵟廔廔拝揰偑3000cc僄儞僕儞嶲愴嵟屻偺擭偺乬嬻椻僄儞僕儞偺F1儅僔儞乭偱巰幰傑偱弌偡斶寑傪堷偒婲偙偡偺偱偡偑丄偙偺榖偼傑偨屻偱丅
RA272偼憤儂儞僟惢儅僔儞偱偁傝丄摉慠僄儞僕儞傕儂儞僟惢丅
偲偄偆傛傝僄儞僕儞偑庡偱摉弶偼僄儞僕儞嫙媼偺傒偱嶲愴梊掕偱偟偨丅
偑丄嶲愴捈慜丄偦傟傑偱僠乕儉傪慻傓梊掕偩偭偨儘乕僞僗偺愑擟幰偺僠儍僾儅儞偑撍慠丄儂儞僟傪棤愗偭偰僐儀儞僩儕乕丒僋儔僀儅僢僋僗僄儞僕儞偺搵嵹傪寛傔偰偟傑偄丄偣偭偐偔偺僄儞僕儞偼拡偵晜偄偨懚嵼偵側偭偰偟傑偄傑偡丅
偑丄儗乕僗偑偟偨偔偰偨傑傜側偄杮揷廆堦榊憤巌椷姱偼丄偩偭偨傜僔儍僔乕傕偰傔偊偱憿傟偽偄偄丄偲慡儂儞僟偱偺嶲愴傪寛掕丄偙傟傑偨儗乕僗偑偟偨偔偰偟偐偨側偐偭偨F1儅僔儞奐敪愑擟幰偺拞懞偝傫傕偙傟偵忔偭偰偟傑偭偨偺偱偟偨丅桳柤側揹曬暥乽儂儞僟偼儂儞僟偺摴傪恑傓乿偼偙偺帪丄拞懞偝傫偑僠儍僾儅儞偁偰偵憲偭偨傕偺偱偡丅
偪側傒偵1500噒側偑傜V宆12婥摏乮婥摏1杮偁偨傝125cc乧乯丄偟偐傕DOHC偱4僶儖僽丄12000rpm傑偱夞偭偰乮14000偱傕戝忎晇偩偭偨愢偁傝乯嵟廔揑偵偼230攏椡傪弌偟偨丄偲偄偆僗僑僀偟傠傕偺偱丄悢帤偩偗尒傟偽廫暘偵悽奅儗儀儖偺僄儞僕儞偱偟偨丅偨偩偟偙偺嬅偭偨愝寁偺偨傔偵戝暆側廳検憹傪彽偒丄懠偺儊乕僇乕偺F1僄儞僕儞偵斾傋摉弶偼30噑嬤偔廳偐偭偨偲尵傢傟偰偄傑偡丅
偙偺攏椡偼偁傞偗偳廳偄丄偼嵟屻傑偱戞堦婜儂儞僟F1偵晅偒傑偲偭偨栤戣偱傕偁傝傑偟偨丅
偙偺僄儞僕儞偼偦傟偱傑偱崙嵺儗乕僗偱廫暘側惉愌傪巆偟偰偄偨擇椫偺儗乕僗奐敪晹栧偑扴摉偟偰傑偟偨丅1500噒偱12婥摏偲偄偆偺傕丄斵傜偑摼堄偲偟偰偄偨堦婥摏125噒亊12亖1500噒偲偄偆扨弮側寁嶼偐傜弌偨傕偺偩偭偨偲偄偆愢偑偁傝傑偡乮偨偩偟偙偺榖偼傗傗夦偟偄丅摉帪偺儂儞僟2椫儗乕僒乕偼彫攔婥検側偺偵懡婥摏偑摿挜偱丄125cc偱4婥摏丄250噒偵帄偭偰偼6婥摏僄儞僕儞偱1婥摏125噒側傫偰僄儞僕儞偼柍偐偭偨乯丅
愭偵偪傚偭偲愢柧偟偨媣暷偝傫偺F2梡寙嶌僄儞僕儞偑搊応屻丄F1偺僄儞僕儞奐敪傕巐椫晹栧偵堏傞偺偱偡偑丄摉弶偼偡偱偵悽奅傪惂攅偟偰偄偨擇椫儗乕僒乕偺奐敪晹栧偑旲懅傕偁傜偔F1偵傕嶲壛偟偰偄偨偺偱偡丅
偙偺偨傔丄擇椫幵偺僄儞僕儞愝寁庤朄偑偦偺傑傑帩偪崬傑傟傞偲偄偆慜戙枹暦偺僄儞僕儞偲側傝丄僔儕儞僟乕働乕僗偼墶抲偒丄摉慠丄僋儔儞僋働乕僗傕墶抲偒偲側傝傑偡丅偑丄偙傟偱偼偦偺屻傠乮偲偄偆偐峔憿忋墶偵側傞乯偵暲傋偰僊傾儃僢僋僗偑抲偗側偄偺偱丄擇抜峔憿偵偟偰丄僔儕儞僟乕働乕僗偺壓丄傗傗庤慜偵弌偭挘偭偨壓抜偵墶暲傃偵廂傔傑偟偨丅偝傜偵僄儞僕儞杮懱偲僊傾儃僢僋僗偼堦懱宆偱暘棧晄擻偲側偭偰傑偡丅偙偺曈傝偺峔憿偼2椫偺惉岟偱帺怣枮乆偩偭偨杮揷廆堦榊憤巌椷姱偺堄岦偩偭偨丄偲偄偆榖傕偁傝傑偡丅
偑丄偙偺峔憿偑屻偵惍旛惈偺埆壔偱戝栤戣偲側傝傑偡丅椺偊偽僊傾斾傪曄偊傞丄偁傞偄偼僊傾偑杸栒偟偨偺偱曄偊傞丄偲偄偆応崌捠忢偺F1儅僔儞偱偼僄儞僕儞偺屻傠偵捈寢偝傟偰傞僊傾儃僢僋僗傪奜偟偰奧傪奐偗傟偽嵪傫偩偺偑丄儂儞僟偱偼偦偺偨傃偵偨偩偱偝偊廳偄僄儞僕儞傪崀傠偟丄慡晹傪暘夝偟偨偆偊偱僊傾傪曄偊傞丄偲偄偆庤娫偑偐偐傞帠偵側傝傑偡丅
V12偺墶抲偒儗僀傾僂僩偱偡偐傜丄僄儞僕儞偺墶暆偑僨僇偄偺偱丄幵懱屻晹偺嵍塃偵嬻娫偑慡偔側偄忬懺偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅偦傟偳偙傠偐晛捠偵僔儍僔乕傪慻傫偱偄偨傜屻晹偩偗偑戝偒偔嵍塃偵挘傝弌偟偰偟傑偆帠偵側傝傑偡丅偙偺偨傔幵懱屻晹偺僔儍僔乕偼庢傝暐傢傟僄儞僕儞偺傒偑抲偐傟傞峔憿偲側傝傑偡丅偡側傢偪慜敿偺僔儍僔乕屻晹偵寽壦幃偵僄儞僕儞偑捈寢偝傟丄偦偺僄儞僕儞偵捈愙僒僗儁儞僔儑儞偺巟帩晹傪庢傝晅偗傞丄偲偄偆峔憿偵側偭偰傑偟偨乮幵懱墶偵巐杮偺巟拰偑屻傠傑偱怢傃丄偙傟偱僄儞僕儞偲僒僗儁儞僔儑儞傪巟偊偨乯丅
偙傟偼戞擇師戝愴婜偺僄儞僕儞偺庢傝晅偗曽傪嶲峫偵偟偨丄偲偄偆帠偱偡偑丄偝傜偵幵懱屻敿晹偺嫮搙堐帩傪僄儞僕儞偑扴偆峔憿偩偭偨傢偗偱偡丅

1500噒帪戙偺儂儞僟F1偑丄V12僄儞僕儞側偺偵塣揮惾屻傠偺僄儞僕儞晹偑柇偵抁偄偺偼墶抲偒儗僀傾僂僩偩偭偨偐傜丅偦偟偰塣揮惾屻晹偺幵懱墶偐傜曅懁擇杮偺寽壦巟帩朹偑僞僀儎榚偺僒僗儁儞僔儑儞峔憿偵怢傃偰傞偺偑敾傞偐偲丅
偦偟偰愭偵愢柧偟偨傛偆偵丄摉帪偺儂儞僟偼偦傕偦傕巐椫偺愝寁宱尡偑柍偐偭偨偺偱慡偰庤扵傝偱偟偨丅
僔儍僔乕愝寁偼巐椫晹栧偺扴摉偩偭偨偺偱丄偙傟偑僨價儏乕嶌偩偭偨擖幮4擭栚偺庒庤丄嵅栰復堦偝傫乮搶戝偺峲嬻妛壢弌恎偩偭偨偺偱傾儖儈儌僲僐僢僋儃僨傿偵揔擟偲偝傟偨乯丄僒僗儁儞僔儑儞側偳偺懌夞傝偼擔栰帺摦幵偐傜F1偑傗傝偨偔偰堏愋偟偰偒偨晲揷塸晇偝傫偑扴摉偟偨偺偱偡偑丄幚嵺偺巐椫愝寁宱尡幰偼晲揷偝傫側偳偛偔彮悢偱丄偙偺偨傔婎杮拞偺婎杮偺尋媶偐傜奐敪偑巒傑偭偰偄傑偡丅
傛偭偰巐椫愝寁偱偼忢幆偲偝傟傞帠偡傜媍榑偺懳徾偵側傝丄偁傞擔丄幵懱偺崉惈偼嫮偄曽偑偄偄偐庛偄曽偑偄偄偐丄偲偄偆栤戣偑榖偟崌傢傟傑偟偨丅幵懱偺崉惈偑掅偄偲僇乕僽側偳偱榗傫偱偟傑偄丄偦偙偵宷偑傞僞僀儎傪巟偊傞僒僗儁儞僔儑儞偑偒偪傫偲摥偐側偔側傝傑偡偟丄戝攏椡偺幵側傜幵椫偑杸嶤偱幵懱傪慜偵墴偟弌偡偲偒傕丄偦偺椡偺堦晹偑慜恑偵偱偼側偔丄幵懱偺曄宍偵徚旓偝傟偰偟傑偄晄棙偱偡丅
愝寁幰側傜忢幆偺斖醗偱偟偨偑丄儂儞僟F1偺愝寁拞偵偙傟偑専摙偝傟傞偲丄嬃偔傋偒偙偲偵僔儍僔乕偺崉惈偼掅偄曽偑偄偄偲庡挘偡傞楢拞偑媍榑偵彑偭偰偟傑偄丄悢彮側偄幚柋宱尡幰偩偭偨晲揷偝傫側偳偼偁傢偰偰巭傔偵擖偭偨偦偆側丅
偦偆偄偭偨拞偱嶲愴擇擭栚偵偟偰愴慜偐傜儗乕僗偵柧偗曢傟偰偄偨楢拞憡庤偵堦彑傪偁偘偰偟傑偭偨傫偩偐傜丄摉帪偺儂儞僟丄偍偦傞傋偟偱偟傚偆丅
偲偄偭偨姶偠偱丄傑偩擖傝岥儂乕儖偵擖偭偨偽偐傝偱偡偑丄偲傝偁偊偢崱夞偼偙偙傑偱丅
傑偩傑偩懕偔偺偱偁傝傑偡丅